倉庫内作業者は人手不足で、需要が増大。そのぶん時給が高い!
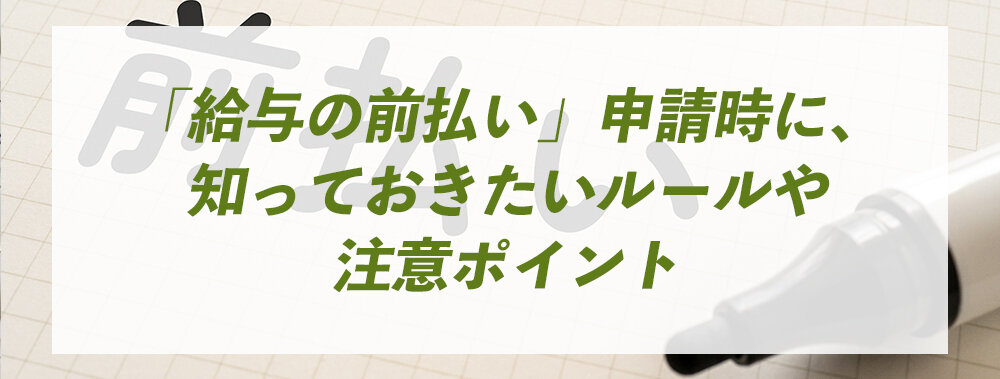
2024/1/15 更新
国民生活や経済活動を支える倉庫業
製造(生産)者と消費者の中間地点に位置し、物品を倉庫で保管する事業を倉庫業といいます。
倉庫業は、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物など、多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っていることから、国民生活・経済活動を支えるきわめて公共性の高い産業に位置づけられます。
そのため、国が定める倉庫業法では、物品ごとの倉庫の種類が定められているほか、保管される物品も、種類によって第一類~第八類に分類されています。
倉庫業法に定められた「倉庫」の主な種類
ひとくちに「倉庫」といっても、さまざまなタイプの倉庫があり、私たちが普段よく目にする建屋の「倉庫」は設備・構造基準によって一類、二類、三類の3つに分類され、それ以外にも「野積倉庫」「水面倉庫」があります。

オートメーション化や、特殊な目的をもった倉庫
上記で紹介した以外にも、以下のような種類・特性をもつ倉庫があります。
-
-
■貯蔵槽倉庫/高温多湿下で保管すると劣化しやすい、袋に梱包されていない状態(バラ状)の米、小麦、トウモロコシなどの穀物類を保管する倉庫。「穀物倉庫」とも呼ばれる
-
-
-
■危険品倉庫/消防法が指定する危険物や高圧ガスなど保管する倉庫。保管する物品の種類によって法で定められた防火設備の設置、防犯措置等の規定を満たす必要がある
-
-
-
■冷蔵倉庫/常に10度以下で保管する必要がある農畜産物、生鮮品、凍結品等の加工品等の物品を保管する倉庫。法律では保管温度が常時摂氏10度以下に保たれている、見やすい位置に温度計を設けるなどが定められている
また最近、社会情勢の変化や災害によって、次のような「倉庫」の存在意義も高まっています。
-
-
-
■特別倉庫/災害の救助その他公共の福祉を維持するために国土交通大臣が定める倉庫。阪神淡路大震災、東日本大震災に起きた物資の調達・輸送時混乱、被災者の生活必需品の入手難といった状況を教訓に、緊急支援物資を保管する倉庫
-
-
-
■自動倉庫/特殊倉庫などをコンピュータによって一元管理する仕組みを取り入れた倉庫。とくに、冷凍・冷蔵品、重量物、危険物等を取り扱う「特殊倉庫」では、省人化をめざし自動化が進められている
-
-
-
■特殊倉庫/保管物や入出荷の環境などに合わせた自動化や、特殊な機能性を有した倉庫
-
人手不足の倉庫業界には、どんな仕事がある?
無数の小型ロボットが倉庫内を縦横無尽に駆け回り、製品棚から商品をピックアップして出荷窓口の担当者のもとに商品を届ける超進化系の倉庫が最近大きな注目を集めていますが、一般的な私たちの家の近所にある倉庫は、どのような流れで仕事(作業)が進められているのでしょうか。仕事の流れと作業内容は、主に下記イラストのようになります。

倉庫は、製造(生産)者の製品・物品を、お客様のもとに届ける橋渡し的な存在であるため、一般的な倉庫では日々大量の製品が倉庫に「納入」され、注文によって「選別」され、指定の日時にその物品がお客様のもとに届くよう「出荷」される……といった流れをとります。
こうした流れから、倉庫で作業する人の多くが、貨物・資材・製品などさまざまな物品の「搬入&開梱」「検品」「整理棚へのストック」「ピックアップ」「搬出」「積み卸し・積み直し」「仕分け」「梱包」「荷積み」などの業務に従事しています。
倉庫作業者のメリット
時給が高い
慢性的な人手不足にあり、肉体を使う仕事が多いことからも、倉庫作業者の時給は比較的高く設定されています。全国で最も時給が高い東京での倉庫作業者の時給は1300円以上(派遣)、1200円以上(アルバイト)が相場です。今夏に最低賃金が引き上げられたことによって、時給は今秋以降上昇と見込まれています。
人間関係のわずらわしさがない
ひとつの作業や一工程を担当することが多いため、人間関係のわずらわしさがないことも倉庫作業者のメリットです。職場によって少人数のチーム制で業務を担当することもありますが、その場合も過剰なコミュニケーションは必要としないと考えてよいでしょう。
休みが取りやすく、融通がきく
作業内容がマニュアル化されているため初心者でもすぐに慣れることができる仕事が多いといえます。そのため、アルバイト仲間にシフトを替わってもらうなどすれば休みも取りやすく、急に体調が変化する幼児を保育所に預けている親御さんや、自宅で家族を介護している人にとって融通がきくメリットがあります。
外まわりに行ったり、上司の顔色を窺うことも少ない
黙々と自分の仕事をこなす倉庫作業者は、基本的に自分に課せられた作業を正確にこなすことが求められているので、よほどのことがない限り、上司から叱責されることはありませんし、営業職のように外まわりに出かけたり、他部署や業務が異なる人とコミュニケーションを取る必要はありません。

倉庫作業者のデメリット
体を使うことが多く、日々の体調管理が大切
指定された作業服を着て倉庫内で作業することが一般的ですが、なかには重量物を運ぶ、同じ姿勢で業務を続ける、単調な動作を長時間繰り返す……といったケースもあるため、足腰、手・腕などに支障が生じることも。
過酷な環境で作業をすることも
指定された作業服を着て倉庫内で作業することが一般的ですが、なかには重量 倉庫の種類によって炎天下や摂氏10度以下の冷蔵倉庫や、20度以下の冷凍倉庫で業務に従事することもあります。空調設備があっても、巨大な倉庫では空調管理が万全に行き届かないこともありますので、職場環境に不安がある場合は事前にきちんと確認しましょう。
単調な作業が続く
指定された作業服を着て倉庫内で作業することが一般的ですが、なかには重量 出荷指示書に基づき、巨大倉庫の商品棚から物品をピックアップする業務を担当した場合、その作業が毎日繰り返し続けていくことになります。そうした特徴から、飽きっぽい人や集中力に自信がない人は、倉庫の仕事には向いていないといえるかもしれません。逆に、同じ仕事を黙々とこなすことで高い時給をもらっている……といった割り切り感を持って仕事に臨める人には、倉庫での仕事に向いているといえるでしょう。

どんなに自動化が進んでも、やはり人が必要
冷凍・冷蔵品、重量物、危険物などを取り扱う倉庫では、体力的にきつく、作業員の負担が大きいことから、人材を募集してもなかなか集まりらない傾向にあります。
あるいは、ネットショッピングなどを利用する人が増大し、多種多様な商品が取り引きされるようになった現在は、そのためこうした倉庫では製品の受け入れ、保管、出荷までをオートメーション化する「自動倉庫」化の動きが加速しているのですが、自動化がいくら進んでも、そこには必ず“人”が必要です。
Amazonの新巨大物流拠点では、小型ロボット2000基が天井近い高さの商品棚が林立する倉庫内を縦横無尽に動きまわり、注文商品をピックアップする“超効率化”が推し進められています。これらの進化系ともいえる倉庫の様子はすでにさまざまなメディアでも報じられていますが、今後、どんなに進化したとしてもロボットが運んできた商品をチェックし、その商品を出荷・配送にまわす“人手”はやはり必要でしょう。

現在は、倉庫作業者として多くの女性が活躍中
ネットショッピングを利用する人が増大したことで、物流にかかわる従業員の人手不足や労働時間が社会問題になっているいま、倉庫でもさまざまな変化が起きています。また、すべての倉庫で自動化が進められているわけではないことからも、他の業種で働くアルバイトより時給が高めに設定されている倉庫での作業は、稼ぎたい人にとって魅力ある仕事といえるでしょう。
また、倉庫作業者というと「重い荷物を運ぶつらい重労働」「単調で飽きやすい」「倉庫で働く知り合いが腰を痛めた」というネガティブイメージを抱いていた人も過去には多かったのですが、今日では重い荷物の搬送はフォークリフトを活用して効率化を図るところが増えていますし、数多くの女性がイキイキと活躍する職種に様変わりしています。
人間関係にわずらわされることなく、黙々と仕事ができて、時給も高めで、女性も多く活躍している……そんな倉庫作業者は、時代の変化によってさらに働きやすい環境に整えられていくことでしょう。短期で集中的に稼ぎたい、人づきあいが苦手な人……という人には、注目の職場かもしれませんね。
