期間工はどうやって税金を支払うの?使える控除や退職後の注意点も解説
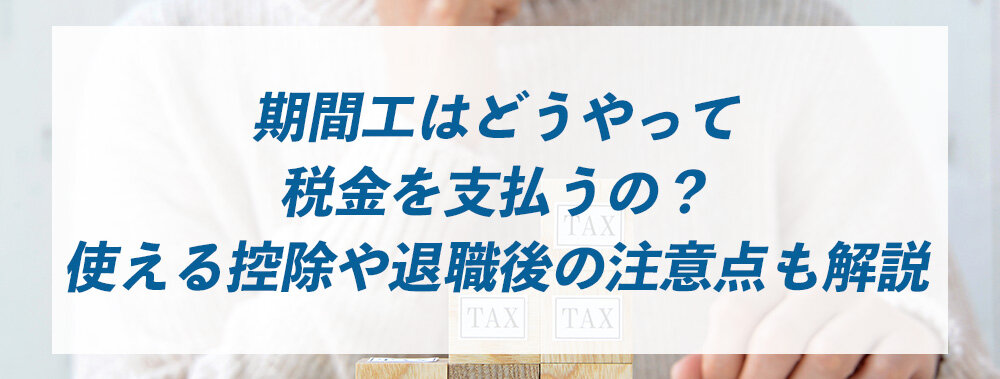
2024/5/15 更新
期間工の税金の納付方法は?
期間工は自分で税金を納めなくてもOK
期間限定で働く期間工は、雇用期間に定めのない正社員と雇用形態が異なるため、どうやって税金を支払えばいいのか、気になる人も多いのではないでしようか。
結論から言うと、期間工は自分で手続きをして税金を納める必要はありません。期間工はメーカーに直接雇用される契約社員となるため、正社員と同じく給料から各種税金が天引きされるからです。期間工として働いている間は、税金の計算や支払いなどを含め、すべて雇用先の会社が行ってくれますので、税金についてさほど心配する必要はないでしょう。
給料から天引きされる税金や社会保険料は?

多くの場合、期間工は会社の社会保険に加入しますので、税金とともに社会保険料も給料から天引きされます。期間工の給料から天引きされる主な税金・保険料は以下の通りです。
-
-
《1》所得税……給与などの所得に対してかかる税金
《2》住民税……居住している都道府県・市区町村に納める税金
《3》社会保険料……厚生年金・健康保険(被用者保険)など
※住民税は前年の年収から計算されるため、期間工として働く前に無職だった場合は、2年目から天引きされます
※厚生年金と社会保険の保険料は、勤務先の会社と本人が折半します(本人負担は半分)
-
上記《1》~《3》のいずれも、課税額(天引きされる金額)は年収によって異なりますので、具体的な金額などの詳細については、以下の各サイトを参考に算出してみてください。
※参考(所得税):No.2260 所得税の税率|国税庁
※参考(住民税):総務省|地方税制度|個人住民税
※参考(社会保険料):保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) |日本年金機構
※参考(社会保険料):令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
期間工の年末調整について
期間工になれば、税金の計算や支払いは会社が行ってくれますが、過不足なくきちんと税金を支払うためには年末調整が必要となる場合があります。
年末調整とは?

年末調整とは、その年に支払っていた(源泉徴収として天引きされていた)税金と、本来納めるべき税金(正式な税額)のズレを是正するための手続きです。毎月の給料から天引きされる税金は、あくまでも概算した金額(仮定額)となるため、本来納めるべき税金の額と違っている可能性があるからです。
こうして、その年の所得額が決定した年末の時点で、正式な税額を再計算して差額を確認し、過不足分があれば還付または追加徴収されます。とくに、以下のようなケースに当てはまる人は、年末調整での申告が必須となります。
-
-
【年末調整が必須となる主なケース】
●扶養する家族が増えた・減った
●本人が障害者・寡婦・ひとり親になった
●配偶者や扶養家族が障害者となった
-
期間工が年末調整を行う方法

期間工として働いていれば、その年の11月~12月ごろに、雇用先の会社から年末調整の申告書類を渡されます。書類は自分で記入する必要がありますので、記入方法や申告について不明な点があれば、会社に直接相談するか、国税庁のサイト(以下参照)で確認しておきましょう。
※参考:No.2662 年末調整のしかた|国税庁
※参考:給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)|国税庁
期間工が利用できる主な控除について
控除(こうじょ)とは「金額などを差し引く」という意味です。先述した年末調整では、各種の控除を申請することで、支払いすぎた税金の還付を受けることも可能です。では、期間工が利用できる主な控除4つ(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除)について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
配偶者控除

配偶者の年間所得金額が48万円以下の場合、納税者本人(控除を受ける本人)の収入によって最高38万円の配偶者控除が受けられます。また、配偶者の所得が給与所得のみの場合は、給与所得控除額が55万円なので、その年の給与所得が103万円以下であれば(103万円-55万円=48万円となるため)配偶者控除が利用できます。
配偶者控除における配偶者とは、婚姻届を受理された者で、居住状況に関わらず生計を共にする者という条件があります。また、納税者本人の年間所得金額が1000万円を越える場合は、配偶者控除を利用することはできません。期間工として年収が1000万円を越えるケースはまれですが、副業などの収入が多ければ利用できない場合もありますので、上限条件として覚えておきましょう。
配偶者特別控除
配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除が利用できます。受けられる控除額は、納税者本人と配偶者の所得に応じて最高38万円となっています。
こちらも控除の対象となる配偶者の条件(婚姻届や生計に関する条件)は同じで、本人の年間所得金額が1000万円以下という条件があります。また、配偶者特別控除は配偶者控除と併せて(両方)利用することはできません。
扶養控除

配偶者以外に扶養する親族(年間所得金額43万円以下の親や子どもなど)がいる場合、扶養控除を利用することができます。
控除額は扶養対象となる人の年齢によって異なり、16歳以上で38万円、19歳~23歳未満で63万円となっています。また、70歳以上の親族を扶養する場合は、同居の有無で控除額が異なり、同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円です。
※参考:No.1180 扶養控除|国税庁
障害者控除

生計を共にする配偶者や扶養する親族、または納税者本人が所得税法の障害者に当たる場合、障害者控除を利用することができます。障害者控除には障害の程度によって「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3区分があり、「障害者」の控除額は27万円、「特別障害者」の控除額は40万円、「同居特別障害者」の控除額は75万円となっています。
本人や家族がどの区分に該当するのかは、障害の程度や生活状況によって異なりますので、不明な点があれば居住する地域の役所に相談してみましょう。
※参考:No.1160 障害者控除|国税庁
期間工を退職した後の税金はどうする?
期間工の税金に関して注意したいのが退職後です。期間工を辞めた後は、税金や保険などの手続き・支払いを自分で行う必要があるからです。ここでは、期間工を退職した後の税金・保険の扱いについて解説します。
住民税について

住民税は前年の所得に対して納税額が決まるため、収入があった翌年に前年の住民税を支払うことになります。つまり、期間工として働いていた最後の年の住民税は、退職後に自分で納付しなければいけないため、再就職しないのであれば、ある程度貯金をして備えておくことが大切です。
健康保険について

健康保険には、大きく分けて被用者保険(社会保険)と国民健康保険の2種類があり、期間工として働いている間は会社の被用者保険に加入します。しかし、期間工の契約期間が満了した後は退職となるため、これまでの被用者保険を任意継続(最長2年間)するか、国民健康保険に加入するかを選択し、手続きや支払いを自分で行う必要があります。以下、それぞれのケースの注意点を見ていきましょう。
-
-
【これまでの被用者保険を任意継続する場合】
被用者保険の任意継続は、退職後20日以内に、加入する保険組合へ必要書類を添えて申請する必要があります。なお、在職中は会社と折半していた保険料が、退職後は全額自己負担となります(負担額の上限あり)。【国民健康保険に加入する場合】
被用者保険から国民健康保険に切り替えて加入する際には、居住する地域の役所へ必要書類を添えて申請する必要があります。なお、国民健康保険の保険料は、地域や年齢、収入などによって異なるため、居住する市区町村のサイトなどで確認してください。
-
年金保険について
年金保険には基礎年金となる「国民年金保険」と、会社で加入する「厚生年金保険(社会保険)」の2種類があり、期間工として働いている間は会社の厚生年金保険に加入します。しかし、期間工の契約期間が満了した後は退職となるため、国民年金保険に加入して自分で保険料を支払わなければいけません。
厚生年金から国民年金へは自動的に切り替わらないため、国民年金に加入する際には、居住する地域の役所で手続きをする必要があります。加入の手続きには、退職日を証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書など)と年金手帳が必要となりますので、忘れないようにしましょう。
まとめ
期間工は最長2年11ヵ月の契約期間が満了すると退職することになりますが、在籍中は会社が税金に関する手続きを代わりに行ってくれます。毎年12月ごろの年末調整や利用できる控除についてしっかり押さえておけば、税金の払い忘れや払いすぎを心配する必要はないでしょう。
ただし、期間工を退職した後、しばらく働かない期間がある場合は、税金や保険料の手続き・支払いを自分で行わなければいけません。よって、期間工として働きながらも、税金に関する本を読んで勉強したり、わからないことがあれば役所に相談したりするなど、税金や保険に関する基礎知識を得ておくようにしましょう。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験者歓迎・学歴不問の工場ワークを多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。正社員就職を目指す高卒フリーター方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
