期間工からの転職のポイント/再就職先や職種の選択肢をケース別に紹介!
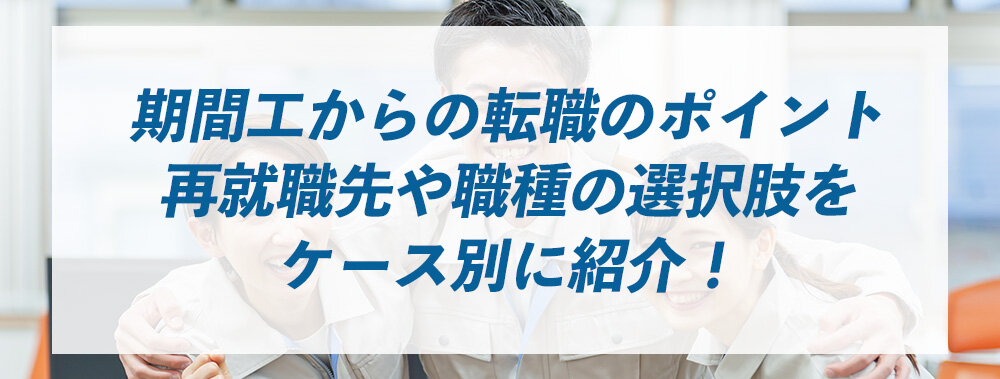
2024/5/7 更新
-
■目次
- 1.期間工からの転職【選択肢1】期間工を続ける
-
・同じ会社の期間工として再契約(再入社)する
・別の会社の期間工として働く
・期間工を続けるメリット・デメリット
- 2.期間工からの転職【選択肢2】期間工として働きながら正社員を目指す
-
・期間工が正社員に登用されるための条件
・期間工から正社員になるメリット・デメリット
- 3.期間工からの転職【選択肢3】期間工以外の仕事に就く
-
・期間工とは異なる職種・業種の企業に転職する
・フリーランスとして独立・起業する
- 4.期間工からの転職/失業手当・再就職手当も要チェック!
-
・失業手当について
・再就職手当について
- 5.期間工や製造業のお仕事探しなら<工場求人ナビ>へ!
期間工からの転職【選択肢1】期間工を続ける
期間工の転職において、まずひとつ目の選択肢となるのが「期間工を続ける」ことです。以下、期間工を続ける場合の2つのパターンを紹介します。
同じ会社の期間工として再契約(再入社)する
先述したように、期間工は数ヵ月(2~3ヵ月)ごとの契約更新を繰り返しながら、最長2年11ヵ月の契約期間が満了すると退職しなければいけません。これは「同じ企業で3年以上勤務する従業員は、正社員として雇用しなければならない」と労働基準法で定められているからです。
ただし、満了退職後からクーリング期間(最長6か月 )が経過していれば、同じ会社の期間工として再契約(再入社)することが可能です。再入社までややブランクは生じるものの、事情を知った同じ職場で働けるのは安心感がありますし、会社側にとっても仕事に慣れた経験者を雇えるというメリットがあります。とはいえ、前回の勤務態度や辞め方に問題があった場合(遅刻・欠勤などが多い、自己都合で契約途中に退職など)、再入社はやや厳しくなるかもしれません。
別の会社の期間工として働く

二つ目のバターンは、別の会社の期間工として働くことです。先のバターンのように、期間工として同じ会社で働くには、クーリング期間をおく必要がありますが、別の会社であれば、退職後すぐに働き始めることができます。応募する際にも、期間工として働いた前職の経験が強みとなりますし、採用においても大きなアドバンテージになるでしょう。
期間工を続けるメリット・デメリット

同じ会社であっても、別の会社であっても、期間工を続けることにはメリットもあればデメリットもあります。自分にとって期間工を続けるのがプラスなのか、マイナスなのか、メリット・デメリットを照らし合わせて判断することが重要です。
-
-
【期間工を続けるメリット】
●満了慰労金などの手当をもらいながら、短期間で効率的に稼げる
●会社の格安・無料の寮を利用しながら、生活費を抑えて貯金を増やせる【期間工を続けるデメリット】
●経験を積んでも特別なスキルが身につけにくく、経歴として評価されにくい
●会社の格安・無料の寮を利用しながら、生活費を抑えて貯金を増やせる
●ほかの仕事と比べて給与や待遇が良いため、期間工を延々と続けるループから抜け出せなくなる可能性がある
●正社員と比べて雇用が安定しないため、将来に不安を抱えやすい
-
期間工からの転職【選択肢2】期間工として働きながら正社員を目指す
二つ目の選択肢が「期間工として働きながら正社員を目指す」ことです。 期間工を募集している会社の多くは正社員登録制度を設けており、期間工としての働きが認められると、契約終了後にそのまま正社員になれるチャンスがあります。とくに、正社員登録制度のある大手自動車メーカーでは、毎年、相当数の期間工が正社員に登用されており、なかには登用率が80%を超えるメーカーもあります。
期間工が正社員に登用されるための条件

大手メーカーの通常の正社員採用の場合、多くは高卒・大卒などの学歴が応募条件となっていますが、期間工から正社員になるために学歴は関係なく、実際に中卒でも正社員に登用されるケースが多々あります。 ただし、期間工が正社員に登用されるためにはいくつかの条件があり、それをすべてクリアする必要があります。細かい登用条件は会社によって異なりますが、一般的には以下のような条件が基本となります。
-
-
【正社員登用条件の一例】
●期間工として半年~1年以上勤務している
●年齢は20~30代が中心(年齢制限のない会社もあり)
●勤務態度が良好(遅刻や無断欠勤がないなど)
●上司から正社員登用の推薦を受ける
●正社員登用試験(筆記・面接など)に合格する
-
期間工から正社員になるメリット・デメリット

正社員になると基本的に定年まで雇用が保証され、退職金も支給されますので、将来への不安も少なくなるでしょう。また、長く働いて実績を積めば昇給・昇格が期待でき、キャリアアップにともなって役職手当なども支給されます。
一方で、労働条件が「期間限定・高報酬」という設定の期間工は、短期間で効率的に稼げるので、正社員になると期間工で働いていた時より、給与や年収が下がってしまうケースもあります。また、職場を管理する正社員として、責任が重い業務(部下のマネジメントや現場管理など)を任せられることも多くなるため、人によってはストレスを感じるかもしれません。
期間工からの転職【選択肢3】期間工以外の仕事に就く
三つ目の選択肢が「期間工以外の仕事に就く」ことです。たとえば、期間工とは異なる職種・業種の企業に転職する、フリーランスとして独立・起業する、といったバターンです。以下、それぞれのケースについて見ていきましょう。
期間工とは異なる職種・業種の企業に転職する

期間工とはまったく異なる職種・業種に転職する場合、基本的にはゼロからのスタートとなります。よって、期間工が一般企業の求人に応募する際には、人手不足の業種や未経験OKの職種を選ぶことが、採用を勝ち取るための基本となります。
たとえば、人手不足が深刻化している製造業、建設業、介護業、物流業、サービス業などの企業は、実務経験や資格不問の求人が多く、期間工からの転職先としても狙い目です。求人の多い主な職種としては、製造職や工場スタッフ、建設現場の作業員、介護職、物流業やタクシーのドライバー、営業職、警備員、販売員などがあり、とくに製造職の場合は、工場で働いていた期間工の経験がプラスに評価される可能性もあります。
ただし、はじめはどの職種も、期間工より収入が低くなることは覚えておきましょう。
フリーランスとして独立・起業する

企業に就職せず、フリーランスとして独立・起業するのもひとつの方法です。独立・起業にはある程度の開業資金が必要となりますが、期間工は短期間で効率的に稼げるので、目標の金額を貯めることも可能でしょう。まとまった資金があれば、自分のショップを開店したり、フランチャイズ店に加盟したりすることもできます。また、士業などの公的な仕事に興味があれば、未経験から挑戦できる行政書士や司法書士の資格を取得して、経験を積みながら独立を目指す方法もあります。
ただし、独立・起業を成功させるためには、期間工として働きながらしっかりと計画を立て、資金面を含めて準備を整えておくことが肝要です。ときにはチャレンジ精神も大切ですが、無計画・無謀な選択は失敗の元となりうるので注意しましょう。
期間工からの転職/失業手当・再就職手当も要チェック!
では最後に、期間工の退職・転職において、必ずチェックしておきたい公的な手当について解説します。
失業手当について

期間工は会社の雇用保険に加入するため、退職した際には失業保険の受給対象になります。ただし、実際に失業手当をもらうためには、主に以下のような条件を満たす必要があります。
-
-
【失業保険の主な受給条件】
●自己都合による退職(契約中途の退職など)……退職日より前の2年間で(前職を含めて)、雇用保険の加入期間が1年以上あること
●会社都合による退職(満了退職など)……退職日より前の1年間で(前職を含めて)、雇用保険の加入期間が6ヵ月以上あること
●その他の主な条件……退職してから1年以内に申請し、再就職の意思があること
-
期間工は会社の雇用保険に加入するため、退職した際には失業保険の受給対象になります。ただし、実際に失業手当をもらうためには、主に以下のような条件を満たす必要があります。
再就職手当について

また、雇用保険受給資格者が、基本手当(失業保険)の受給期間中に再就職が決定した場合や、自分で事業を開始した場合には再就職手当が支給されます。再就職手当についても一定の受給条件がいくつかあり、再就職先などによっては受給できないケースもありますので、事前にしっかり確認しておきましょう(以下参照)。
細かい条件や内容がよくわからなければ、ハローワークや就職エージェントなどで、詳しい説明を受けることをおすすめします。
※再就職手当の受給条件や、受給に関する注意点はこちらをご覧ください
期間工も再就職手当をもらえる?条件・金額・失業手当との違いは?
期間工や製造業のお仕事探しなら<工場求人ナビ>へ!
日総工産<工場求人ナビ>では、全国各地の工場ワークや期間工の求人を多数ご紹介!人材コーディネーターによるお仕事探しやアドバイスはもちろん、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。
製造業や期間工のお仕事に興味がある方も、期間工からの転職を考えている方も、まずは下記からお気軽にエントリー&ご応募ください!
