派遣社員も社会保険に加入できる?加入条件やメリットを解説!
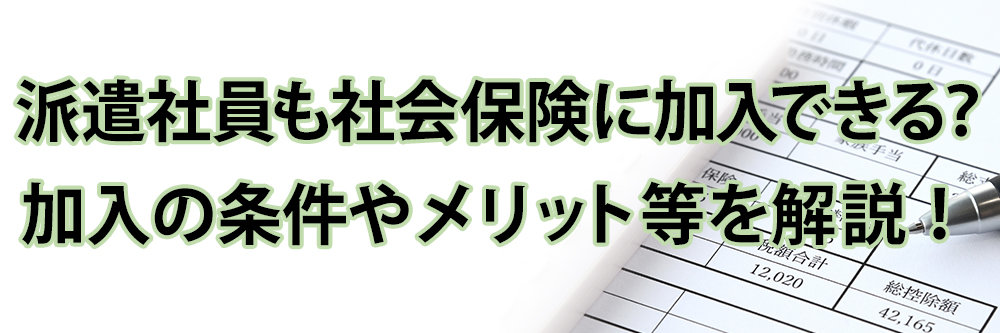
2023/7/5 更新
社会保険に関する基礎知識
そもそも社会保険とは?

社会保険とは、国民の生活を保障するために、国が設けた社会保障制度の総称です。国や公的機関が保険者として運営し、会社員や公務員を被保険者として、万一の際に給付を行う仕組みになっています。
社会保険は、民間の生命保険や医療保険などとは異なり、一定の条件を満たしている人は法律によって加入が義務づけられています。また、雇用主と労働者(被保険者)の双方で保険料を負担する点も、社会保険の大きな特長です。
社会保険の種類について

社会保険には、病気やケガ、老齢、失業、労働災害、介護などのリスクに応じて、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」「介護保険」の5種類があります。以下、それぞれの保険について解説します。
健康保険
病気やケガで医療機関を受診した際、かかった医療費の一部が給付される保険です。基本的に医療費の7割が保険で給付されるため、自己負担は3割となり、扶養家族は年齢によって1~2割で済むことが特徴です。健康保険の保険料は、雇用主と労働者が半分ずつ支払う仕組みとなっています。
厚生年金保険
厚生年金保険には、老後に年金が受け取れる「老齢年金」のほか、病気やケガで障害を負った場合に支給される「障害年金」、本人が死亡したときに遺族が受け取れる「遺族年金」があります。厚生年金保険の保険料は、報酬に比例した保険料を雇用主と労働者が半分ずつ支払う仕組みとなっています。
雇用保険
一般的に失業保険と呼ばれる保険制度です。万一、失業して収入が途絶えた場合や、何らかの理由で雇用が継続しなかった場合、国から一定期間手当が支払われます。雇用保険の保険料も雇用主と労働者の双方で負担しますが、支払う額は労働者の負担が軽い設定となっています。
労働者災害補償保険
一般的に労災保険と呼ばれる保険制度です。仕事が原因で病気やケガにつながった場合や、勤務中・通勤途中の事故でケガや障害を負ったり死亡したりした場合に、本人や遺族に対して保険金が支払われます。労働者災害補償保険の保険料は、他の社会保険とは異なり、労働者の負担は一切ありません。
介護保険
介護認定を受けた際に、必要な介護サービスを1割負担で受けられる社会保障です。40歳未満の人に加入義務はありませんが、40~64歳までは健康保険料と一緒に徴収され、保険料は雇用主と労働者が半分ずつ支払う仕組みとなっています。
契約社員は社会保険に加入できる?
加入条件は?
社会保険は正規雇用の正社員しか加入できないと思われがちですが、派遣社員であっても一定の条件を満たしていれば加入できます。言い換えると、加入条件に当てはまれば加入義務が生じるため、それぞれの社会保険の加入条件をしっかり理解しておくことが重要です。
以下、5種類の社会保険の加入条件について説明します。
※本記事で紹介している加入条件は、2023年5月現在のものです。今後、社会保険の見直しが行われると加入条件も変更される場合があるため、最新情報は厚生労働省のホームページなどでご確認ください
健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件

契約期間が2ヵ月を超える場合、下記《A・B》の条件を満たす人が健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入対象となります(学生には適用されません)。
-
-
《A》1週間の所定労働時間が正社員の3分の4以上である
1週間の所定労働時間が、雇用元の派遣会社に勤める正社員の4分の3以上(1ヵ月の所定労働日数が15日以上、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上)であれば加入できます。
-
-
-
《B》1週間の所定労働時間が20時間以上で、下記の条件をすべて満たしている
◎2ヵ月以上の雇用が見込まれる
◎月額の賃金が8万8000円以上である
◎企業の従業員数が101人以上である
-
雇用保険の加入条件

雇用保険は、下記の条件を満たす人が加入対象となります。
-
-
◎1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用が見込まれる
ここで注意したいのは「31日以上」の雇用です。たとえば、同じ1ヵ月契約の仕事でも、日数が31日に満たない月(2月・4月・6月など)は31日以上の条件を満たさないため、雇用保険に加入することはできません。
-
労働者災害補償保険の加入条件

労働者災害補償保険は他の4つの社会保険とは異なり、対象は労働者ではなく雇用主(企業)となります。そのため、労働者に特別な条件は設けられておらず、労働者を1人でも雇用する企業は、加入が義務づけられています。したがって、労働者は就業した時点で自動的に加入することになり、保険料についても雇用主が全額負担します。
社会保険の加入手続きは自分でするの?
派遣社員の社会保険については、実際に就労する派遣先企業ではなく、派遣元である派遣会社が負担します。法律上、社会保険の管理・支払いを行うのは雇用主となるため、雇用契約を結んでいる派遣会社が、入社後に加入手続きを行ってくれます。
そのため、自分で加入の手続きをする必要はありませんが、加入に必要となる以下の書類は用意しておきましょう。
-
-
◎雇用保険被保険者証
※以前就業していた企業で雇用保険に加入していた場合、退職時に渡されます
◎年金手帳
◎基礎年金番号通知書
-
ただし、それまで国民健康保険に加入していた場合は、自分で脱退の手続きを行う必要があります。国民健康保険の脱退手続きを忘れてしまうと、保険料を二重払いすることになるので注意しましょう。同じように、退職後も自分で国民健康保険へ切り替える必要がありますので、各市町村役場の窓口で所定の手続きをしてください。
労働者が社会保険に加入するメリット
保険料の自己負担が少ない

国民健康保険の保険料は全額が自己負担となりますが、社会保険の場合、健康保険と厚生年金保険の保険料は、基本的に労働者と雇用主が折半することになっています。個人での全額負担ではない分、経済的な負担が軽くなるというメリットがあります。
将来受け取れる年金が増える

日本の公的年金制度は、国民すべてに加入義務がある国民年金(基礎年金)と、社会保険である厚生年金保険の二段構造になっています。したがって、社会保険に加入すると基礎年金に上乗せして厚生年金が支給されるため、老後により手厚い保障を受けられることになります。
国保にはない補償が受けられる

社会保険には、国民健康保険(国保)にはない手厚い補償制度があります。たとえば、業務外の病気やケガで3日以上連続で休んだ場合、4日目以降から傷病手当金を受け取ることができます。また、妊娠・出産で会社を長期間休んだ場合にも、出産手当金や出産育児一時金が支給されます。
派遣社員の社会保険加入は必須なの?
社会保険に加入するメリットは大きいものの、加入すると保険料が月給から差し引かれるので、その分だけ手取り収入が減ることになります。そのため、できれば社会保険に加入したくないという人もいるでしょう。
しかし、社会保険は一定条件を満たしている人に加入義務がある、公的な強制保険制度です。原則として、正社員や派遣社員といった雇用形態に関わらず、適用事業所(雇用元が社会保険に加入している事業所)で働く労働者は、誰でも社会保険の適用対象となります。 つまり、派遣社員でも条件を満たしている場合は、本人の意向に関わらず、社会保険に加入することになるのです。
もちろん、先述した条件を満たさないようにすれば、加入する必要はありません。したがって、社会保険に加入せずに派遣社員として働きたい場合は、どのような勤務形態や働き方をすればいいのか、派遣会社の担当者に相談して決めていくことをおすすめします。
ちなみに、契約期間が2ヶ月以内の短期派遣の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の適用外となりますので、加入する必要はありません。
扶養内で働きたい場合は?
また、世帯主の扶養内で働きたいという人は、年収を106万円以下にすると、社会保険上も扶養の範囲内となります。 一方、年収が106万円を超えると、扶養に入りつつも加入条件を満たせば、社会保険への加入を課せられる可能性が出てきます。さらに、年収が130万円を超えると、扶養を外れて社会保険への加入を課せられます。したがって、「社会保険上の扶養内」で働くのであれば、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」を意識する必要があります。
また、同じ扶養内でも「税制上の扶養内」となると、さらに上限となる年収が低くなります。それが「103万円の壁」「100万円の壁」と呼ばれる上限年収です。年収が103万円を超えると所得税、100万円を超えると(自治体によっては93万円~)住民税が課せられます。よって、どの税金を軽減したいのかを確認し、生活に無理のない働き方を選ぶ目安にするといいでしょう。
いずれにしても、派遣社員として扶養内で働きたい場合は、派遣会社が派遣先や仕事内容などを調整してくれますので、自分の希望をきちんと伝えておくことが重要です。また、扶養控除や社会保険、税金に関しては、仕組みが複雑でわかりにくい部分も多いため、不明な点があれば派遣元の担当者に相談することをおすすめします。
まとめ
ご紹介したように、社会保険は一定の条件さえ満たせば、派遣社員でも加入することができます。加入することで、手取り収入が減ったり、扶養から外れたりする場合もありますが、老後の年金や各種手当などの面で得られるメリットも多くあります。
とくに派遣社員の場合、社会保険に加入できるかどうかは、自分の働き方次第で変わってきます。社会保険に加入することで得られるメリットと、ワークライフバランスを考慮した上で、自分にマッチした働き方のスタイルを選択しましょう。
