夜勤明け、夜勤前に入眠しやすく、快眠をとるコツをマスターしよう!
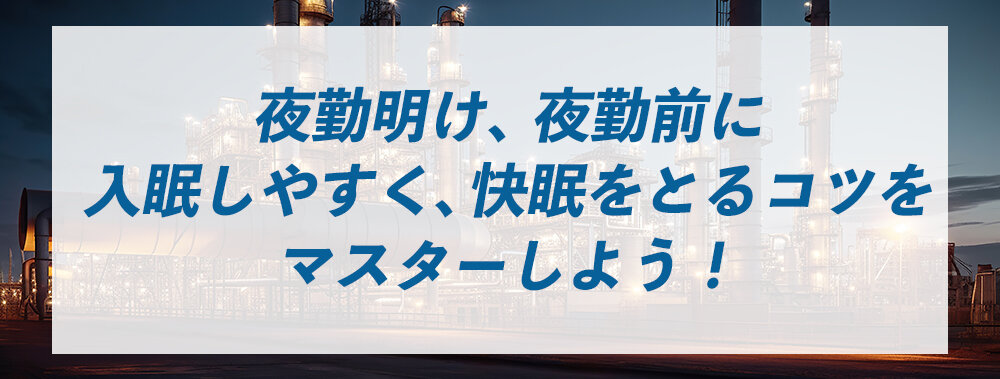
2024/1/26 更新
夜勤勤務の人は、意識的に眠りをとることが大切
私たち人間の体には生体リズムを司る体内時計がセットされていて、意識しなくても太陽が出ている日中は活動モードに入り、日が沈んだ夜間は休息モードに入るようになっています。この体内時計は人間を含む哺乳類から昆虫はもちろん、「発芽→生長→開花→枯れる」といったサイクルで花や実をつける植物など、地球上のすべての生物に体内時計が備わっています。
例えば、「昼夜逆転の生活」など体内時計に反した行動をとると生体リズムが狂い、人間の体は入眠しづらくなることがわかっていますが、「昼夜逆転の生活」以外にも「航空機や新幹線での長距離移動」や「運動や仕事で体を酷使」「強いストレスや精神への強い刺激」「空腹・飢餓」「寒暖・気圧の変化」といった環境や、精神に強い刺激やプレッシャーを感じると脳が興奮(混乱)状態に陥り、眠りにつきづらい、数時間で目覚めてしまう(浅眠)といった睡眠障害が起きやすくなります。
また、「生体リズムが狂う」→「睡眠がきちんととれない」のサイクルに陥ると、「常に重だるい倦怠感に体が包まれる」「食欲不振」「頭がボーっとする」「気力低下」などの症状が発生し、さらに、長期化することで命にかかわる大病を誘発するリスクも高まります。こうした点からも工場、医療、介護、タクシー、飲食などの昼夜逆転の夜勤で働く人は、健康を維持するためにも意識的に快眠をとることが非常に大切です。

夜勤勤務の人の健康を維持する成長ホルモン
昼夜逆転の生活を過ごす夜勤勤務の人はもちろん、日中に働いている人にとっても、体と脳の疲れに最も効果があるのが睡眠です。
体と脳の疲労を回復させる効果がある質のよい睡眠は、体の各器官の成長促進や、傷ついた組織を修復させるなどの効用があり、この成長ホルモンが睡眠中に脳の下垂体から分泌されることで、私たちは健康な日常を過ごせています。
具体的に成長ホルモンが果たしている役割の一部をあげだけでも、成長ホルモンが健康な生活を送るためにいかに大切であるかがわかります。
-
-
【睡眠によって成長ホルモンが分泌されると……】
◎ 体中の細胞を修復・回復してくれる
◎ 免疫力を強化してくれる
◎ 骨皮質や骨形成を増加してくれる
◎ 骨密度を高めてくれる
◎ エネルギー代謝や身体機能を維持してくれる
◎ 筋肉量を増やしてくれる
◎ 脂肪や糖を分解してくれる
◎ 皮膚の再生、頭皮の生え変わりを促進してくれる
-

夜勤勤務の人の不調は、成長ホルモンが関係している?
ところが、夜勤などの昼夜逆転の生活が続き「睡眠不足」が慢性化すると、成長ホルモンの分泌量が低下し、下記のようなさまざまなダメージが発生しかねません。
-
-
【睡眠障害によって成長ホルモンの分泌量が低下すると】
△ 脱毛、薄毛、肌荒れが起きやすくなる
△ 免疫が落ちることで体調不良に陥りやすくなる
△ 骨密度が低下し、骨粗鬆症、骨折を引き起こす
△ スタミナ低下により疲れやすく、疲れが取れにくくなる
△ 集中力、気力、が低下する
△ 認知機能、性欲、運動機能の低下
△ 内臓脂肪が蓄積しやすくなる
△日中や運転中に激しい眠気に襲われる他、意識が飛ぶこともある
-
そのほかにも「起床後、数時間は頭がボーッとしている」「心や思考がネガティブモード」」「栄養ドリンクを頻繁に飲んでいる」「忘れ物が多い」「財布やスマホを探すことが多い」「行動がゆったり気味」ということに心あたりがある人は、睡眠不足が大きく影響しているかもしれません。
夜勤明けに寝つけない。実は何気ない習慣が入眠を妨げる要因に
夜勤明けで体は疲れているのに、ベッドに入って目を閉じても頭が冴えわたり眠気が訪れない……。
夜勤前にしっかり睡眠を取ろうと思って早い時間にベッドに入ったけれど、無理に眠ろうと焦る気持ちが逆効果になり、まったく眠りにつけない……。
夜間や深夜のタイムシフトで働く多く人が、一度はこうした経験をしたことがあると思いますが、ベッドに入るまでは全身が眠気に包まれていたのに、ベッドに入ってもなかなか寝つけないのは、体や脳の興奮モードがおさまっていないことが要因として考えられます。スムーズな入眠には体と脳が休息(リラックス)モードに切り替える必要がありますが、実は、誤った方法で休息(リラックス)モードとは逆の行動をとり、体と脳を覚醒(アクティブ)モードにしてしまっている可能性があるのです。
思いもよらない普段の何気ない行動が睡眠を妨げる要因になっている可能性があるため、ベッドに入る前に自分がどのような行動をとっているか、以下の項目と照らし合わせながらチェックしてみましょう。
-
-
【体と脳を覚醒(アクティブ)モードにする要因】
✔︎ 眠りに入る1時間以内に食事をとり、入眠前はお腹いっぱいの状態
✔︎ 眠りに入る1時間以内に入浴している
✔︎ 食事は揚げ物、肉などの消化器官に負担がかかるものが好き
✔︎ ベッドに入っても眠気が訪れるまで、スマホを操作している
✔︎ ベッドに入ってから読書やスマホなどで目を酷使している
✔︎ 眠りに入る前にアルコールやコーヒーを摂取している
✔︎ 部屋のカーテンは閉めず、室内が明るい
-

体と脳を休息(リラックス)モードにする「2時間前」の行動
入眠しやすくし、ぐっすり眠るためのコツはいくつもありますが、脳と体を覚醒(アクティブ)モードから休息(リラックス)モードに切り換えるため、「眠りにつく2時間前」「眠りにつく20分前」の2段階に分けて次のような行動をとると、入眠しやすくなります。
-
-
【眠りにつく2時間前に済ませたいこと】
○ 消化器官を休ませるため、揚げ物、肉等の食事は2時間前に済ませる
○ サウナや42℃以上の湯船に浸かる入浴は、2時間前に済ませる
○ 入眠直前に入浴する際は、ぬるめのお湯に浸かるようにする
○ 深酔いした状態で眠りにつく習慣がある
-
ベッドに入る前に、眠りにつきやすくするためアルコールを摂取する人も多いと思いますが、アルコールには覚醒作用があるため、眠りに入ったとしても深い眠り(快眠)を得ることが難しくなります。同様に覚醒作用が高く、入眠や快眠を妨げるカフェインやタバコも、睡眠直前(1時間以内)にはできるだけ避けるようにすると、入眠しやすく、ぐっすり眠れるようになります。
体と脳を休息(リラックス)モードにする「20分前」の行動
食事や入浴を済ませ、あとは眠るだけ……という段階になったら、次の項目に従って睡眠環境を整えましょう。
-
-
【眠りにつく20分前に済ませたいこと】
○ 遮光カーテンなどで室内を暗くする
○ 室内を快適な室温・湿度に整える
○ 外の音を遮断するため、窓を閉める(耳栓を使用する)
○ 入眠作用があるアロマ(精油)を活用する
-
最後の「入眠作用があるアロマ(精油)を活用する」は、安眠効果があるラベンダー、カモミール、ヒノキ、サンダルウッド、ゼラニウムなどを活用しましょう。また、アロマディフューザーを持っていない人は手軽な方法としてオイルを1〜2滴垂らしたティッシュを枕元に置くだけでも、ふーっと深呼吸したくなる心地よさを体感できるはずです。

掛け布団をかけ、目をつぶってから意識したいこと
無理矢理眠りに入ろうとする焦りは脳へのストレスになるため、ストレスフリーの状態でスーッと眠りにつけるよう、掛け布団をかぶって目をつぶる段階で次のポイントを実践してみましょう。
-
-
【眠りにつく直前に意識したいこと】
○ 掛け布団をかける前に、スマホを充電コードにさし、手元から離す
○ テレビのオフタイマーを30分に設定し、音量を小さくする
○ うつぶせ、横向き、大の字など、入眠しやすい体勢をとる
○ ギッュと閉じているまぶたや目元の力をほどく(和らげる)
○ 5秒吸って5秒吐く……このリズムでゆっくり深呼吸する
-
それでも、頭と体が眠りにいざわれにくい時は、「もうここまできたら、体を休ませられればいいや……」という割りきった考えに切り替え、静かに横になっている状態を維持しましょう。「早く眠らないと!」という焦りの気持ちやプレッシャーを捨て去ることで、気づかないうちに眠りにつける可能性がグンと高まります。
夜勤勤務の人は、日常の過ごし方にもちょっとした心配りを!
今回は入眠・快眠をとるためのコツをご紹介してきましたが、睡眠時間を維持し、睡眠の質を向上・改善させるのは、そうはいってもなかなか難しいもの。
「早く寝ないと!」「ベッドに入ってもう3時間が経ってしまった!」と焦れば焦るほど眠りにつきにくくなる悪循環に陥ることがありますし、「明日は大事な仕事があるので緊張して寝つけない!」「ホットミルクを飲んでも、羊を数えても眠気が訪れない!」というプレッシャーや強迫観念によっても目が冴えわたり、眠りにつきにくくなります。
夜勤勤務の人は、シフト開けやシフト前にしっかり睡眠をとることが大切なので、睡眠を入りやすい体内環境を整えるためにも、日頃から下記のようなポイントに注意するようにしましょう。
-
-
✔︎ 不規則な食事、偏った献立、暴飲暴食をしない
✔︎ お腹いっぱいではなく、腹八分目を心がける
✔︎ 香辛料、味が濃いもの、油が多いもの、消化が悪いものを控える
✔︎ 夜勤シフト前に寝溜めしていない
✔︎ 軽めの運動で適度な疲労感を得ることを習慣化する
✔︎ 夜勤シフト前に適度な仮眠をとる
-

夜勤シフト前に適度な仮眠の目安は、起床後7〜8時間ほどのタイミングで90分〜180分の仮眠をとることがよいとされています。睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠の周期が90分ほどで入れ替わるため、仮眠の際には90分〜180分の目覚めたい時間にテレビのタイマーなどをセットしておくと、体と脳に負担をかけず覚醒しやすくなります。
——最近、脳や体の機能劣化を誘発する「睡眠負債(Sleep Debt)」というキーワードをよく見聞きするようになりましたが、この「睡眠負債」は慢性的な睡眠不足、積み重なる眠りに対する借金を意味します。
「睡眠負債」が蓄積するとがん、糖尿病、高血圧などの生活習慣病や、うつ病などの精神疾患や認知症といったさまざまな病気の発症リスクを高めることが各方面の研究結果から明らかになっています。慢性的に眠気を感じている、疲れがなかなか抜けない、気持ちにハリがない……といった不調を放置していると、仕事中や運転中の事故や、命にかかわる思い病気を発症しかねないため、ぜひ今日から入眠・快眠のコツを実践して、健やかな心と体を維持しましょう!
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験者歓迎・学歴不問の工場ワークを多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。正社員就職を目指す高卒フリーター方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
