期間工の人生は「終わり」ではない!目的と目標を定めて人生を豊かに変える!
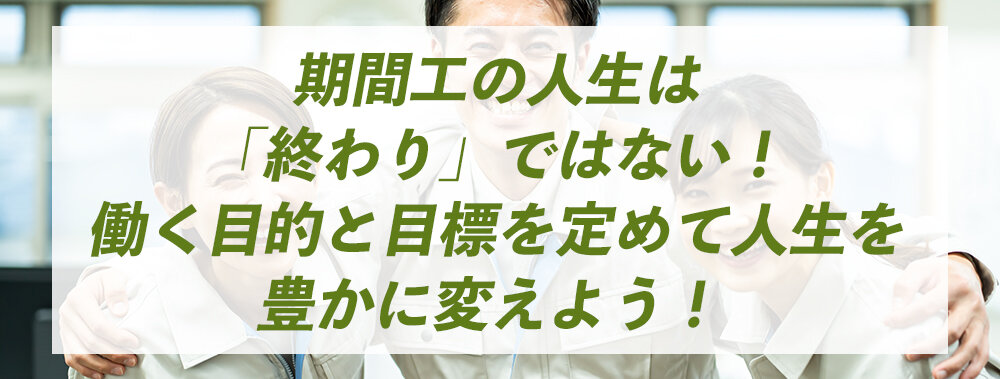
2024/1/11 更新
期間工の仕事は未経験でも高収入を目指せるのが魅力ですが、ネットの口コミなどでは「期間工はやめておけ、人生終わり」といった声もあるようです。ただ、どんな仕事にもメリット・デメリットとなる部分はありますし、仕事に対する考え方や向き・不向きも人それぞれです。
本記事では、期間工がネガティブに言われる理由とともに、期間工という働き方の特性やメリットを最大限に生かして、人生を豊かに変えていくためのポイントについて解説します。期間工の仕事に興味がある人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください!
-
■目次
- ●押さえておきたい期間工の基礎知識
-
・そもそも期間工とは
・期間工と派遣社員の違いは?
- ●期間工で働くメリット・魅力とは?
-
・学歴・経験不問の求人が多い
・未経験でも短期間で効率的に稼げる
・入社特典や満了慰労金が支給される
・備品付きの寮完備で快適に生活を始められる
・日々の生活費をセーブして貯金しやすい
・正社員登用のチャンスがある
- ●期間工がネガティブに言われる理由
-
・長期的に安定した雇用が保証されない
・ハードな力仕事や立ち仕事が多い
・単純作業の繰り返しが苦痛
・特別なスキルが身につけにくい
・期間工の仕事を繰り返しやすい
- ●期間工の仕事で人生を豊かに変えていくために
-
・期間工として働く理由・目的を明確にする
・毎月の収支を把握して貯金を心がける
・正社員登用を目指す
・将来に向けてお金の使い道を考える
- ●期間工の仕事を選ぶ際のポイント
-
・自分の体力や適性に合ったメーカーを選ぶ
希望する収入や目的に合わせて選ぶ
派遣会社を通して選ぶ
- ●まとめ
押さえておきたい期間工の基礎知識
そもそも期間工とは
期間工(期間従業員)とは、 主に自動車メーカーや製造業の工場において「働く期間が決められている従業員」のこと。契約期間は工場によって異なりますが、一般的に3ヵ月~6ヵ月ごとに契約更新(満了)となる仕事が多く、最長2年11ヵ月(※)で契約終了(退職)となります。同じ職場で続けて働く場合は、契約終了後に再雇用契約を結ぶ必要があります。
※「同じ企業で3年以上勤務する従業員は、正社員として雇用しなければならない」と労働基準法で定められているため、基本的に期間工の契約期間は最長2年11ヵ月となっています。
期間工と派遣社員の違いは?

働く期間が定められている点では期間工も派遣社員も同じですが、期間工が「企業に直接雇用されて働く」のに対し、派遣社員は「派遣会社に雇用され、派遣先の企業で働く」という違いがあります。つまり、企業と直接契約する期間工は、派遣会社が給料から差し引く手数料が発生しないため、収入面では派遣社員より有利となるのです。
また、12ヵ月働いた後に次の仕事がない場合、期間工も派遣社員も失業保険が給付されますが、期間工が契約満了から1ヵ月後(待機期間7日)に受給できるのに対し、派遣社員は基本的に4ヵ月後(待機期間3ヵ月)からの受給となります。
期間工で働くメリット・魅力とは?
学歴・経験不問の求人が多い

期間工の求人は、基本的に学歴・経験不問で、健康面に問題がない満18歳以上の人(夜勤があるため学生は不可)であれば、誰でも応募することが可能です。
仕事内容は、決められた生産ラインでの単純作業がメインとなるため、仕事に関する基礎知識・技術は一切必要ありません。入社後の研修のほか、慣れるまでは職場の先輩が指導してくれますので、工場勤務の経験がない人でも安心して働き始めることができます。
未経験でも短期間で効率的に稼げる

期間工として働く最大のメリットは、未経験でも短期間で稼げることです。期間工の平均的な時給は1100円~1500円程度、日給は1万円程度が相場で、1日8時間・1ヵ月に22日間勤務すると月給は約20~25万円ほどになります。
ただ、期間工は夜勤や残業も多く、基本給の25%以上増しとなる深夜手当や残業手当が支給されるため、実際の月給は30万円を超えるケースがほとんどです。さらに、毎月の給料に加えて特別手当なども別途支給されるので、未経験者でも年収400万円以上を目指すことが可能なのです。
入社特典や満了慰労金が支給される

期間工を募集する多くのメーカーでは、入社特典・特別手当として入社祝い金を支給しています。入社祝い金の有無や支給額、支給条件などはメーカーや時期によって異なりますが、最大で50~100万円の祝い金が支給されるケースも少なくありません。
また、期間工として契約期間(一般的に3~6ヵ月ごと)を満了するまで働き続けると、満了慰労金が支給されるのも魅力のひとつです。満了慰労金の額は企業によって異なりますが、基本的に長く働けば働くほど金額が増えていきます。雇用期間が終了(最長2年11ヵ月)するまで勤務すれば、合計で100万円以上の満了金がもらえるメーカーもあります。
備品付きの寮完備で快適に生活を始められる

期間工を募集しているほとんどのメーカーでは、工場の近隣に寮を完備しているため、自宅から通えない遠方の人も安心して働き始められます。寮の個室には基本的な生活家電や寝具なども用意されていますので、すぐに入寮して快適に新生活をスタートできます。
また、寮から工場への通勤には無料バスが利用できるほか、通勤用の自家用車やバイクが持ち込みOK(諸条件あり)の寮もあります。
日々の生活費をセーブして貯金しやすい

期間工は寮を格安(無料の場合も)で利用でき、メーカーによっては水道光熱費や寮の食事代が無料のところもあります。また、食事補助などの手当を支給するメーカーも多いため、日々の生活費をセーブして、働いた分だけしっかり貯金することも可能です。
正社員登用のチャンスがある

期間工を募集する多くのメーカーでは正社員登用制度を設けており、期間工としての働きが認められると、正社員になれる可能性があります。とくに、正社員登録制度のある大手自動車メーカーでは、毎年、相当数の期間工を正社員に登用しており、なかには登用率が80%を超えるメーカーもあります。
期間工がネガティブに言われる理由
期間工の仕事に多くのメリットがある一方で、ネットの口コミなどでは「やめておけ、人生終わり」といったコメントも散見されます。なぜ、期間工がネガティブに言われるのか、その理由としては、主に以下のような点が挙げられるでしょう。
長期的に安定した雇用が保証されない

期間限定で働く非正規雇用の期間工は、正社員のように長期的な雇用が保証されていません。そのため、雇用が安定した職場で長く働きたい人にとって、期間工は「不安定で将来性がない仕事」とネガティブに捉えてしまうのかもしれません。
ハードな力仕事や立ち仕事が多い

期間工の仕事の中には、長時間の立ち仕事や重量物を扱う力仕事もあります。とくに自動車メーカーでは、重いタイヤを持ち上げたり、大きなパーツを取り付けたりする作業も多いため、体力や筋力に自信がない人にはキツイと感じるかもしれません。とはいえ、力仕事は慣れの部分もありますし、担当する部署や工場の業種(部品メーカーなど)によっては、体力的な負荷の少ない軽作業もあります。
単純作業の繰り返しが苦痛

期間工の仕事は簡単な単純作業が多く、未経験者や初心者でも始めやすいのがメリットです。ただし、毎日単調な作業の繰り返しとなるため、同じ作業にコツコツと取り組むのが苦手な人や、単純作業に飽きやすい人にとっては「苦痛な仕事」となってしまい、「やめておいた方がいい」と言いたくなるのかもしれません。
特別なスキルが身につけにくい

先述したように、期間工の仕事は簡単な単純作業が多いため、難易度の高い作業や期間工以外のスキルが身につけにくい傾向にあります。そのため、自分自身の成長やスキルアップが実感しにくく、人によっては「やりがいのない仕事」と感じるかもしれません。
期間工の仕事を繰り返しやすい

期間工は短期間でしっかり稼げるメリットがあることから、契約終了後に他のメーカーの期間工に応募して働く人も多いようです。前職の経験を生かして、同じ業種で再び働く人もいれば、他業種の期間工に挑戦して、新たな経験を積む人もいます。
ただ、期間工に対してマイナスなイメージをもった人からすると、「期間工の仕事を繰り返す=負のループ」と捉えてしまうようです。
期間工の仕事で人生を豊かに変えていくために
期間工がネガティブに言われる理由を見てもわかるように、期間工の仕事には人によってデメリットとなる部分や、働く上で注意しておきたい点があるのも事実です。
もちろん、どのような仕事においても働くメリット・デメリットや、人によって向き・不向きもあります。よって、期間工で人生をどう変えていくかも「本人次第」ということです。
期間工になって後悔したり、悲観したりしないように、期間工として働く際には、まず以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
期間工として働く理由・目的を明確にする

期間工としてただ漠然と働いていると、仕事に向かう姿勢や意思がブレやすく、ちょっとしたことで挫折してしまう可能性があります。一方で、働く理由や目的・目標を具体的に掲げれば、仕事に対するモチベーションを保ちやすく、期間工として働く日々もより充実するでしょう。
たとえば、「留学・結婚のために○○円貯金する」「自店の開店資金や起業資金を貯める」「稼ぎながら一人暮らしを体験したい」「正社員登用を目指す」など、人それぞれに働く理由や目的があると思います。もちろん、公言するかどうかは別として、借金の返済が目的で働いている期間工もいますし、短期集中で稼いで完済できれば、人生の大きなターニングポイントにもなるはずです。
毎月の収支を把握して貯金を心がける

期間工は、期間を決めて自由な働き方ができる反面、長期的な雇用が保証されない不安定な働き方でもあります。そのため、毎月の収支をきちんと把握してムダな出費を抑え、できるかぎり貯金を心がけることが、将来への備えや心の安定にもつながります。ある程度の蓄えがあれば、契約終了後すぐに仕事が見つからない場合でも、気持ちに余裕を持って自己投資や就職活動に取り組めるでしょう。
正社員登用を目指す

採用されたメーカーの正社員登用制度を利用して、期間工から正社員を目指すのもおすすめです。正社員として実績を積めば昇給・昇格が期待でき、キャリアアップに伴って役職手当なども支給されます。また、基本的に定年まで雇用が保証され、まとまった退職金も支給されますので、将来への不安も少なくなるでしょう。
もちろん、正社員に登用されるためには、各メーカーが定める諸条件(勤務態度、勤務期間、上司の推薦、年齢、登用試験など)をクリアする必要がありますので、無断欠勤や遅刻などをせず、日ごろから前向きに仕事に取り組むことが重要です。
将来に向けてお金の使い道を考える

原則として期間工の採用に年齢制限はありませんが、現実的には体力面を考慮して40代までというケースが多いようです。よほどの経験や技術を持っていたり、かなりの繁忙期だったりしないかぎりは、50代以降の採用はやや厳しいかもしれません。
したがって、50代以降に安定した人生を送るためには、期間工で稼いだお金をいかに有効活用し、将来に向けて投資していくかがカギとなります。たとえば、起業や開店資金にまわして独立する、自己投資や資格取得の資金にまわして、他の仕事に役立つスキルを身につける……等々。また、若いうちから徹底して稼ぐことに集中し、可能なかぎり貯金にまわしていけば、50代でのセミリタイアも夢ではないかもしれません。
期間工の仕事を選ぶ際のポイント
自分の体力や適性に合ったメーカーを選ぶ

期間工を募集しているメーカーの業種は、自動車・部品系・精密機器・重機・家電など多岐にわたり、業種によって扱う製品や仕事内容も異なります。したがって、期間工の仕事を検討する際には、自分の体力や適性を見極め、無理のない範囲で働ける業務内容のメーカーを選ぶことが重要です。
とくに、体力や筋力に自信がない人は、力仕事が少ない部品系メーカーがおすすめです。また、手先が器用な人は精密機器メーカー、体力に自信がある人やクルマ好きな人なら自動車メーカーなど、自分の得意分野や興味に合わせて選ぶのもいいでしょう。
希望する収入や目的に合わせて選ぶ

貯金したい額が明確で収入面を重視するなら、入社祝い金や満了慰労金など、特別手当が充実したメーカーを選ぶのがおすすめです。また、寮の費用・水道光熱費が無料のメーカーや、食事手当が充実したメーカーを選べば、生活費を抑えて効率的に貯金できます。
その他、期間工から正社員を目指したい人は、応募時に正社員登用制度の有無や登用条件をしっかり確認しておきましょう。
就職エージェントを通して選ぶ

期間工の仕事が初めての人や、仕事選びに不安がある人は、期間工の求人を扱っている就職エージェント(派遣会社など)を通して応募するのがおすすめです。就職エージェントはメーカーや業界、期間工の仕事に関する情報に精通しているため、期間工の経験がない場合でも、相談しながら仕事選びができ、自分にマッチしたメーカーの仕事が見つけやすくなります。
また、仕事の紹介だけでなく、履歴書の添削や面接対策などのサポートも受けられるので、一人で就活を進めるのが不安な人も心強いでしょう。さらに、期間工の仕事が契約終了した際にも、希望に応じて次の仕事を紹介してもらえるので、ブランクを空けずに働きたい人にもおすすめです。
まとめ
今回は「期間工の人生」というやや難しい話題になりましたが、皆さんはどう思われたでしょうか。
ご紹介したように、期間工は未経験でも高収入を目指せるのが魅力ですが、その利点ばかりに頼って、働く目的や目標を考えずに浪費してしまえば、将来得られるはずのチャンスも逃してしまいます。一方で、期間工として働くメリット・デメリットを十分理解し、将来のビジョンと目標をしっかり定めて仕事に取り組めば、人生を豊かに変える大きなステップにもなり得るのです。
本記事を読んで期間工の仕事に興味を持った方はもちろん、期間工として働きながら自分の夢をかなえたい方も、ぜひこの機会に、人生のネクストステージへ向けて挑戦してみてはいかがでしょうか。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、大手メーカーを中心とした全国各地の期間工求人を多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。期間工の仕事を探している方も、製造業やモノづくりの現場で働きたい方も、下記リンクからお気軽にエントリー&ご応募ください!
