フリーターが保険証を持っていないリスクや保険証の取得方法を解説
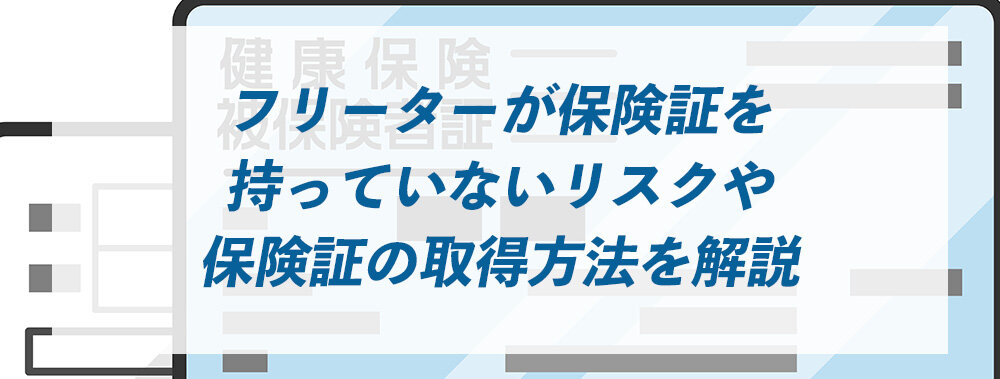
2025/4/15 更新
-
■目次
- 1.フリーターも公的医療保険への加入は必須!
-
2.フリーターが加入する国民健康保険と社会保険について
-
・国民健康保険とは
・社会保険の被用者保険(健康保険)とは
-
3.フリーターが保険証を持っていないことのリスク
-
・通院・入院で医療費が全額自己負担になる
・本人確認を必要とする手続きができないことも
・延滞金などのペナルティーが科される
-
4.フリーターが保険証を取得するには?
-
・勤務先の社会保険に加入する
・国民健康保険の加入手続きをする
・親の扶養に入る
-
5.フリーターが国民健康保険に加入する際の手続き
-
・国民健康保険の加入手続きに必要な書類
・国民健康保険の加入手続きの方法
-
6.国民健康保険料が支払えない場合はどうする?
-
・国民健康保険料の徴収猶予制度
・国民健康保険料の減免制度
・国民健康保険料の分割納付
-
7.まとめ フリーターも必ず保険証を取得しておこう!
フリーターも公的医療保険への加入は必須!

アルバイトやパートで働くフリーターの中には、公的な医療保険に加入せず、保険証(健康保険被保険者証)を持っていない人も一定数いるようです。しかし、日本では「国民皆保険制度」を導入しているため、すべての国民が公的医療保険に加入することが義務づけられています。
国が定める公的医療保険には、おもに「国民健康保険」と会社で加入する「社会保険の被用者保険(健康保険)」があり、フリーターでも年収130万円を超えて親などの扶養から外れた場合、いずれかの保険に加入しなければいけません。
フリーターが加入する国民健康保険と社会保険について
ここからは、フリーターが加入する国民健康保険と社会保険の被用者保険について解説します。
国民健康保険とは

国民健康保険は、会社の社会保険(被用者保険)に加入していない自営業者や年金受給者、アルバイト・パート従業員などが対象となります。よって、勤務先の社会保険に加入していないフリーターが、親などの扶養から外れた場合も、自分で国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。
国民健康保険料は前年の収入や年齢などに準じて請求されますが、算出方法は自治体によって異なるため、詳しくは住んでいる市区町村のサイトなどで確認してください。保険料の納付方法は、郵送された納付書または口座振替が基本となりますが、自治体によってはクレジットカードや電子マネーでの支払いも可能です。
社会保険の被用者保険(健康保険)とは

勤務先の会社を通して加入する社会保険には、被用者保険(健康保険)・雇用保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険が含まれています。よって、会社の社会保険に加入すると、被用者保険にも入ることになるため、国民健康保険に加入する必要はありません。基本的にアルバイトやパートで働くフリーターも、以下の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。
-
-
《社会保険の加入要件》
●学生ではない
●1ヵ月の給料が8万8000円以上
●見込まれる雇用期間が2ヵ月以上
●1週間の所定労働時間が20時間以上
●勤務先の従業員数が51人以上
-
被用者保険の場合、保険料の半分は勤務先の会社が負担し、残りの半分は従業員の給料から天引きされるのが一般的です。被用者保険の保険料率は、会社が加入する保険組合・協会によって異なりますが、収入の9%~10%程度が目安となります。
フリーターが保険証を持っていないことのリスク
公的医療保険に加入していることを証明する保険証は、持っていないことでさまざまな不都合が生じます。以下、フリーターが保険証を持っていない、または保険料を支払っていないことで生じるリスクについて解説します。
-
-
●通院・入院で医療費が全額自己負担になる
●本人確認を必要とする手続きができないことも
●延滞金などのペナルティーが科される
-
通院・入院で医療費が全額自己負担になる

体調不良やケガで医療機関を受診する際には、窓口で保険証の提示が求められます。保険証があれば、保険診療(通常の病気やケガに対する診療、高度先進医療や美容整形などは除く)にかかる医療費の一定割合が保険でカバーされるため、その証明書として保険証が必要になるのです。
保険証がなくても医療機関を受診することは可能ですが、かかった医療費の全額を窓口で支払わなければいけません。これは、ちょっとした通院だけでなく、大きな病気やケガによる手術や入院も対象となるため、場合によっては何十万~何百万円もの医療費が全額自己負担になる可能性もあるのです。もし保険証を持っていないと、長期的な通院や入院が必要になったとき、高額な医療費が支払えず、経済的に困窮することになるかもしれません。
【保険証があると医療費の自己負担は3割で済む】
医療機関に保険証を提示すると、実際にかかった医療費から保険でまかなわれる分を差し引いた金額が患者(本人)に請求されます。本人負担の割合は年齢によって変わりますが、小学校入学後から70歳未満の人であれば3割となります。たとえば、実際にかかった医療費が3000円の場合、本人はその3割にあたる900円の支払いで済むことになります。
本人確認を必要とする手続きができないことも

保険証は、銀行口座の開設やクレジットカードの作成、不用品の買い取りや賃貸住宅の契約など、本人確認が必要な手続きを行う際の身分証明書として使用できます。一般的な身分証明書としては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードといった顔写真付きのものが使われますが、これらを持っていない人もいるでしょう。そのような場合、身分を証明する保険証を持っていないと、本人確認を必要とする手続きがスムーズにできなくなる恐れがあります。
なお、2024年12月2日からマイナ保険証(マイナンバーカードと一体化した保険証)への一本化により、従来の保険証(紙の保険証)は新規発行されなくなります。マイナ保険証を利用しない場合は、保険証に代わって資格確認書が交付され、従来の保険証と同様に使用できます。
延滞金などのペナルティーが科される

先述したように、公的医療保険への加入は義務となっています。そのため、普段から保険証を使うかどうかに関わらず、毎月の保険料は必ず支払わなければいけません。
社会保険(被用者保険)の保険料は、毎月の給料から天引きされるため、払い忘れる心配はありませんが、国民健康保険料は納付期限までに自分で支払う必要があります。国民健康保険料を支払わないと、納付期限の翌日から延滞金が発生するので注意が必要です。さらに、納付期限を過ぎても滞納を続けていると、自治体から督促状や勧告書が送付され、場合によっては預貯金や不動産などを差し押さえられる可能性があります。
フリーターが保険証を取得するには?
ここからは、フリーターが保険証を取得する方法を紹介します。まだ保険証を持っていないフリーターの人は、以下いずれかの方法で早めに取得するようにしましょう。
-
-
●勤務先の社会保険に加入する
●国民健康保険の加入手続きをする
●親の扶養に入る
-
勤務先の社会保険に加入する

先述した社会保険の加入要件を満たしているフリーターの場合、勤務先の社会保険に加入すれば、被用者保険の保険証が取得できます。被用者保険料は会社と従業員の折半になるため、アルバイトやパートでも社会保険に加入できる場合は、入った方がお得といえるでしょう。
ただし、会社によっては雇用コストの観点から、正社員のみを社会保険の加入対象としているケースもありますので、フリーターが加入を希望する場合は勤務先に確認してください。
国民健康保険の加入手続きをする
社会保険の加入要件を満たしていないフリーターの場合、自分で国民健康保険の加入手続きをして保険証を取得します。親の扶養から外れた人はもちろん、会社を退職してフリーターになった人も、社会保険から抜けることになるため、自分で国民健康保険に切り替える必要があります。加入に必要な書類や手続きの方法は、次項で詳しく解説します。
親の扶養に入る

収入の低いフリーターの場合、親の公的医療保険の扶養に入れば、自分で保険料を支払うことなく保険証を取得できます。ただし、子ども(被扶養者)が親(扶養者)の扶養に入る場合は、以下の条件を満たす必要があります。
-
-
●原則:被扶養者の年間収入が130万円未満であること
●同居の場合:被扶養者の年間収入が扶養者の年間収入の2分の1未満であること
●別居の場合:被扶養者の年間収入が扶養者からの仕送り額未満であること
-
フリーターが国民健康保険に加入する際の手続き
社会保険への加入手続きは勤務先の会社が行ってくれますが、国民健康保険への加入手続きは自分で行う必要があります。ここからは、フリーターが国民健康保険に加入する際に必要な書類と手続きの方法を解説します。
国民健康保険の加入手続きに必要な書類
国民健康保険の加入手続きに必要な書類は、加入する理由によって異なります。たとえば、フリーターが親などの扶養を外れて国民健康保険に加入する場合は、以下の書類や証明書が必要です。
-
-
●本人確認の証明書(顔写真付きの運転免許証やパスポートなど)
●マイナンバーカード、または個人番号がわかる通知カード
●扶養から外れた日が記載されている証明書(健康保険資格喪失証明書など)
●銀行のキャッシュカード・通帳・銀行印(保険料を口座振替にする場合)
-
運転免許証やパスポートなどを持っていない場合は、本人の氏名が確認できる書類を2点そろえることで本人確認が可能です。本人確認が認められる書類については、各自治体のルールを確認してください。また、健康保険資格喪失証明書は、扶養者(親など)の勤務先を通して発行してもらいましょう。
国民健康保険の加入手続きの方法

国民健康保険の加入手続きは、自分の住民票がある自治体の役所で行います。上記の必要書類を持って役所に出向き、担当の窓口で申請してください。マイナ保険証を利用する場合は、申請してから数日~1週間程度で、マイナンバーカードに保険証が反映されます。マイナ保険証を利用しない場合は、従来の保険証に代わる資格確認書が交付されます(窓口交付で最短当日、郵送交付で数日程度かかります)。
なお、親などの扶養を外れた場合や会社を退職した場合、資格喪失日(扶養を外れた日、退職した日)から14日以内に、国民健康保険への切り替え手続きを行う必要があるため、期限が過ぎないように注意しましょう。
国民健康保険料が支払えない場合はどうする?

収入が不安定なフリーターは、国民健康保険料の支払いが難しいこともあるでしょう。経済的な事情で保険料の支払いが困難な場合は、住んでいる市区町村の役所に行って早めに相談することをおすすめします。支払えない理由によっては、保険料の徴収猶予や減免制度を利用できたり、分割納付が認められたりする場合があります。
国民健康保険料の徴収猶予制度
徴収猶予制度とは、震災や火災、水害などの自然災害で損害が出てしまった場合や、失業・廃業などで収入が激減してしまった場合に、国民健康保険料の支払いを一定期間猶予してもらえる制度です。
国民健康保険料の減免制度
減免制度とは、震災や火災、水害などの自然災害で損害が出てしまった場合や、倒産・失業で職を失ってしまった場合、会社都合で退職し収入が激減してしまった場合に、国民健康保険料の減額や免除が認めてもらえる制度です。
国民健康保険料の分割納付
支払いの猶予や減免が認められなかったとしても、役所の担当者に支払いが難しい旨の相談をすることで、保険料の分割納付を認めてもらえる場合があります。
まとめ フリーターも必ず保険証を取得しておこう!

今回は、国民健康保険と社会保険(被用者保険)の違いや保険証の取得方法、フリーターが保険証を持たないリスクについて解説しました。
フリーターの中には「病院にほとんど行かないから」「保険料を支払いたくないから」などの理由で、保険証を持っていない人がいるかもしれません。しかし、公的医療保険への加入は国民の義務であり、思わぬケガや病気で医療機関を受診した際にも、保険証があれば医療費の負担を大きく減らすことができます。もし保険証を持っていないのであれば、できるだけ早く保険に加入するか、収入を調整して親の扶養に入るかして、必ず保険証を取得しておくようにしましょう。
── 日総工産の<工場求人ナビ>では、製造業に特化した紹介予定派遣の求人を多数掲載しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就活のサポート体制も充実。まずは下記ボタンから、お気軽にエントリー&ご応募ください!
