夜勤は生活リズムが乱れやすい? デメリットとメリットを解説
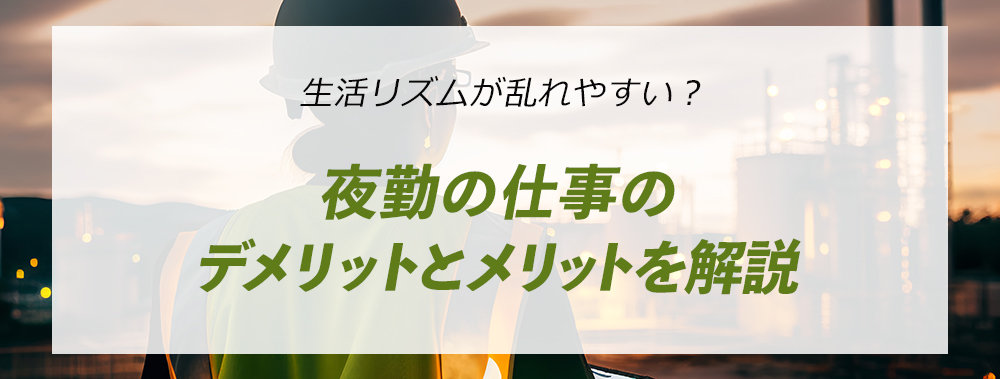
2024/6/3 更新
-
■目次
- 1.そもそも「夜勤」とは?
- 2.夜勤は生活リズムが乱れやすく、体力的にきついって本当?
- 3.夜勤の生活リズムが乱れる以外のデメリットは?
-
(1)夜勤は業務範囲も広くなる?
(2)夜勤は眠りに入りにくくなる?
(3)夜勤は友人や家族と生活リズムが合わない?
(4)夜勤で生活リズムが乱れると疲れやすい?
- 4.夜勤は生活リズムが乱れやすいもののこんなメリットが!
-
(1)日勤よりも賃金が高い
(2)通勤ラッシュとは無縁
(3)時間を有効活用できる
(4)日勤よりラクに働ける
(5)日中の用事をサクサクこなせる
- 5.夜勤の生活リズムが気になるのなら「交替制」がおすすめ!
- 6.生活リズムの乱れなく、希望に適した働き方を選択するために
1.そもそも「夜勤」とは?
「夜勤」とは、その言葉どおり「夜」に「勤務」することを意味し、厳密に夜勤は深夜労働のことを指します。このことから、暗くなり始める17時から21時までの4時間を働いても、それは夜勤と言いません。
夜勤で働く人の雇用形態は正規・非正規とさまざまですが、原則として満18歳未満の年少者の夜勤は労働基準法で禁止されているため、コンビニで働いている高校生が時給の高い深夜のシフトに入りたくても、午後10時~翌午前5時の時間帯に働くことはできません。これは満18歳未満の年少者が法的に保護されているためです。
また、妊娠した女性が会社から夜勤のシフトを組まれた場合、妊産婦が自ら「夜勤のシフトに入れない」と申し出れば、労働基準法の「母性保護規定」によって、雇い主はその意向を受け入れなくてはならないとしています。
夜勤の仕事って大変? 意外と知らない夜勤について徹底解説
2.夜勤は生活リズムが乱れやすく、体力的にきついって本当?
夜勤がある業種は意外とたくさんあります。
例えば工場などの生産現場から、運輸・タクシー業、医療機関、介護施設、宿泊施設、ファミレスなどの深夜営業の飲食店、ネットカフェ、深夜に行われる工事、コンビニエンスストア、警備・管理会社、警察・消防などは、みなさんもすぐに思いつく身近な仕事でしょう。
でも、消防士や警察官などの専門職や、コンビニや警備会社などのサービス業で夜勤をこなす人の多くは、「昼と夜が逆転するので、夜勤の仕事に就いた最初は大変かも……」と言います。こうした発言からも生活リズムが乱れやすく、体力的にきついという評判はあながち外れていないようですが、夜勤の仕事に従事する人はさまざまな工夫や対策を講じることでカラダを順応させ、与えられた仕事をまっとうしているようです。

では早速、夜勤で働くデメリットを見ていきましょう。
3.夜勤の生活リズムが乱れる以外のデメリットは?
では早速、夜勤で働くデメリットを見ていきましょう。
(1)夜勤は業務範囲も広くなる?
深夜のコンビニに行くと、アルバイトスタッフ1名が品出し・商品補充、納品・検品からレジまでの業務を、すべて一人でこなしているシーンを見かけますが、一人または少人数でのスタッフで業務をこなす夜勤の職場では、店長や管理職がいないぶんトラブルや事故が発生した際の臨機応変な対応力のほか、円滑に業務がこなす責任感やスキルが求められます。
(2)夜勤は眠りに入りにくくなる?
夜勤明けに自宅に戻って「さあ寝よう」と思っても、窓からは直射日光が降り注ぎ、道路を往来する車の走行音、街の喧騒、人々の話し声、家族の生活音などが気になって、眠りに入りにくくなることがあります。
夜勤をする人は、日差しが出ている時間に寝て、日が沈んでいるときに活動することになり、多くの人の生活スタイルとは昼夜が逆転するため、生活やカラダのリズムが乱れやすくなるデメリットがあります。

(3)夜勤は友人や家族と生活リズムが合わない?
友人などの親しい人が日中に働いていることが多い場合は、日帰り旅行や外出、食事、イベントへの参加など、一緒に出かけて楽しむ機会が減ることになり、家族ともそろって食事をする機会が減ることになります。こうした点から、夜勤の最大の悩みどころは、昼と夜が逆転した生活サイクルになることで、まわりの人と予定が合わせにくくなることかもしれません。
(4)夜勤で生活リズムが乱れると疲れやすい?
昼夜逆転の生活サイクルになることで、自分でも気づかないうちに自律神経に負担がかかり、カラダの不調を感じやすくなります。「疲れたな」と感じたら次のポイントに気をつけて、疲労を解消しましょう。
-
-
✓ しっかり睡眠をとるため、眠りに就きやすい環境を作る
✓ サウナなどでたっぷり汗をかき、老廃物を排出する
✓ 1日20分程度、太陽光を浴びて体内リズムを整える
✓ 20〜30分でよいので定期的にカラダを動かす
✓ 暴飲暴食は避ける
✓ アルコールや甘いものの摂取は適度に
-
4.夜勤は生活リズムが乱れやすいもののこんなメリットが!
ここからは、夜勤で働く魅力やメリットを見ていきましょう。
(1)日勤よりも賃金が高い
最大のメリットは、時給や賃金が高い点にあります。下図では通常の時間給1500円での「日勤」と「夜勤」の賃金の差を表していますが、夜10時~翌午前5時の夜勤のシフトに入った場合の賃金の計算方法は「働いた時間分の時間給×1.25倍」になるため、通常の時間給が1500円であれば375円が深夜割増分として上乗せされます。

また、介護職や看護師などが「夜勤」をする場合、割増賃金のほかに1回あたり数千円~2万円ほどの「夜勤手当」が設定されていることもありますが、「日勤」と「夜勤」の人が1日8時間働いた際の月給の差は数万円におよぶこともあり、ベースになる時間給が高ければ高いほどその差は大きくなります。
(2)通勤ラッシュとは無縁
夜勤で働く人の場合、道路の混雑しない時間帯に自家用車や自転車、オートバイなどを使って通勤する人が多い傾向にあります。また、電車やバスを利用して通勤する人も、朝夕のラッシュアワーと時間帯がかぶりにくいため、日勤の人が毎日感じている朝夕の大渋滞、電車やバスの混雑などとは無縁のストレスフリーな通勤ができるでしょう。
(3)時間を有効活用できる
土日や祝日に混雑するアミューズメント施設やテーマパーク、観光地にも、混雑していない平日に行けますし、大型量販店や人気店でのショッピングも混んでいない平日の時間帯なら、じっくり買い物ができます。そのほか、美容院や理容院やイベントも平日を狙えば予約が取りやすく、さまざまな場面で時間を有効活用できるメリットがあります。

(4)日勤よりラクに働ける
夜勤のデメリットとして、〈少人数で業務を担 当することが多い〉〈業務範囲が広くなり、責任が重くなる〉とご紹介しましたが、このデメリットも場合によってはメリットになります。
少人数で働くことが多い夜勤は、上司や管理職の顔色を窺うことや、同僚との人間関係に煩わされる心配が少なくなりますし、日中に比べて来店数も少ないので、慌ただしく業務に追われることがあまりないといえます。
(5)日中の用事をサクサクこなせる
日勤の人であれば、出勤時間を遅らせる、仕事の合間に抜け出す、有給を取得するなどの方法で病院、役所、銀行などに行って用事を済ませることが多いのですが、夜勤の人は日中の時間を自由に使えるため、平日の日中の時間を活用すれば長い時間待たされることなく、用事を済ませられます。
5.夜勤の生活リズムが気になるのなら「交替制」がおすすめ!
夜勤には、さまざまなメリット、デメリットがあることが理解できたところで、「夜勤で働きたいけれど、家の事情などを考えると生活リズムが崩れやすい夜間の仕事は難しそう……」「夜勤がずっと続くとカラダがきつそう……」と思い悩んでいる人は、交替制勤務にも目を向けてみましょう。
交替制勤務とは1日の勤務時間を2〜3つのシフトに分け、複数の従業員が交替で勤務形態のことを指します。24時間体制でフル稼働する製鉄、自動車、半導体、食品などの製造現場では、従業員が3交替制で勤務することによって現場を支え、工場の稼働が止まらないようにしています。
24時間フル稼働する製造現場では従業員が「日勤」「準夜勤」「夜勤」の3交替制のシフト制を敷いていることが多く、シフトを上手に組み合わることで夜勤限定の働き方をしなくて済む可能性があります。
また、同じ夜勤でも、その企業のシフトが「日勤」「準夜勤」「夜勤」の3交替制か、または「日勤」と「夜勤」の2交替制かによって、労働基準法が定める「休日」の規定が異なるので、夜勤で働くことに不安を抱いている人は、安心材料を増やすためにその職場で働く人はどのようなローテーションで働いているのか、どのように休日をとって生活リズムを整えているのかなどを事前に確認するようにしましょう。

6.生活リズムの乱れなく、希望に適した働き方を選択するために
時給のよい「夜勤」をあえて選択して効率的に稼ぎたい……、日勤と夜勤をローテーションさせて、カラダの負担を上手にコントロールしたい……など、その人のライフスタイルや求めるものによって、働き方は千差万別ですが、最近は日勤の賃金より割高な深夜割増分を重視し、夜勤をメインにする「夜勤専従」と呼ばれる人も増えています。
「夜勤専従」の人は遮光カーテン、騒音が少ない住環境など快眠を取りやすい環境を整えてデメリットを克服しているようですし、交替制の職場では従業員が心身ともに健康であるよう、休日を取りやすい環境を整えているところも最近は増えてきています。
——夜勤を選択する際には、賃金、休日、メリット、デメリットなどさまざまな観点からしっかり比較検討し、心とカラダの健康をしっかり維持するためにも、自分の希望に最も適した働き方を選択するよう心がけてくださいね。
