ニートとフリーターは違う?ニートの定義や実態、ニートからの脱出方法も紹介!
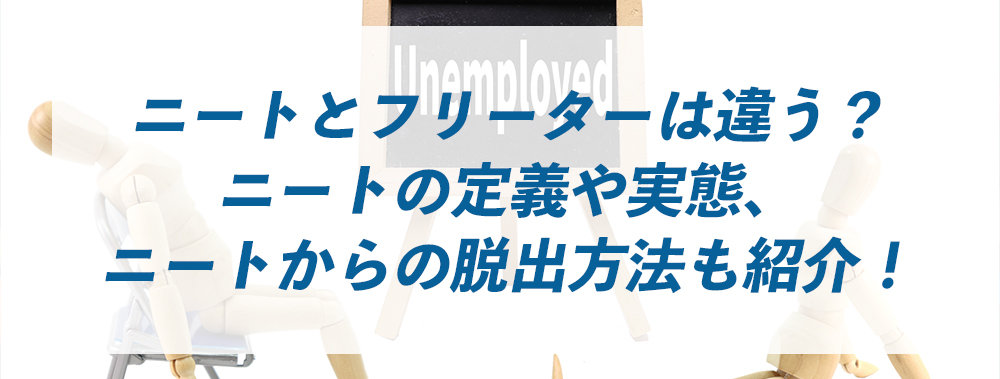
2023/12/12 更新
そもそも「ニート」とは?
ニートの定義
「Not in Education, Employment or Training」の頭文字をとった「ニート(NEET)」という言葉は、1990年代に英国の労働政策の中で登場した造語で、「就学・就業していない、職業訓練も受けていない者」を指す呼称として使われるようになりました。
日本においては、2000年代に入ってニートという言葉が広まり、厚生労働省や内閣府では、ニートの対象者を以下のように定義づけています。
-
-
【ニートとは】
通学・家事をしていない15~34歳の若年者のうち、就業していない(求職活動していない、働く意思がない)無業者
-
35歳以上の無業者はニート?
この定義によると、ニートに該当するのは「学生や主婦(主夫)を除く34歳までの若年無業者」で、35歳以上の無業者に対する呼称に明確な定義はありません。35歳以上の無業者に対しても、広い意味でニートという呼称は使われていますが、一般的には「中年層ニート」「中年無業者」などと呼ばれることが多いようです。
ニートとフリーターの違いは?
フリーターの定義

同じく、定職に就かない若者に対して使われる「フリーター」という呼称ですが、ニートとの違いは何なのでしょうか。「フリーアルバイター」の略称となるフリーターという呼称についても、厚生労働省や内閣府が以下のように定義づけています。
-
-
【フリーターとは】
15~34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、次のいずれかに該当する人
●雇用者のうち、勤め先における呼称が「パート・アルバイト」である者
●完全失業者のうち、探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
●家事も通学もしていない者のうち、 就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
-
このように、ニートとフリーターの大きな違いは「働いているかどうか」「仕事を探しているかどうか」という点です。よって、失業中などで現在働いていなくても、アルバイトやパートの仕事を探している求職者はフリーターとして扱われ、ニートに該当しないことになります。
ちなみに、内閣府の定義では、35歳以上でパートやアルバイトをしている人は「非正規労働者」「アルバイト」という呼称になり、フリーターとは区別して扱われています。
ニートの現状と背景について
国内にニートはどれぐらいいる?
総務省統計局の労働力調査によると、国内でニートに該当する若年無業者の数は、2022年平均で57万人、35~44歳の無業者(中年層ニート)の数は36万人。ここ10年の無業者数の推移(下記グラフ)を見ると、若年層は微増傾向、中年層は横ばいの状態が続いていることがわかります(2020年の若年層の急増はコロナ禍の影響と考えられる)。
また、12~24歳、25~34歳、35~44歳ごとの無業者の数は、年齢層が高くなるにつれて増えており、年齢とともに仕事に就くのが難くなる傾向にあることを示しています。

※参考資料(グラフ出典)/総務省統計局「労働力調査(基本集計)2022年平均結果の要約」
index1.pdf (stat.go.jp)
ニートが就職しない理由
総務省の「就業構造基本調査結果」によると、ニートが就職しない理由として最も多いのが「病気やケガ」です。この中には、メンタル面の不調や疾患(うつ病・パニック障害など)が多く含まれていると見られています。
また、就職を希望しているが求職活動は行っていない「非求職型」のニートと、就職そのものを希望していない「非希望型」のニートでは、就職しない理由が若干異なっていることがわかります。非希望型では「とくに理由はない」という回答が多いことから、なんとなくニートを続けている人が多い傾向にあるようです(以下参照)。
-
-
【非求職型のニートが就職しない理由トップ5】
《1》病気やケガのため……26.5%
《2》その他……24.0%
《3》学校以外で進学や資格取得などの勉強中……12.3%
《4》探したが見つからなかった……11.0%
《5》知識・能力に自信がない……10.5%
-
-
-
非希望型のニートが就職しない理由トップ5】
《1》病気やケガのため……29.7%
《2》その他……27.8%
《3》とくに理由はない……15.8%
《4》学校以外で進学や資格取得などの勉強中……12.1%
《5》仕事をする自信がない……6.4%
-
※参考資料(直近データ)/総務省「平成24年 就業構造基本調査結果」
kgaiyou.pdf (stat.go.jp)
ニートになってしまう原因

ニートが就職しない理由は人それぞれにあると思いますが、はじめからニートになりたいと思ってなった人は、ほとんどいないのではないでしょうか。にもかかわらず、若年者がニートになってしまうきっかけや主な原因としては、以下のような点が考えられます。
-
-
●就職活動に何度も失敗して諦めた
●一度就職したが、仕事や職場が合わず退職した
●親と同居していて、働かなくても生活に困らない
●人との関わりが苦手で、家に引きこもりがちになった
-
ニートを続けるリスク

ニートを続けている人の中には、「とりあえず、今は働かなくてもいいか」「就職は○○歳になったら考えよう」と、仕事に就くことを先送りにしてしまう人も少なくないようです。
とはいえ、今は親の経済的支援で生活できていても、親が高齢になって収入が減ったり、亡くなったりして頼ることができなくなれば、当然ながら生活に困窮することになります。結婚を考えたときにも、生活力のなさでパートナーが見つからない、パートナーがいても二の足を踏まれる、相手の家族から反対されるなど、厳しい状況になる可能性が高くなるでしょう。
また、仕事に就くまでのブランクが長くなればなるほど、社会に出たとき・復帰したときのギャップは大きくなりますし、年齢とともに就職へのハードルが高くなっていくのも事実です。たとえそれが「親の介護」や「病気の治療」といった正当な理由であっても、年齢を重ねてブランク期間が長引くほど就職に不利になることは覚えておきましよう。
ニートから脱出するには
では、ニートをやめて働きたいと思ったとき、何から始めればいいのでしょうか。以下、ニートから脱出するためのポイントや具体的な方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
生活習慣を改善する

不規則な生活や運動不足が続くと、仕事を始めても身体がついていけず、朝起きられない、通勤がしんどい、仕事がキツくてこなせないなど、さまざまな支障が生じて心理的なプレッシャーになることも。まずは、毎朝6~7時に起床して太陽の光を浴び、遅くとも夜12時までには就寝するようにしましょう。朝食・昼食・夕食も決まった時間に摂り、できるだけ栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。
また、適度な運動も基礎体力をつけ、心身のバランスを保つことに役立ちます。手軽に始められる運動としては、1日30~40分程度のウォーキングがおすすめです。ウォーキングを始めると外に出る機会が増えるので、自宅に引きこもりがちな人にも好適です。
できる仕事から始めてみる

自分で働いてお金を手にすれば、自信とやりがいを持って仕事に取り組めるようになります。まずは、ハードルの低い単発・短期のアルバイトやパートなど、できる範囲の仕事から始めてみましょう。ブランクが長くても、アルバイトやパートであれば採用される可能性が高く、週に2~3日・1日数時間といった負担の少ない働き方も可能です。また、人との会話やコミュニケーションが苦手であれば、データ入力などの在宅ワークからスタートするのもいいでしょう。
さらに、将来的に正社員就職したいと考えているのであれば、まず単発の派遣社員や契約社員として働き始め、職場体験を積むことで自信をつけていくのもおすすめです。また、正社員登用制度のある企業を選べば、アルバイトやパートとして働きながら正社員になれる可能性もありますので、制度の有無や登用条件を応募時に確認しておきましょう。
資格を取る

資格を持っていると就職に有利になるとともに、自分に自信がつくという利点もあります。比較的取得しやすい資格としては、介護系であれば「介護職員初任者研修」、IT・事務系であれば「マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)」や「ITパスポート試験」、クリエイティブ系であれば「Webクリエイター能力認定試験」や「Webデザイン技能検定」などがあります。いずれも、受験するために必要な条件はありませんので、興味のある人はぜひ検討してみてはいかがでしょう。
国や民間の就活支援サービスを利用する

ニートが仕事探しをする上では、全国の各都道府県に設置されているハローワークや、民間の就職・転職エージェントを利用すると、自分にマッチした仕事が見つけやすくなるでしょう。いずれも、自分の希望・適性に合った仕事選びはもちろん、プロによる就業相談や応募書類の作成支援など、さまざまなサポートが受けられますので、一人で就活を進めるのが不安な人にもおすすめです。
そのほか、全国に177ヵ所に設置された「地域若者サポートステーション(通称サポステ)」や、全国の46都道府県に設置された「若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ)など、若年層の就職を支援する公的機関・施設もあります。利用に関する詳細や支援サービスについては下記サイトで確認できますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
サポステ[地域若者サポートステーション] (mhlw.go.jp)
ジョブカフェにおける支援 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
まとめ
今回は、ニートの定義や現状、フリーターとの違いについて解説しながら、ニートを続けるリスクやニートから脱出する方法などをご紹介しました。
ニートは「働いていない」「仕事を探していない」という点で、フリーターと比べると社会的にもネガティブに捉えられがちです。まだ若いうちの短期間、ニートであることはさほど問題にならないかもしれませんが、ズルズルとニートを続ければ続けるほど、就職を含めたさまざまな面で不利になり、将来への不安やリスクも深刻化していきます。
現在、なんとなくニートを続けている方はもちろん、ニートをやめて働きたいと考えている方も、本記事でご紹介したポイントやアドバイスを参考に、“脱ニート”に向けた一歩を踏み出していただければ幸いです。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験者歓迎の工場ワークを多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。製造業やモノづくりの現場で働きたい方も、ニートから派遣・契約社員や正社員を目指したい方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
