【夜勤明けの過ごし方】疲れを溜めないコツや心身のリフレッシュ法を紹介!
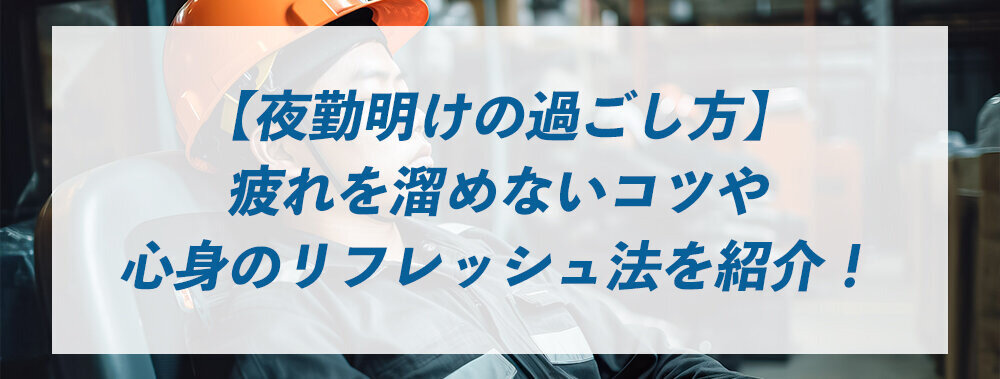
2024/10/22 更新
夜勤がキツイ・しんどいと感じた時は?

工場で働く人の多くが経験する夜勤。しかし、昼間に休んで夜働くサイクルは、人間の体内時計や生活リズムが乱れやすくなるため、夜勤明けの過ごし方によっては、「いくら寝ても眠い・だるい・疲れがとれない」といった体調不良を招きやすくなります。
よって、夜勤がキツイ・しんどいと感じた時は、まず夜勤明けの過ごし方を見直してみましょう。その基本ポイントとなるのが、身体と生活のリズムを整える「睡眠」「食事」「入浴」です。では、夜勤明けの睡眠・食事・入浴のコツについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
夜勤明けの睡眠のとり方のコツ
帰宅後は3時間ほど仮眠をとる

夜勤明けで帰宅したら、活動する前に3時間ほど仮眠をとりましょう。短時間の仮眠は睡眠不足の脳をリフレッシュさせ、疲労感の軽減や疲労蓄積の予防にも効果的です。
ちなみに、人間は浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」を約90分周期で繰り返しています。入眠後の90分はレム睡眠の状態にあるため、比較的スッキリと目覚めることができ、起きた後も疲労感が残りにくいとされています。一方で、ノンレム睡眠中は深く眠っているので起きづらく、ムリに起きても疲労感が残りやすくなります。したがって、2サイクル目のレム睡眠で覚醒できる3時間前後の仮眠が、夜勤明けには好適なのです。
夜勤明けに長時間寝るのはNG?

とはいえ、夜勤明けは疲れて眠いので、長時間しっかり寝たいという人もいるでしょう。しかし、昼間に寝すぎると夜に眠れなくなり、次の日の生活に影響が出てしまいます。身体と生活のリズムを整えるためにも、夜勤明けの睡眠は短時間にとどめ、夜はいつも通りの時間か少し早めに就寝するのがおすすめです。
夜勤明けの食事のとり方と入浴のコツ
仮眠前は消化の良い食事を軽めにとる

夜勤明けは疲れてお腹も空いているので、こってりしたラーメンや揚げ物、ボリュームのあるカレーや甘いデザートなどを食べる人も多いようです。しかし、仮眠する前に脂っぽい高カロリーの食事をしたり、必要以上に食べ過ぎたりすると、肥満の原因になるだけでなく、睡眠中に胃に負担がかかって、消化不良や胃もたれを起こす恐れがあります。
夜勤明けには消化の良い食事(うどん、おかゆ、温野菜、ヨーグルト、スープ、フルーツなど)を軽くとる程度にして、しっかりとした食事は仮眠後にとるようにしましょう。
入浴してから仮眠をとる

夜勤明けは、仮眠する前に入浴することをおすすめします。仕事の汚れや汗を洗い流して湯船に浸かれば、気分もすっきりして快適に眠れるはずです。疲れすぎて気力がなければシャワーだけでもかまいませんが、湯船に浸かると水圧と温熱の相乗効果で血流がスムーズになり、足腰のだるさや全身の疲れを軽減することができます。
ただし、熱いお湯に長時間浸かると、交感神経が活発になって寝付きが悪くなるので要注意。全身の疲労を和らげつつ、心身のリラックス効果を高めるためには、38~40℃のお湯に15分程度浸かるとよいでしょう。
リフレッシュできる夜勤明けの過ごし方のパターン
夜勤明けの自由時間をどう過ごすかは人それぞれですが、主な行動パターンとしては「アクティブ系」と「リラックス系」の2種類があります。夜勤明けに何をしようと迷ったら、自分の趣味や好み、その日の気分や体調に合わせて試してみてください。
夜勤明けの過ごし方の一例《アクティブ系》

外出してレジャーや趣味を楽しんだり、身体を動かしたりすることで、心身ともにリフレッシュするなら、以下のような行動パターンがおすすめです。平日昼間の時間帯は、お店や施設、交通機関なども比較的空いているので、人ごみや混雑を避けてスムーズに行動できます。また、平日昼間の時間を有効活用して、たまった家事や用事などを一気に済ませるのもいいでしょう。
-
-
●デパートやショッピングモールへ買い物に行く
●映画館や美術館、カラオケに行く
●近場の観光スポットへドライブに行く
●スパやサウナ、スポーツジムで汗を流す
●散歩やジョギング、サイクリングに行く
●習い事やサークル活動に参加する
●家の掃除や銀行・役所などの用事をまとめて済ませる
-
夜勤明けの過ごし方の一例《リラックス系》

自宅でのんびり過ごしながら、仕事のストレスや疲れを癒してリフレッシュするなら、以下のような行動パターンがおすすめです。ゆっくり休養したい時はもちろん、悪天候で外出したくない時にもGOOD。自宅なら時間を気にせず好きなことに没頭でき、リラックスしながら気分転換を図れるのがメリットです。
-
-
●観たかったドラマや映画を一気に見る
●読書やゲーム、趣味に集中する
●手の込んだ料理やお菓子作りに挑戦する
●家庭菜園やガーデニングを楽しむ
●ヨガやピラティスで心身を整える
●資格や趣味の勉強をする
-
疲れを溜めない夜勤明けの過ごし方のスケジュール例
では、ここまで見てきたポイントを踏まえて、疲れを溜めない夜勤明けの過ごし方のスケジュール例を紹介しましょう。外出してアクティブに活動したい人も、自宅でリラックスしたい人も、ぜひ参考にしてみてください。
-
-
【9時 帰宅後に食事をする】夜勤明けで家に帰ったら、早めに食事を済ませます。高カロリーの食事や食べ過ぎを避け、消化に良いものを軽く食べましょう。
-
-
-
【10時 入浴する】できればシャワーだけで済まさず、しっかり入浴しましょう。湯船に浸かることで全身がほどよく温まり、新陳代謝が促されて疲労感が和らぎます。お湯の温度が高すぎると入眠しにくくなるため、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。
-
-
-
【10時30分 ストレッチやマッサージで全身をほぐす】入浴後は全身が温まっているので、ストレッチやマッサージをすることで、筋肉の疲れがほぐれやすくなります。また、水分補給も忘れないようにしましょう。
-
-
-
【11時 仮眠をとる】夜勤の疲れをとるためにもソファなどでのごろ寝は避け、ベッドや布団に入って寝ましょう。部屋の明るさや周囲の音が気になる場合は、遮光カーテンやアイマスク、耳栓などのアイテムを取り入れるのもおすすめです。
-
-
-
【14時 起床して食事をとる】起床してお腹が空いていたら食事をとります。夕食に影響しないよう、できるだけ消化のよいものを食べ、食べ過ぎにも注意しましょう。
-
-
-
【14時30分 好きなことをして過ごす】自宅でリラックスしたい人も、外出してアクティブに活動したい人も、自分の好きなことをして心身ともにリフレッシュしましょう。
-
-
-
【19時 夕食をとる】日勤の時と同じ時間帯に夕食をとります。家族や友人と食事に行くのもリフレッシュになるでしょう。
-
-
-
【20時30分 ゆっくりと入浴する】湯船にゆっくりと浸かって心身の疲れを癒しましょう。お好みの入浴剤を湯船に入れて、香りを楽しみながらリラックスするのもおすすめです。
-
-
-
【22時 就寝する】睡眠時間を確保するためにも、いつもより早めに就寝します。寝る前のパソコン作業やスマホ視聴は、睡眠の質を低下させるので避けましょう。
-
まとめ
今回は、夜勤明けの過ごし方について解説しました。
夜勤明けは一般的な生活と昼夜が逆転している状態にあるため、体内時計や生活のリズムが崩れやすくなっています。だからこそ、夜勤明けにきちんとした睡眠や食事、入浴を心がけることで、不規則な生活リズムと体調を整え、健康的な毎日を送ることができるのです。
こうした夜勤明けの基本ポイントを押さえつつ、身体を動かしてアクティブに活動したり、自宅で好きなことをしてリラックスしたりと、自分に合った過ごし方を工夫して、心身の疲れを残さないようにすることが大切です。ぜひ、本記事でご紹介したポイントを参考にしながら、夜勤明けのリフレッシュに役立ててくださいね!
――日総工産<工場求人ナビ>では、未経験歓迎の工場ワークや正社員募集の求人を多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職に向けたサポート体制も充実!社内ニートから転職したい方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
