フリーターが納める税金の種類や支払額、控除の仕組みなどを徹底解説!
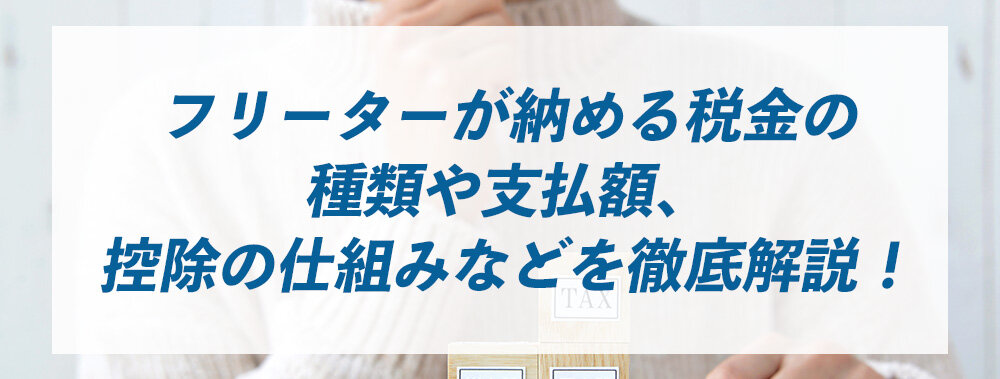
2024/5/10 更新
フリーターにも納税義務がある
正規・非正規などの雇用形態に関係なく、税金は所得のあるすべての国民が納めなければいけません。したがって、アルバイトやパートで働くフリーターでも、一定以上の収入があれば、正社員と同じように「所得税」や「住民税」を納める義務が生じます。さらに、状況によっては「国民健康保険」や「国民年金」の保険料を、自分で支払わなければいけない場合もあります。
所得額や勤務先、働き方などによって、フリーターが納めなければいけない税金・保険料の種類は異なってきますが、主なものを挙げると以下の通りとなります。
-
-
【フリーターが納めなければいけない主な税金・保険料】
《1》所得税
《2》住民税(都道府県税・市区町村民税)
《3》健康保険料(国民健康保険または被用者保険)
《4》単純作業の繰り替えしが苦痛な人、飽きやすい人
《5》雇用保険料
-
では、以上《1》~《5》の税金・保険料について、納税義務が生じる所得金額や納税額(税率)、納付方法などを詳しく見ていきましょう。
フリーターが納める税金《1》所得税

所得税とは1年間の所得に対して一定の税率を課す税金で、年収(年間の総所得金額)が103万円を超えた場合はフリーターも課税対象になります。年収から各種控除を差し引いた金額(課税対象となる金額)に、規定の税率をかけて算出するため、収入が多くなるほど納付する所得税は高くなります(以下参照 ※)。

※参考資料/国税省「所得税の税率」より出典
所得税は、勤務先の給与から毎月天引きされるのが一般的です。毎月天引きされる所得税は概算した金額(仮定額)なので、本来納めるべき金額(正式な所得税額)より多くなるケースがあります。それを是正するために、正式な所得税額を年末調整や確定申告で精算し、多く払いすぎていた場合には還付されます。
フリーターでも確定申告は必要?

確定申告とは、1年間の所得に対してかかる所得税を、自分で申告する手続きのことです。勤務先で年末調整を受けていなかったり、2つ以上の仕事を掛け持ちしたりする場合、フリーターでも確定申告で正しい所得を申告する必要があります。
ただし、複数の勤務先から給料をもらった場合、年末調整されなかった給料の合計額が20万円を超えていなければ申告は不要です。また、仕事を掛け持ちしておらず、勤務先で年末調整を受けている場合や、年収が103万円を超えない場合も申告する必要はありません。
フリーターが納める税金《2》住民税

住民税は、居住している都道府県および市区町村に納める地方税です。自治体によりますが、多くの場合、前年度の年収が100万円を超えると課税対象となります。
住民税の納税額は、すべての対象住民に一律に課される「均等割」と、所得額に応じて支払う「所得割」の合算によって決定します。納税額の算出方法は自治体によって異なりますが、均等割は「一律5000円」、所得割は「対象課税額の10%」が一般的な目安となります。これで住民税の年間納税額を算出すると、対象課税額が100万円の場合は「100万円×10%+5000円=10万5000円」となります。
なお、住民税の納付方法は、勤務先の給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の2種類があります。普通徴収の場合は、自治体から自宅へ納付書が郵送されてきますので、一括払いまたは年4回の分割払いから選んで期限内に納めてください。
フリーターが納める保険金《3》健康保険料
健康保険料は、医療機関でかかった医療費の自己負担を、一定の割合に抑えられる国の保険制度です。健康保険には「国民健康保険」と「被用者保険(社会保険)」の2種類があり、国民はいずれかの保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険について

国民健康保険は、会社に勤めていないフリーランスや自営業、年金受給者など、社会保険に加入していない人が対象となります。よって、勤務先の社会保険に加入していないフリーターも、国民健康保険に加入する義務があり、自分で保険料を支払わなければいけません。ただし、年収130万円未満のフリーターが親や配偶者の扶養内で働く場合は、国民健康保険への加入が免除されます。
なお、国民健康保険料の算出方法は自治体によって異なるため、住んでいる市区町村のサイトなどで確認してください。納付方法は、口座振替または納付書による支払いが基本となります。
被用者保険(社会保険の健康保険)について

被用者保険は会社で加入する社会保険のひとつ(健康保険)で、主に健康保険組合(組合健保)や全国健康保険協会(協会けんぽ)の2種類があります。フリーターの場合、年収130万円を超えると社会保険の加入義務が生じますが、年収130万円を超えないフリーターも、以下の要件に当てはまれば社会保険の加入対象となります。
-
-
【社会保険の加入要件】
●学生ではない
●1ヵ月の給料が8万8000円以上
●見込まれる雇用期間が2ヵ月以上
●1週間の所定労働時間が20時間以上
●勤務先の従業員数が101人以上
※2024年10月以降は、従業員数51人以上の勤務先も対象になります)
-
被用者保険の場合、保険料の半分は勤務先の会社が負担し、残りの半分が給料から天引きされるのが一般的です。保険料率は組合・協会によって異なりますが、収入の9%~10%台が目安です。たとえば、月給が15万円の場合、毎月の保険料は1万5000円程度、本人負担の折半額は7500円程度となります。
フリーターが納める保険金《4》年金保険料
年金保険は将来に備える公的な保険制度で、基礎年金となる「国民年金保険」と会社で加入する「厚生年金保険(社会保険)」の2種類があります。
勤務先の社会保険に加入していないフリーターは、国民年金のみに加入することになりますが、社会保険の加入要件を満たしていれば厚生年金に加入することも可能です。また、厚生年金の保険料には国民年金の保険料も含まれているため、勤務先の厚生年金(社会保険)に加入しているフリーターの場合は、別々に加入・納付する必要はありません。
国民年金保険について

国民年金保険は、収入に関係なく20歳以上60歳未満の国民に加入義務があります。国民年金の保険料は収入に関わらず一律で決まっており、2024年度の1ヵ月あたりの保険料は1万6520円となっています。口座振替や納付書、クレジットカードなどで納付でき、12ヵ月分を一括で前払いすると、割引が適用されるのでお得です。
厚生年金保険について

厚生年金保険は、前述した国民年金保険の基礎年金に上乗せして支給される年金です。厚生年金に加入すれば、定年後に国民年金と合わせた年金をもらえるので、国民年金のみの加入より受給額が多くなるのがメリットです。
厚生年金の保険料の半分は勤務先の会社が負担し、残りの半分が給料から天引きされるのが一般的です。保険料は毎月の給与ラインの金額を標準報酬として、その金額に18.3%をかけて算出します。たとえば、毎月の給与が10万円の場合、標準報酬は9万8000円で、毎月の保険料は「9万8000円×18.3%=1万7934円」、本人負担の折半額は8967円となります。
フリーターが納める保険金《5》雇用保険料

雇用保険は会社で加入する社会保険のひとつで、失業して収入が途絶えた場合や、育児・介護などで休職した際に、国から一定期間手当が支払われます。雇用保険料も会社と従業員(本人)の双方で負担しますが、支払額は従業員の負担が軽い設定となっています。もちろん、フリーターでも以下の要件を満たすことで雇用保険への加入が可能です。
-
-
【雇用保険の適用要件】
●見込まれる雇用期間が31日以上
●1週間の所定労働時間が20時間以上
●学生ではない(休学中の者など、例外もあり)
-
フリーターが知っておきたい「控除」について

控除(こうじょ)とは「金額などを差し引く」という意味です。税金は、年収から控除額を差し引いた額に税率をかけて算出するため、控除を利用することで納税額を低く抑えることができます。控除にはさまざまな種類がありますが、ここではフリーターが知っておきたい「4つの控除」について解説します。
基礎控除
基礎控除とは、所得税を計算する際に、年収から差し引くことのできる基本の控除です。控除額は納税者の年収によって異なります(以下参照 ※)。たとえば、年収2400万円以下であれば、年収から48万円の控除額を差し引いた額に所得税が課せられます。

※参考資料/国税省「基礎控除」より出典
給与所得控除
給与所得控除とは、勤務先から給料をもらっている人が利用できる控除です。控除額は納税者の年収によって異なります(以下参照 ※)。

※参考資料/国税省「給与所得控除」より出典
扶養控除

扶養控除とは、配偶者以外の親族を扶養する場合に利用できる控除です。扶養対象となる人の年齢によって控除額は異なり、16歳以上で38万円、19歳~23歳未満で63万円となっています。また、70歳以上の親族を扶養する場合は、同居の有無で控除額が異なり、同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円です。
なお、親の扶養に入っているフリーターの場合、年収が103万円を超えると、親が扶養控除を受けられない(扶養から外れる)ので注意しましょう。
配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者(夫や妻)のいる人が利用できる控除です。控除を受ける納税者の年収が1000万円以下で、配偶者の年収が年間48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)であれば控除を受けられます。控除額は、控除を受ける納税者の年収によって異なります(以下参照 ※)。

※参考資料/国税省「配偶者控除」より出典
税金が支払えない場合はどうする?

税金や保険料を自分で納める(給与から天引きされない)場合、決められた期限までに必ず納付しましょう。期限を過ぎても支払いが確認できない場合、役所から督促状が送られてきます。それでも滞納を続けていると、電話や訪問による勧告があり、高額な延滞金が加算されたり、資産が差し押さえられたりする可能性もありますので注意してください。
税金や保険料の負担が大きく、どうしても支払えない場合は、住んでいる市区町村の役場に行って早めに相談しましょう。支払えない理由によっては、納付期限が猶予されたり、支払いが免除されたりすることもあります。
たとえば、所得が少なくて国民年金保険料の支払いが困難な場合は、保険料の支払いが免除、または猶予となる「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が利用できます。詳しくは下記、国民年金機構のサイトをご覧ください。
まとめ
今回は、フリーターが納める税金や保険料について、押さえておきたい基本的なポイントを中心に解説しました。
ご紹介したように、フリーターでも一定の収入があれば納税義務が生じますし、20歳を超えると、国民年金保険の加入も義務づけられます。収入によっては、税金や保険料の支払いがキツイと感じるかもしれませんが、適用できる控除を利用したり、役所に相談したりすることで負担を軽くできる可能性もありますので、過度に心配する必要はありません。
ただし、どのような理由であっても、納めるべき税金や保険料を未納のまま放置すると、後々大きなリスクを負う可能性もありますので、納税の義務や重要性をしっかりと理解し、きちんと支払うことを心がけてくださいね。
