フリーターが社会保険に加入する条件とメリット
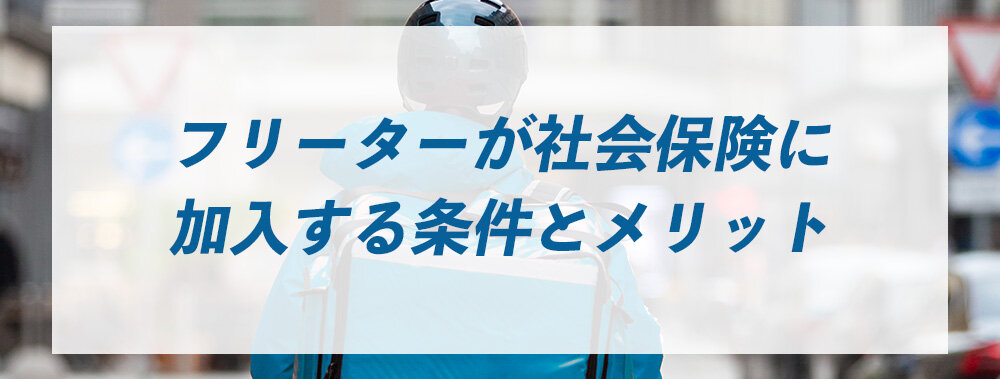
2024/11/20 更新
-
■目次
- 1.社会保険の基礎知識①「国民皆保険制度」とは?
- 2.社会保険の基礎知識②社会保険とは?
- 3.社会保険の基礎知識③公的医療保険制度を最も早く導入したドイツ
- 4.社会保険の基礎知識④医療においても自己責任の精神が根づく米国
- 5.社会保険の基礎知識⑤社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い
- 6.社会保険の基礎知識⑥フリーターも、社会保険の加入対象?
- 7.社会保険の基礎知識⑦国民健康保険には出産手当がない?
- 8.社会保険の基礎知識⑧国民健康保険には、傷病手当がない?
- 9.社会保険の基礎知識⑨国民健康保険に加入、または脱退する方法
- 10.社会保険の基礎知識⑩社会保険の加入・脱退手続きの流れ
- 11.社会保険の基礎知識⑪フリーターが健康保険に加入するメリット
- 12.社会保険の基礎知識⑫フリーターが厚生年金に加入するメリット
- 13.社会保険の基礎知識⑬フリーターが雇用保険に加入するメリット
- 14.社会保険の基礎知識⑭フリーターが労災保険に加入するメリット
- 15.社会保険の基礎知識⑮「103万円」「106万円「130万円」の壁とは?
- 16.社会保険の基礎知識⑯【103万円の壁】は“所得税の壁”
- 17.社会保険の基礎知識⑰【106万円の壁】は“社会保険の壁”
- 18.社会保険の基礎知識⑱【130万円の壁】は“扶養の壁”
- 19.社会保険の基礎知識⑲フリーターも、年収によって様々な義務が生じる
- 20.社会保険の基礎知識⑳健康保険と年金未加入時に発生するリスク
-
・【健康保険に加入していないときのリスク】
・【年金未加入者に発生するリスク】
社会保険の基礎知識①「国民皆保険制度」とは?
日本では1955年頃まで農業・漁業従事者や自営業者、零細企業の従業員を中心とする国民の約30%(約3000万人)が無保険者でしたが、1958年に国民健康保険法が制定されたことで、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険医療を受けられる体制が確立しました。この保険制度を「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」と呼びます。
【国民皆保険制度】
すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、互いの医療費を支え合う「国民皆保険制度」は、国が発行する保険証(※)一枚によって、誰もが医療機関や医療サービスを受けられる制度を指します。
※保険証 = 2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は終了し、医療機関・薬局を利用する際はマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行する予定です
この「国民皆保険制度」を支えているのが、「社会保険(健康保険)」と「国民健康保険」の2つの公的医療保険であり、国民皆保険制度が採用される日本では、国民すべてが「社会保険(健康保険)」と「国民健康保険」のどちらかに加入しています。
社会保険の基礎知識②社会保険とは?
会社員や公務員、条件を満たすアルバイト・パートなどの短時間労働者が加入する社会保険は、社会生活を営むうえで起こりうる様々なリスクに備える公的な強制保険制度です。
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つの総称で、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」は労働保険と呼ばれます。
社会保険の大きな特徴は、運営者と被保険者が折半して、毎月の給与から天引きされる形で保険料を支払うことにありますが、そのほかの違いについても下図を参照して違いを理解しましょう。

社会保険の基礎知識③公的医療保険制度を最も早く導入したドイツ
日本の「国民皆保険制度」と同様の公的医療保険制度はドイツ、フランス、オランダなどのヨーロッパ諸国でも採用されていて、最も早く社会保険形式を導入した国はドイツとされています。
また、2023年の社会保障制度の充実度ランキング(2023年)では北欧諸国が名を連ね、1位はデンマーク、2位はノルウェー、3位はフィンランドになっていて、質の高い教育、医療、社会保障を受けられる国を「SDGs先進国」と呼びます。
同ランキングで28位にランクインする日本は、社会保障制度の水準が公的医療保険が未整備であるアメリカと同水準とかなり低く、社会保障制度を充実させるために以下のような課題が山積しています。
-
-
●男女の賃金格差是正、女性の地位向上、夫婦別姓をはじめとするジェンダー平等
●女性の社会進出や、管理職比率の向上
●子育てをしながら働きやすい環境の整備
●高齢化・少子化などの社会構造の変化に伴う社会保障制度の財源減少 など
-
社会保険の基礎知識④ 医療においても自己責任の精神が根づく米国
米国では全国民をカバーする公的医療保険制度がなく、国民の半分ほどが民間の医療保険(低所得者や高齢者・障害者は国や州が運営する公的医療保険)に加入しています。連邦制で州の権限が強い米国は、個人の生活に干渉しないという自己責任の精神が根づいていて、この精神性が社会保障制度のあり方に影響をおよぼしているとされます。こうした背景から、米国では、医療機関にかかったときに高額な医療費を請求されることも珍しくなく、医療費を支払えず自己破産する人も多くいます。
日本と米国の医療サービスのわかりやすい違いに、日本では急病を発したときに、費用が国の交付金と行政サービスで賄われている救急車が無料で駆けつけてくれますが、米国では、消防局などが運営する公的救急車も民間救急車も有料(タクシーのように走行距離や医療器具の使用によって料金が変動)で、その費用は利用者自身が負担します。

社会保険の基礎知識⑤ 社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い
健康保険には、雇用先を通じて企業とともに保険料を折半する社会保険(健康保険)と、自営業者などが加入する国民健康保険があります。
-
-
【社会保険(健康保険)】
● 保険者は、国や企業などの公的団体の運営者(健康保険組合)
● 被保険者は、万一の際に保険料を給付される人のことで、会社員や公務員、または条件を満たす短時間労働者のアルバイト・パートなど
● 保険料の負担は、勤務先と折半
● 家族が増えても、保険料は変わらない
-
-
-
【国民健康保険】
● 保険者は、市町村の国民健康保険組合など
● 被保険者は、農業・漁業従事者や、74歳以下の個人事業主(※)
● 保険料は、全額自己負担
● 国民健康保険には、扶養(※)という概念がない
● 家族が増えると保険料が変わる扶養者分を合算すると金額が跳ね上がることもある
-
※扶養 = 社会保険における扶養とは、「未成年」「高齢」「失業している」などの理由で生計を立てられない人を家族や親族が援助することを指します
※個人事業主 =フリーランスを含む個人で事業を営んでいる自営業者
社会保険の基礎知識⑥ フリーターも、社会保険の加入対象?
「社会保険の基礎知識⑤」で解説したとおり、社会保険(健康保険)の加入対象(被保険者)には、会社員や公務員のほかに、非正規雇用のフリーター、アルバイト、パートの短時間労働者も含まれます。
非正規雇用のフリーター、アルバイト、パートが、社会保険(健康保険)の加入対象(被保険者)として認められるには、次のような条件があります。
-
-
従業員数(厚生年金の被保険者数)が101名以上(※)の勤務先で、
月収8万8000円以上(8万8000円×12カ月=105万6000円≒106万円)の人
-
※社会保険に加入条件が法律改正によって変更され、2024年10月以降は「厚生年金の被保険者(従業員)数101名以上」から「従業員数51名以上」になり、51名の従業員がいる勤務先で働く非正規雇用の人も社会保険に加入する必要があります
「社会保険(健康保険と厚生年金)を合わせた支払額」と、「国民健康保険と国民年金を合わせた支払額」を比較すると、「国民健康保険と国民年金」の合算額が高くなりますが、年収350万円以上になると「社会保険(健康保険と厚生年金)」の合算額のほうが高く(※)なります。
※扶養家族の有無や収入に応じて保険料の算出方法は異なるため、正確な情報を知りたい人は区役所などで確認しましょう
社会保険の基礎知識⑦国民健康保険には出産手当がない?
社会保険(健康保険)では、出産によって仕事を休まなくてはならないときに「出産手当」の制度によって一定額の給付を受けることができます。一方の国民健康保険には「出産手当」の制度がないため、出産のために仕事を休んでも手当の給付はありません。
● 社会保険(健康保険)加入者に・・・「出産手当」が支給される
● 国民健康保険の加入者・・・・・・・・・「出産手当」は支給されない
女性のフリーターの人は、妊娠・出産のときに費用面で慌てなくて済むよう、自分が社会保険(健康保険)と国民健康保険のどちらに加入しているかを理解するとともに、出産手当金の支給条件も確認しておきましょう。
【出産手当金の支給条件】
● 勤務先で健康保険に加入している
● 妊娠4カ月(85日)以降の出産である
● 出産のための休業をしていて、給与の支給がない

社会保険の基礎知識⑧ 国民健康保険には、傷病手当がない?
「傷病手当」とは、病気やけがによって仕事ができないときに一定金額の給付を受け取れる保障を指します。「出産手当」と同様に、社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いによって、「傷病手当」に該当する、該当しないの違いがあります。
● 社会保険(健康保険)加入者には「疾病手当」が支払われる
● 国民健康保険の加入者には「疾病手当」は支払われない
※ただし、国民健康保険加入者には「傷病手当金」がないが、コロナウイルス感染症など、特定疾病罹患時は、例外的に国民健康保険の加入者に「傷病手当」に該当する手当が支給されることもあります
また、社会保険における「傷病手当」の支給額と期間は、おおよその目安として「直近1年の給与(標準報酬月額)の日割の3分の2で、初めて支給を受けた日から通算で1年6カ月まで支給されます。
手当の対象は、会社員などで健康保険に加入している人が病気やケガの治療のために手術や入院をして仕事を4日以上連続して休んだときや、うつ病などの精神疾患と診断(医師の証明が必要)され、入院・手術などをしなくても働けない、仕事に就けない状態にある場合も支給の対象になります。

社会保険の基礎知識⑨ 国民健康保険に加入、または脱退する方法
厚生労働省のサイトでは、「国民健康保険の加入・脱退について」では、以下のように記されています。
—— 日本国内に住所を有する方であって、以下のいずれにも該当しない方は、国民健康保険の被保険者となります。
-
-
・ 他の医療保険(健康保険)に加入している人、その被扶養者
・ 生活保護を受けている人
・ 後期高齢者医療制度に加入している人
・ 短期滞在在留外国人の人 など
-
国民健康保険の被保険者となったとき、あるいは脱退するときは、14日以内に居住地の市町村の国民健康保険の窓口(国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合の窓口等)に行って、関係書類を提出する必要があります。
社会保険の基礎知識⑩ 社会保険の加入・脱退手続きの流れ
社会保険に加入することになったとは、その手続きは基本的に雇用主が行いますが、手続きに必要な以下の書類は自分で準備しましょう。
-
-
● 雇用保険被保険者証
(前の就業先で雇用保険に加入していた人は退職時に受け取ることができます)
● 年金手帳
● 基礎年金番号通知書
-
社会保険に加入する以前に国民健康保険に加入していた人は自分で各市町村の役所に行って、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。新しい仕事に就くタイミングは生活の変化によってなかなか時間を取りにくく、国民健康保険の脱退手続きを後まわしにしがちですが、手続きをしないと保険料を二重払いすることになってしまいますので注意しましょう。
同じように、退職する時も自身で社会保険から国民健康保険へ切り替える必要があります。退職時は、勤めていた会社に健康保険証を返納し、役所の窓口で国民健康保険へ切り替えを行います。
ここまで、社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いや、社会保険の加入条件などについて解説してきましたが、フリーターは非正規雇用なので社会保険には加入できない……という考え方が間違っていることを理解できましたでしょうか。

社会保険の基礎知識⑪ フリーターが健康保険に加入するメリット
では実際に、フリーターであるあなたがアルバイト先の社会保険に加入すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
「健康保険」に加入すると社会保険用の保険証(※)が発行され医療費が減額されます。また、健康保険は国民健康保険に対して、けが、病気以外にも出産・死亡までがカバーされるなど、適用範囲が広くなっている利点があります。
※2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は終了し、医療機関・薬局を利用する際はマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行する予定です
社会保険の基礎知識⑫ フリーターが厚生年金に加入するメリット
厚生年金保険は2種類ある年金保険のうちのひとつです。成人した国民全員が加入する「国民年金」に対し、会社員や公務員が加入するのが「厚生年金」で、条件を満たせばフリーターでも「厚生年金」に加入できます。厚生年金に加入することのメリットは、国民年金に上乗せして年金受給額が増えることにあります。
社会保険の基礎知識⑬フリーターが雇用保険に加入するメリット
「失業保険」とも呼ばれる「雇用保険」は、失業時に給付金を受け取れる保険を指し、最長11カ月にわたって給付金を受けとれるため、次の仕事が決まるまでの生活費に保険料を充てることができます。収入が安定しないフリーターにとっては、失業時に給付金を受け取れることは大きなメリットになります。
社会保険の基礎知識⑭ フリーターが労災保険に加入するメリット
「労災保険」は勤務中にケガなどを負った場合に給付金が支払われる保険を指し、職場の従業員数に関係なく、従業員を雇用している企業すべてに労災保険の加入が義務づけられています。万が一、業務中にけがをしたときは医療・治療費は会社が保険料を使って負担してくれるので、労働者は医療・治療費を支払う必要がありません。

社会保険の基礎知識⑮「103万円」「106万円「130万円」の壁とは?
「短時間労働者」であるフリーター、アルバイト、パートの人は、社会保険の基礎知識を理解できたら、自分が社会保険の加入対象者(被保険者)かどうかを知りたいですよね。
最近、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」というキーワードをよく目にするようになりましたが、「短時間労働者」であるフリーター、アルバイト、パートの人は、それぞれの「壁」の意味を理解することで、自分が社会保険に加入てきるか否かの目安をつけることができます。

社会保険の基礎知識⑯【103万円の壁】は“所得税の壁”
「103万円の壁」は“所得税の壁”です。
年収が103万円を超えると所得税がかかり始めます。ただし、扶養(※)する側(夫などの世帯主)は引き続き配偶者特別控除が利用できるため税金が増えることはありませんが、扶養者が勤務先から家族手当や配偶者手当を受け取っている場合は、「103万円の壁」を超えることで手当の対象から外れる可能性があります。
■ポイント!非正規雇用のフリーターが年収「103万円の壁」を超えたら、所得税を支払う義務が発生する
※扶養 = 社会保険における扶養とは、「未成年」「高齢」「失業している」などの理由で生計を立てられない人を家族や親族が援助することを指します
社会保険の基礎知識⑰【106万円の壁】は“社会保険の壁”
「106万円の壁」は“社会保険の壁”です。
以下の条件をすべて満たした場合、親や配偶者の扶養(※1)から外れ、勤め先の社会保険に入る必要があります。親や配偶者の扶養範囲内で働きたい人は「103万円の壁」に続いて「106万円の壁」を意識する必要性があります。
① 労働時間が週20時間以上(正社員の4分の3以上の時間と日数を勤務している)
② 月収が8万8000円以上(残業代・交通費をのぞく)で、年収が106万円以上ある
③ 雇用期間(見込み)が2カ月以上ある
④ 勤務先の従業員(厚生年金の被保険者)が101名以上(※2)
⑤ 学生ではない
■ポイント!非正規雇用のフリーターが年収「106万円の壁」を超えたら、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が発生する
※1 社会保険における扶養とは、「未成年」「高齢」「失業している」などの理由で生計を立てられない人を家族や親族が援助することを指します
※2社会保険に加入条件が法律改正によって変更され、2024年10月以降は「厚生年金の被保険者(従業員)数101名以上」から「従業員数51名以上」になり、51名の従業員がいる勤務先で働く非正規雇用の人も社会保険に加入する必要があります
社会保険の基礎知識⑱【130万円の壁】は“扶養の壁”
「130万円の壁」は社会保険の“扶養の壁”です。
年収が130万円(※1)を超えると、会社員や公務員等として働く親や配偶者の社会保険の扶養(※2)から外れるため、厚生年金や健康保険の社会保険に加入することになります。それができない場合は国民年金や国民健康保険に加入することになりますが、“扶養の壁”を超えることによって社会保険料の負担が増え、手取りが減ることになります。
■ポイント!非正規雇用のフリーターが年収「130万円の壁」を超えたら、親や配偶者の扶養から外れるため、勤務先の社会保険(健康保険や厚生年金)に加入する必要がある
※1 130万円 = 障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
※2 社会保険における扶養とは、「未成年」「高齢」「失業している」などの理由で生計を立てられない人を家族や親族が援助することを指します
月によって収入がバラバラ、扶養として親の社会保険に加入している、いくつかのバイトをかけもちしている、自分の年収がいくらかを把握していない……といった点に思い当たるフリーターの人は、自分が「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」を超えないかを、きちんと把握しておくことが大切です。
社会保険の基礎知識⑲フリーターも、年収によって様々な義務が生じる
ここまで解説してきたとおり、フリーターであっても年収によって所得税の支払い義務や社会保険加入義務が発生します。
■非正規雇用のフリーターが年収「103万円の壁」を超えたら、所得税を支払う義務が発生する
■非正規雇用のフリーターが年収「106万円の壁」を超えたら、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が発生する
■非正規雇用のフリーターが年収「130万円の壁」を超えたら、親や配偶者の扶養※から外れるため、勤務先の厚生年金や健康保険の社会保険に加入する必要がある
年収の違いによって、上記のように「所得税」「社会保険」「扶養(※)」の条件が異なるため、かけもちでバイトをしているフリーターが年収130万円を超えた際には、親の扶養から外れることになります。この場合、親が職場に届け出る、さらに本人も、市区町村の役所で所定の手続きをしなくてはなりません。
※社会保険における扶養とは、「未成年」「高齢」「失業している」などの理由で生計を立てられない人を家族や親族が援助することを指します
かけもちでバイトをしている、短期のバイトが多く、バイトの期間がバラバラというフリーターの人は、3つの「壁」を参考に、自分が年にいくら稼いでいるかを確認することが大切です。例えば、それまで前の年まで月の収入が数万円程度だったフリーターの人も、年収が130万円を超えると健康保険への加入義務が発生します。いざというときに「加入義務が生じていたことを知らなかった!」と慌てないよう、収入によって加入義務が発生することを把握しておきましょう。

社会保険の基礎知識⑳ 健康保険と年金未加入時に発生するリスク
健康保険と年金に加入していないと、どんなリスクが発生するのでしょうか。
【健康保険に加入していないときのリスク】
親の扶養から外れたことを知らないまま国民健康保険に加入手続きをしていないフリーターの人や、退職・転職時に健康保険の移動手続きをしていない人は、交通事故で骨折して長期入院することになったときや、虫歯の激痛で歯科医院に駆け込んだときも、治療費を全額自己負担することになります。
一例として、不慮のケガで治療費が100万円かかっても、保険に加入していれば高額療養費制度によって支払額が約9万円に減額されますが、保険未加入の人は100万円全額を自己負担しなくてはなリません。健康保険に加入していないことで発生するリスクについても理解しておきましょう。
-
-
● 病院の治療費等が全額負担になる
● 重い病気にかかり、手術や長期入院しても高額療養費が使えない
● 加入資格発生日にさかのぼって最長2年分の保険料を納めることになる
● 保険料に加算された延滞金を支払わなくなてはならない
-
【年金未加入者に発生するリスク】
年金保険の加入は日本国民の義務であるため、社会保険の厚生年金保険に加入していた被保険者が退職して、親や配偶者が加入する健康保険の被扶養者となった場合や、フリーランスを含む自営業者(個人事業主)になるときは、国民年金への切り替え手続きを行う必要があります。
なかには、「市区町村の役所に行くのが面倒」「老後に年金をもらえるかどうかわからないので国民年金に加入したくない」「将来もらえる年金が少ないなら、保険料を納めるのはばからしい」「保険料を払わず、自分で積み立てている」といった理由で年金保険料を支払わない状態を放置したり、自己判断で加入をやめている人には次のようなリスクが生じえます。
-
-
● 年金保険料の未納が続くと、財産を差し押さえられることがある
● 未納期間が長くなるほど、将来の年金受給額が減る
● 国民年金保険料を払わない場合、失うのは将来の年金だけではなく、「遺族年金」や「障害年金」も受け取れなくなるリスクが発生する
● 60歳を超えたときに後悔して役所に頼み込んでも、年金は支給されない
-

—— 健康保険や年金の手続きは人生のなかで何度もあることではないので、きちんと手続きの流れを把握している人は少ないといえます。でも、「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」という理由でもらえるはずの年金がもらえなくなったら、いやですよね。そうならないために、退職や結婚などのライフイベントの際に、日本年金機構のHP「会社を退職したときの国民年金の手続き」をはじめとする公的サイトで、自分がすべき手続きを確認して、モレがないようにしてくださいね。
さらに、「自分はめっちゃ健康だし、病気とは無縁なので健康保険は必要ない」と若さや体力を過信している人も、不慮の事故に見舞われて慌てて治療費にかかった大金を払う羽目に陥らないよう、保険に加入して安心感を得ておきましょう。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験者歓迎の工場ワークを多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。製造業やモノづくりの現場で働きたいニートの方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
