食事補助は工場ワーカーにも人気の福利厚生!気になる情報を紹介!
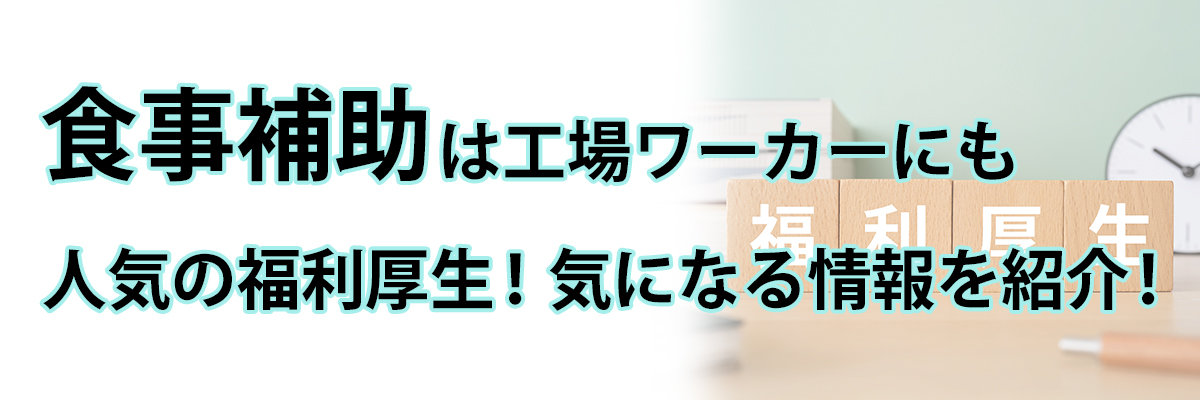
2023/8/2 更新
福利厚生における食事補助とは?

食事補助とは、企業が従業員の食事費用を負担する福利厚生のひとつです。
食事補助は法定外福利厚生にあたり、必ずしも法律で提供が義務づけられているわけではありません。とはいえ、食事補助は従業員からのニーズや注目度が高く、企業にとっても多くのメリットがあるため、近年は“食”の福利厚生として積極的に導入する企業が増えています。
食事補助の提供方法としては、就業時間中に昼食を補助するケースが一般的ですが、24時間稼働する工場やサービス業などの企業では、朝食や夕食まで補助する場合もあります。また、社内食堂の設置や宅配弁当の利用など、食事補助の提供方法も企業によってさまざまです。
食事補助の提供方法はさまざま
では、食事補助の提供方法には、主にどのようなものがあるのでしょうか。以下、工場などでも導入されている5つの方法を紹介しましょう。
従業員食堂の設置

社内や工場内に休憩スペースとなる食堂を設け、厨房で調理した料理を相場より安く提供する方法です。一般企業の食堂は昼食の提供がメインとなりますが、朝勤や夕勤のある工場の食堂では、朝食や夕食のメニューを用意しているところもあります。
従業員食堂は、栄養バランスやカロリーに配慮したメニュー・献立を計画できるため、従業員の健康管理にも役立ちます。また、できたての温かい食事がすぐに食べられることも、従業員食堂ならではの大きな魅力といえるでしょう。
※工場食堂に関する詳しい情報は、こちらの記事もチェック!
工場ワーカーの胃袋を支える「工場食堂」の魅力とメリットを徹底リポート! | 工場・製造業の求人・お仕事・派遣なら日総工産 (717450.net)
宅配弁当サービス

外部の弁当業者に電話やネットで注文し、会社まで弁当や軽食などを届けてもらうサービスです。従業員食堂のある企業や工場でも、深夜の時間帯は食堂がクローズするため、深夜勤務の従業員向けに宅配弁当サービスを利用する職場も多いようです。
設置型の食事サービス

社内に自販のコンビニや食品自販機などを設置するサービスです。24時間いつでも利用可能なので、従業員は好きなときに好きな商品を購入でき、残業や深夜勤務などの際にも便利です。
食事チケットの支給

企業がサービス提供会社から購入したチケットを、従業員に支給する食事補助です。支給されたチケットは、全国の提携コンビニや飲食店で会計時に利用できます。最近は電子チケットのサービスもあり、出張や社外に出ている従業員も、スマートフォンがあればいつでも利用できて便利です。
現金や食事手当での支給

食事代として現金や食事手当などを支給する方法です。名目上は食事補助であっても、受け取った現金や手当は自由に使えるため、従業員には喜ばれるでしょう。とはいえ、食事以外の用途に使ったり、貯金に回したりする従業員もいるので、本来の目的から外れてしまうのが難点です。また、支給額によっては課税対象(詳しくは後章で解説)となる場合もあります。
企業が食事補助を導入するメリット
食事代がセーブできる食事補助は、従業員にとって大きな魅力・メリットとなりますが、企業にとっても導入するメリットが多くあります。以下、企業側から見た食事補助のメリットを見ていきましょう。
従業員の満足度向上につながる

企業が食事費用の一部を負担することで、給与以外の面からも従業員を経済的にサポートすることができます。経済的な支援は従業員からの支持が得やすく、食事面も毎日の生活や労働に欠かせない重要な要素となるため、従業員の満足度向上につながりやすくなるのです。また、従業員の満足度が向上することで、個々のモチベーションアップや離職抑制などの効果も期待できます。
従業員の健康促進につながる

日々忙しく仕事をしていると、食事を簡単に済ませることが多くなりがちです。また、食事代を節約するために、毎日コンビニのパンやおにぎりだけでしのいだり、食事を抜いたりする人もいるようです。当然ながら、食生活が乱れて栄養が偏ってしまうと、仕事のパフォーマンスや集中力が低下し、心身の健康にも支障が出やすくなります。
よって、福利厚生で栄養面に配慮したメニューを提供したり、食事補助で経済的に支援したりすることで、従業員が健康を意識した食事を採る機会が増え、より生き生きと働けるようになるでしょう。
社内コミュニケーションが活性化する

福利厚生として社内食堂を設置すれば、さまざまな部署の従業員同士で食事をする機会が増え、社内コミュニケーションの活性化につながります。部署や役職の垣根を越えて、普段顔を合わせない人とも接することで、社内の風通しが良くなったり、新たな仕事のアイデアが生まれたりするかもしれません。
求職者へのアピールポイントとなる

食事補助は人気の高い福利厚生のひとつなので、積極的に導入することで求職者へのアピール材料にもなります。もちろん、それだけで応募者が急増するわけではありませんが、日々の食をサポートする実用的な福利厚生があると、「従業員のニーズをしっかり汲み取り、働く人を大切にしている優良企業」と認識されやすくなるでしょう。
食事補助の支給額の相場は?
非課税にするためには金額に上限がある

食事補助は企業の裁量で導入できるため、その支給額について上限はありません
ただし、食事補助を福利厚生として法的に計上する(非課税にする)ためには、支給額に以下のような要件が設けられています。
-
-
《食事補助を非課税対象にするための要件》
●企業が負担する補助金額が月額3500円(税別)以下であること
●従業員の負担が50%以上であること
-
非課税であれば企業にとっても経済的メリットがあるため、多くの企業が採用する一般的な支給相場としては月額3500円程度、1食あたり150円程度となっているようです。
もちろん、非課税にならなくても良ければ金額に上限はないため、従業員が満足する額を支給することが可能です。とくに、体力を消耗する作業が多い工場の従業員に対しては、食事面の充実を図ることが求められるため、上限以上の額を支給するメーカーも少なくありません。なかには、従業員食堂や寮の食事が無料になったり、月額1万円以上の食事手当を支給したりするメーカーもあります。
現金支給の場合は給与課税される?

また、食事補助として現金を支給する場合、上記2つの要件を満たしていても、補助する全額が給与とみなされ課税対象となります。
ただし、現金支給には例外があり、深夜勤務などで夜食の支給ができない場合は、1食あたり300円(税抜)まで非課税となります。さらに、まかないなどを従業員に無料で提供した場合も給与として課税されますが、残業または宿日直勤務する場合に支給する食事は、無料で提供しても非課税となります。
※参考資料/国税庁タックスアンサー「食事を支給したとき」
No.2594 食事を支給したとき|国税庁 (nta.go.jp)
まとめ
今回は、食事手当に関する豆知識や、気になる情報をまとめてお届けしました。
ご紹介したように、食事補助は従業員の経済的負担をサポートする人気の福利厚生です。とくに製造業の多くの企業では、より充実した食事補助のサービスや手厚い支給体制を積極的に導入し、工場で働く従業員の“食と健康”を全力で支援しています。工場の仕事を検討する際や、求人に応募する際には、ぜひ食事補助の福利厚生にも注目してみてくださいね!
