工場って残業が多い?残業時間はどれくらい?残業が少ない働き方は?
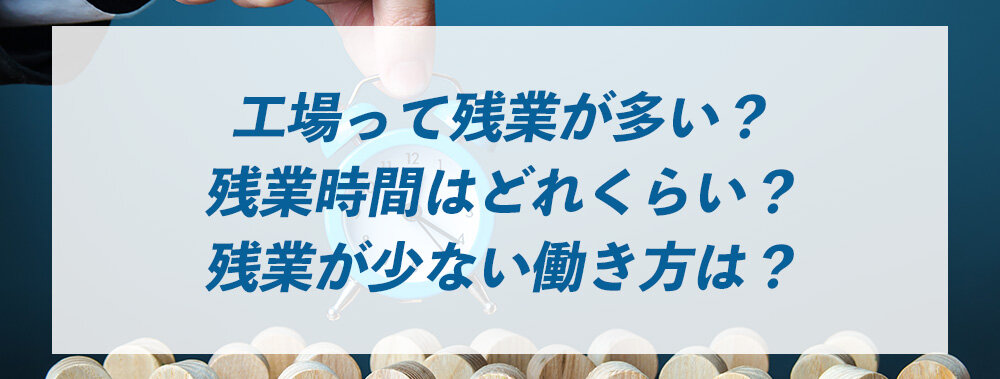
2024/9/17 更新
猛烈社員が推奨されたバブル期に生じた様々な問題
バブル全盛の1980年代後半……。テレビから頻繁に流れていたのは、「24時間戦えますか!」をキャッチフレーズにした栄養ドリンク剤のテレビCMです。一斉を風靡したそのCMでは、世界を舞台に猛烈に働く企業戦士が映し出され、「毎日終電帰り」や「深夜のタクシー帰り」の“午前様”と呼ばれる男性たちが睡眠時間を削って、家庭を犠牲にして働く当時の日本の姿が描かれていました。
「男だったら寝る間を惜しんで24時間戦え!」などといま言ったら「パワハラ」「ブラック」「ジェンダー・ハラスメント」と一斉攻撃を受けそうですが、当時は残業が月に100時間を超えることも珍しくなく、行き過ぎた労働実態はやがて、様々な問題を浮き彫りにします。
-
-
・過剰な残業時間と重い責任をかすことで社会問題化した“過労死”
・毎日終電帰りなど残業が常態化した職場での“作業効率・生産性の低下”
・「自分さえよければいい」という風潮が蔓延し、約80%が“早期離職”する事態も
・一従業員に業務が集中することで、その重責と激務から“精神疾患”を発症
・長時間労働、心理的負荷(ストレス)、パワハラによって“過労自殺”が増加
・働き手が家事や育児に参加せず、配偶者に任せっきりすることでの“家庭不和”
-

労働基準法改正で、残業の上限規制は45時間/月に
“男の優劣は甲斐性で決まる”“働かない者はダメな人”“収入の半分以上が残業代”という風潮がまかり通っていた1970年代〜1980年代。経済的豊かさを追い求める陰で様々な問題が顕在化したことで、国(厚生労働省)は過労死の救済・予防の取り組みや職場のメンタルヘルスケアをはじめとする労働環境の改善に向けて動き出します。
最近よく耳にする「働き方改革」も1970年代〜1980年代に始まった労働環境改善の延長線上の取り組みのひとつですが、2019年4月に施工された労働基準法の改正では、「時間外労働の上限規制関係」について以下のルール変更がなされました。

時間外労働が減る一方で、新たな問題が発生する「2024年問題」
労働基準法の改正により、日本人や企業の働き方に対する意識も大きく変化しようとしていますが、これまで残業が多い傾向にあった工場や製造現場でも、最近は「精神的負荷や過重労働を原因とする精神・肉体的リスク」や「大型設備を取り扱う職場での、労働者のモチベーション低下に伴う安全性へのリスク」など、労働者の心身状態や環境を考慮し、残業時間が増えない工夫を行うようになっています。
その一方、ニュースなどで「2024年問題」というキーワードをよく目にするようになりました。労働基準法の改正は、「物流・運送業界」「建設業界」「医療業界」等の一部の事業・業種で2024年4月1日まで適用が猶予されていました。
〈拘束時間が長く、長時間労働が常態化する物流・運送業界〉
トラック、バス、タクシー、物流・運送のドライバーは、時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間とし、特別な事情があった場合は年960時間以内が上限となる
〈人手不足や短納期で、長時間労働が常態化する建設業界〉
災害復旧や復興事業に従事する場合を除き、他の業界と同様に月45時間、年360時間以内の原則が適用され、特別な事情があった場合は年720時間以内が上限となる
〈医師の働き方改革が難航する医療業界〉
休日労働も含めて上限は年960時間、地域の医療提供体制を確保するため、やむをえず上限を超える場合、医師の労働時間は年1860時間となる
そして、長時間労働が常態化していた特定業界の労働時間是正に伴って、「さらなる人手不足」「物流の停滞」「路線バスの減便」「地域医療への支障」「残業代が減ることで手取り収入の減少」「人件費増加による利益や売上の減少」など、様々な新たな問題が発生しているのです。

業種別の残業時間と、工場の残業時間を比較
「24時間戦っていた時代」の残業時間が100時間を超えることも珍しいことではなかった一方、「人生100年時代」へと変化した現在の平均的な残業時間は、どれくらいに減ったのでしょうか。
厚生労働省が2022(令和3)年2月に公表した「毎月勤労統計調査」によると、残業時間が20時間を超える業種もあるなか、工場勤務を含む製造業の残業時間は他の業種よりやや多い「13.3時間」になっています。
-
-
【業界別 残業時間が長い順から】
・運輸業、郵便業 20.8時間
・情報通信業 15.4時間
・建設業 14.3時間
・電気、ガス業 14.2時間
・学術研究等 13.9時間
・製造業(工場など) 13.3時間
・鉱業、採石業等 12.4時間
・不動産・物品賃貸業 11.2時間
・金融業、保険業 10.6時間
-
上の「業界別 残業時間の平均」を見ると、製造業(工場や製造現場)の残業時間13.3時間は、他業種と比較して決して大幅に多いわけではないことがわかります。
シフト制を敷く工場でよくある「固定残業」とは?
産業別の残業時間の平均値がわかったところで、工場や製造現場でよく用いられている「固定残業」についても触れておきましょう。日勤と夜勤の交代制シフト制を敷く工場では、下のような「固定残業」をあらかじめ勤務時間に含んでいることがあります。
-
-
・昼勤…… 9時〜21時 (9時〜18時は通常勤務/18時〜21時は固定残業)
・夜勤…… 21時〜翌9時 (21時〜翌6時は通常勤務/翌6時〜9時は固定残業)
-
このようなシフトが敷かれた工場では、「勤務時間に固定の残業分が含まれている」ことから基本的に残業は発生しません。※ただし、業務を引き継ぐ交替要員が急病にかかった、事故に遭ったなどの突発的なアクシデントが発生した場合は、残業が発生することもあります。

最近は多くの工場で、残業に対してさまざまな工夫が!
取り扱う製品や雇用形態によっても異なりますが、工場での残業時間は、平均的な数字として1日あたり1〜2時間程度の残業があるとされ、主に以下の3つの要因から残業は発生するとされています。
① 生産ラインのトラブルや機械の故障に起因する残業
機械の不調や予期せぬ問題が生じると、その解決のため残業が必要になることがある
② 工場では、生産計画の変更や急な受注増、繁忙期に起因する残業
③ 人手不足やスキル不足による作業遅延やトラブル、そのリカバリーに起因する残業
また、工場ごとに残業の「ある・なし」「多い・少ない」は様々ですが、最近は毎週水曜日などの特定の曜日を「NO 残業デー」に設定し、全員が定時に帰社することを推進しているところも増えています。
残業時間が気になる、なるべく残業したくない……という人は、面接時に月にどれくらい残業をするのか、1年のうちどの時期に残業が多いか……などを担当者に質問しておくと、安心して仕事に臨むことができることでしょう。

新人さん抱きがちな、残業に対する素朴なギモン
工場で新しく仕事を始める人にとっては、残業時間がどのくらいなのかはとても気になるポイントですが、入社してすぐに「今日も残業」「明日も残業」なんてことはめったにありません。特に、上司から何の説明もないまま強制的に残業を指示されることや、仕事を覚える前に連日残業しなくてはならない……ということは、ほぼないと考えてよいでしょう。
どの工場でも、新人さんにはまず仕事を覚えてもらい、職場の環境に慣れてもらうことからスタートします。そのうえで残業を少しずつお願いするようになる……というのが現実的な流れですし、仕事に慣れた頃には、先輩や同僚と信頼関係も育まれているため、「交替のYさんの出勤が遅れている」と上司から連絡を受けた際は、「Yさんが来るまで自分が頑張ろう」という協調意識も自然と芽生えているはず。よって、重い“やらされ感”を背負ったまま渋々残業をすることは、ほとんどないので安心してくださいね。
残業が少ない工場を探す際の、3つのポイント
実践的な方法として、工場で働きたいけれどなるべく残業をしたくないという人は、以下の3つのポイントをおさえて工場探しをスタートさせてみましょう。
ポイント①/3交替制などシフトが敷かれた工場で働く
例えば食品メーカーの工場などでは、節分、ひなまつり、クリスマス、お正月などの季節商品の生産が立て込む時期は業務量が増大するため、普段より多めに残業が発生することもありますが、交替制が敷かれた工場では勤務時間(シフト)があらかじめ決まっているため、残業が少ない傾向にあります。
ポイント②/一年を通して、残業が少ない企業(工場)を選ぶ
繁忙期が年に数度ある工場でも、残業が増えないよう「シフトを調整する」「人員を増やす」「業務を効率化する」など様々な工夫を凝らすところが増えています。特に、一年を通して残業が少ない企業(メーカー)ほど、労働時間の適正管理や労働環境の充実や、労働者の健康と働きやすさを重視している裏づけになるため、既存社員の残業時間が少ない会社ほど、残業をする確率はグッと減ります。
ポイント③/工場の事務職に応募する
工場内の事務職は残業が少ない傾向にあるため、残業をなるべくしたくない人は、応募段階から事務、経理、あるいは生産管理や労務管理などの業務に従事したい希望を伝えるようにしましょう。ただし、管理部門の事務職に配属されたとしても、帳票整理などの業務が立て込む25日〜月末に残業が発生するなど、月のうち数日は忙しくなることをあらかじめ織り込んでおくと、「こんなはずじゃなかった!」というミスマッチがなくなります。
残業が重なると、心身の健康と安全の維持が危うくなる
工場や製造現場では、忙しい時期や急な発注などが重なった場合は、普段より多めの残業をお願いされることもありますが、現在ほとんどの企業(メーカー)では、法令を遵守した労務管理がなされています。とはいえ、働く側も自分の働き方が法律に違反していないかを、自ら気を配ることも大切です。
【法律違反に該当する働き方】
✕1月〜11月まで月の時間外労働(残業時間)は10時間以内だったが、
繁忙期の12月だけ、残業時間が100時間を超えた
(単月であっても、時間外労働+休日労働の合計が100時間以上は法律違反)
✕1年間のうち、時間外労働(残業時間)が45時間を超えた月が7回あった
(月45時間を超えることができるのは年6回以内。7回以上は法律違反)
✕5月85時間、6月70時間、7月90時間と、3カ月連続で残業がかさみ、
3カ月間の時間外労働(残業時間)の平均時間が80時間を超えた
(3か月平均で80時間を超える場合は法律違反)

—— 残業が多いと精神的ストレスや肉体的疲労に限らず、事故やケガの発生率もアップします。法律では「法定労働時間」について、「 1日8時間・1週40時間以内を原則とする」と定められていて、「休日」についても、「毎週少なくとも1回与えることが義務づける」ことが定められているので、心身の健康と業務の安全を維持するために、どのようなケースが法律違反に該当するのか、ぜひ覚えておきましょう。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験者歓迎の工場ワークを多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。製造業やモノづくりの現場で働きたいニートの方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
