“バリ”の基礎から、“バリ取り”自動化の実例をご紹介!
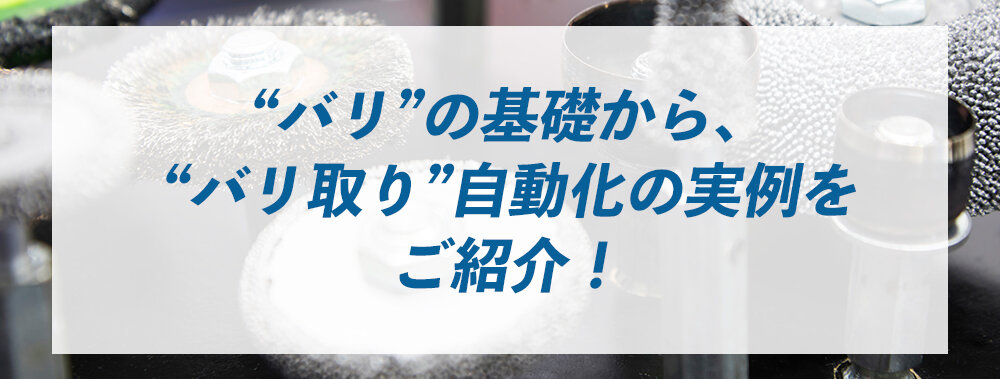
2024/1/25 更新
“バリ”は私たちの暮らしの身近なところに存在する?
“バリ”というと、木材・機械・金属などを取り扱う加工メーカーでの専門用語と思われがちですが、実は私たちの身近な場面でも“バリ”は存在し、どの家庭にもある包丁の“切れ味”にも“バリ”は重要な役割を果たしています。
包丁を研ぐとき、刃先を砥石にあてて何度かストロークするうち、研いでいる面と反対側の刃先に「まくれ」「かえり」と呼ばれる“バリ”が生成されます。包丁研ぎの上級者は作業の途中で何度も親指の腹や爪を刃先にそわせますが、これはわずかながらも確かに感じられる“バリ”の状態を確認するためです。
片面の研ぎが終わったら、次は反対側の刃先の研ぎに取りかかりますが、ここでも切れ味”の目安になる“バリ”が生成されるまで研ぎあげます。次はいよいよ最後の仕上げです。刃先を新聞紙や布地に左右に擦りつけ、刃先を指の腹でスーッと撫でたときに引っかかりがなければ、“バリ”は除去されているため研ぎは完了です。これで驚くほど切れ味は上がっていることでしょう。
日本語の“切れ味”は、その言葉のとおり、包丁の“切れ”と“味”が深くかかわっていることを意味します。例えば、刺し身を作るときに切れ味の落ちた丸い刃先で身を切ると身に余分な力が加わり、苦みや酸味が増すことで味が落ちます。逆に、刃先がスッと吸い込まれるように身に入る包丁で身を切ると、余分な力が加わらないぶん旨味や甘みが増すとされています。

“バリ取り”をしないまま、製品化した際に発生するリスク
包丁と同じく日曜大工(DIY)でも“刃先”が完成品の仕上がりに大きく関係します。片手ノコ(片手で操作できるのこぎり)で一枚の板をカットしたとき、切断面に“切りバリ”と呼ばれるギザギザができます。しっかり板を押さえ、切れのよいノコを使用すれば、板との摩擦が少なくなるため“切りバリ”は少ない状態でカットできます。このことからDIY上級者が木材を切断すると“切りバリ”は少なくなります。
しかし、ノコに不慣れな初心者は、ノコを挽くときに刃先と板が“踊る”ことで“切りバリ”が多くなるため、“切りバリ”を見れば上級者か初心者かが一目瞭然といわれています。さらに、“切りバリ”をしっかり除去せず作業を進めると、作業中に指が“切りバリ”に引っかかってケガをする恐れがあるうえ、完成時の見栄えも悪くなります。
同様に機械・金属・木材等を加工する現場でも、“バリ取り”(研磨)工程は非常に重要な役割を担います。ミリ単位、コンマ単位のわずかな“バリ”であっても、それを放置したまま製品化すると製品の通電に支障をおよぼし、ユーザ(消費者)が火災に巻き込まれる危険もあります。さらには、わずかな“バリ”が原因で企業の信用問題や補償問題にも発展しかねません。

“バリ取り”をしないまま、製品化した際に発生するリスク
ではここで、“バリ”をそのままにして作業を進めた場合のリスクを整理してみましょう。
-
-
●作業工程で従業員がケガをするリスク
●製品化後に、ユーザ(消費者)がケガをするリスク
●製品化後の動作不良や故障発生のリスク
●製品寿命が短くなるリスク
●不良製品が流通し、製造者の信用低下につながるリスク
●加工精度の低下や、火災の発生リスク
●加工外観が悪いなどの製品の不良リスク
●消耗品の経年劣化による測定精度の低下リスク など
-
近年はデジタル機器や高機能製品の多機能化、小型化が進んでいますが、微細な部品を加工する際に“バリ”を除去しないと、ミリ単位やカンマ単価で構成されたICチップの受信感度劣化(動作不良や機能低下)やデジタルノイズの発生要因になる可能性が大きくなります。そうしたことから“バリ取り”は重要な工程に位置づけられています。

“バリ取り”は、太古の時代にも行われていた?
英語の「burr」が語源にもつ“バリ”は、樹脂や金属を加工する際に発生する意図しない形状の不要な突起を指します。日本では昭和中期まで「カエリ」と呼ばれていて、町工場の現場では“カエリ取り”を行うシーンがあちこちでられていました。そんななか、1973年に米国で「Burr Technology」という用語が使われ始たことをきっかけに、「カエリ」が「バリ」へと変化したと伝えられています。
ものづくりなどの現場で重要な役割をもつ“バリ取り”は、太古の時代から継承されてきた作業であり、石を削って斧や刃を作る際にも切れ味を上げるため刃先の研磨が行われていたでしょうし、しなりのよい枝を使って弓矢を作るときにもきっと“バリ取り”は行われたはずです。
悠久の時間のなかで人の手によって行われてきた“バリ取り”も、時代の変化とともにオートメーション化が進み、近年では製造現場での“バリ取り”に、ロボットやAI(人工知能)などの先端技術が活用されるようになっています。さらに最新の“バリ取り”は、目視で確認できない素粒子レベルでの超微細バリ取りや表面研磨、ナノレベルの膜厚除去などへと進化を遂げているのです。
“バリ取り”のオートメーション化はハードルが高い?
最近はさまざまな機械・金属・木材などの加工現場や、バリ取り専業メーカー、ものづくりの現場といった幅広い領域で“バリ取り(Burr Technology)”のオートメーション化が急ピッチで進められています。ただし、“バリ取り”のオートメーション化をカスタマイズする場合、コストや時間がかかるデメリットがあります。一方で、コストや時間に余力がないなかで中小加工メーカーがオートメーション化を採用している背景には、以下のような切実な事情もあるようです。
-
-
●手作業での高度な“バリ取り”に従事する人材が不足している
●熟練の“バリ取り”技術をもつ職人の人件費が経営を圧迫していた
●少子化で働き手の数が少なくなり、欲しい人材が採用できない
●現役技術者が高齢化し、加工や“バリ取り”の技術継承が進んでいない
●少ない人手で技術を維持・継承しなければ競合との競争に勝てない
●熟練技術をオートメーション化するには、感覚値を数値に置き換える必要がある
●技術者が特定領域に専念できるよう、ルーチンワークを自動化させる必要がある
●競争力を高めるため、高難度の加工製品を量産する必要がある
●希少部品の“バリ取り”では、品質のバラツキが発生していた
-
機械・金属・木材等の加工現場における“バリ取り”工程では、こうしたさまざまな課題を受けて“バリ取り”や研磨作業のロボット化を推し進めています。なかには“バリ取り”の品質維持と管理、省人化を同時に実現させるため、カメラやAIを用いた三次元測定を導入する現場も、最近は増えてきています。

“バリ”は、作業工程によって形状も大きさも異なる
とはいえ“バリ取り”のオートメーション化を採り入れていない(採り入れられない)現場が多いのも事実です。その理由はさまざまでますが、大きな要因に「素材や加工法、生産方法によって“バリ”の形や大きさはまったく異なる」ことがあげられます。
そのほかにも、「切削加工やせん断加工のエッジ部分に発生する“バリ”は、金属加工物とつながっているため衝撃や振動程度では容易に除去できない」といった点も多くの現場での共通認識になっています。
つまり、“バリ”の形状や特性に合わせて的確に“バリ取り”をする作業は、依然として人知や人の感覚値に頼る部分が多く、その奥深い世界をロボットやAIに代替することは現状の技術では難度が高い点が、オートメーション化を阻む要因にもなっているのです。人知や人の感性に頼ることが多い“バリ取り”にはいくつかの種類がありますが、まずは「作業工程別の“バリ”の違い」を見ていきましょう。
-
-
●作業工程別の“バリ”の違い
- 〈ポアソンバリ〉
- 切削の開始時・加工中に発生するバリ
- 〈エントランスバリ〉
- 切削開始時に発生するポアソンバリ
- 〈サイドバリ〉
- 加工品の側面に発生するポアソンバリ
- 〈ロールオーバーバリ〉
- 切削終了時に発生するバリ
-

加工、素材がさまざまだからこそ、“バリ取り”は難しい
次は、「加工、素材ごとの“バリ”」です。素材や材料になんらかのエネルギーを加えて部品を製造(加工)する際に“バリ”は生成されますが、加工法によって“バリ”の名称も異なります。
-
-
●加工、素材ごとの“バリ”
- 〈切削バリ、研削バリ〉
- 旋削、研削、ドリル等を用いた機械加工時に発生するバリ
- 〈せん断バリ〉
- 剪断、プレスなどの塑性加工時に発生するバリ
- 〈鋳バリ、鋳造バリ〉
- 鋳造成形時に発生するバリ
- 〈プラスチックバリ、ゴムバリ〉
- 樹脂成形時に発生するバリ
- 〈PLバリ〉
- 鋳造や樹脂の射出成型加工に発生するバリ
- 〈溶断バリ〉
- 放電、レーザ、溶断加工時に発生するバリ
- 〈はんだバリ〉
- はんだ付け時に発生するバリ
- 〈はんだバリ〉
- めっき、塗装、コーティング、金属溶射時に発生するバリ
- 〈鍛造バリ〉
- 鍛造時や転造時に発生するバリ
-
最後にある〈鍛造バリ〉は、金型に金属素材を入れ、プレス機などで叩く・押し潰すなどの高圧力を加え、目的の形状へ成形させる技術を指します。金属加工時に生成される“バリ”は、一般的に有害 = 不要なものとされますが、鍛造技術ではあえて〈鍛造バリ〉を生成させています。
-
-
〈鍛造バリ〉を生成させる理由
① 金型で加工する金属素材は薄いことが多く、金型の隅々まで隙間なく金属素材を流し込む必要がある
② 金型と金型が接触しないよう、金属素材がクッション的な役割を果たす
③ 金型の接触面に金属素材を広く浸透させることで、高圧力(負荷)がかかる金型の劣化を防ぐ
-
“バリ取り”オートメーション化のメリットとデメリット
ここでは、“バリ取りを”オートメーション化するに際のメリットとデメリットを確認しましょう。
“バリ取り”オートメーション化のメリット
-
-
・人員を最適化できることで得られる生産性向上、品質向上オートメーション化により、単純作業や過酷な労働環境を改善
・人件費等、生産現場を稼働する際にかかっていた固定費削減
・顧客からの注文に柔軟に対応できることで得られる売上拡大
・高難度技術のオートメーション化で、技術の継承が容易に
-
“バリ取り”オートメーション化のデメリット
-
-
・カスタマイズ性の高いオートメーション化はコストが高い
・高難度、複雑、特殊材料等は、技術的制約が見込まれる
・導入後、システム障害、災害等により、ロボットが故障するリスクも
・自動化された生産現場や設備を管理する専用技術者の育成
・リスク発生時に迅速に対応できる人員の教育・トレーニングの実施
-

“バリ取り”のオートメーション化を支えるエンジニアたち
“バリ取り”の最前線では“バリ”検出カメラやAI、“バリ取り”専用ロボット、センサでナノ単位の“バリ”を検出する技術、特殊材料を用いた高速回転する“バリ取り”ブラシ、機械学習をする“バリ取り”画像認識技術など、さまざまな最新技術が用いられています。
これらの先端技術を支え、生産現場それぞれのニーズに見合った“バリ取り”のカスタマイズを立案・開発・運営に携わっているのが多様な先端技術を有したエンジニアたちです。
人手不足、競争力・生産性の向上といった観点からも、“今後は“バリ取り”や研磨技術のさらなる高度化が期待されていて、生産・加工現場の無人化を実現するメーカーが増えることも予測されています。
さまざまな産業や生産現場の最前線で“バリ取り”やの自動化が平準的に導入されれば、その陰で効率的で高品質な製品製造に貢献する技術者へのニーズは高まることは必至であるため、イレギュラーを想定しながら要件定義を行う制御ソフトウェアエンジニアや、工作機械や工具を自動化させるソフトウェアエンジニア、ロボット、AI技術を用いた機械系エンジニアなどの活躍が期待されています。このため、画像認識、センサ、IoT、3次元データ分析、AI、ロボット、AGV(無人搬送車)、特殊素材などの先端領域に携わるエンジニアには“バリ取り”に対する知見やスキルも求められる機会が増えることになるでしょう。
