日雇い派遣とは?禁止理由や例外を詳しく解説
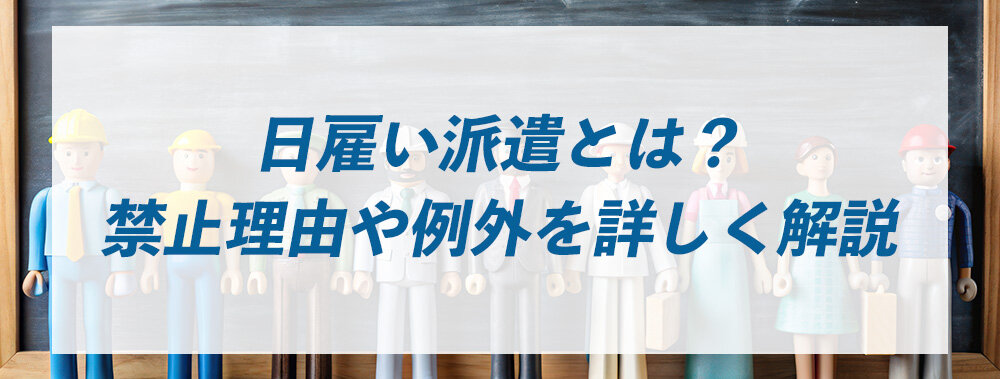
2025/1/22 更新
今回の工場求人ナビでは、
-
-
●日雇い派遣が原則禁止になっている理由
●日雇い派遣OKの例外業務とは
●日雇い派遣のメリット・デメリット
-
などについて詳しく解説します。
日雇い派遣とは

日雇い派遣とは、派遣会社が労働者を雇用し、短期間(1日単位または30日以内の期間)で派遣先企業に派遣する雇用形態のことです。主に人手不足を補うために、イベント会場の設営、倉庫内作業、販売促進キャンペーンなど、短期間の業務で活用されることが多いです。
労働者派遣には一般派遣(登録型)と常用型派遣がありますが、日雇い派遣は一般派遣の一形態とされています。この働き方の場合、労働者は派遣会社に雇用され、派遣先企業の指揮命令を受けて業務を行います。派遣会社と派遣先企業は、労働者の労働条件や賃金などを調整する契約を結んでいます。
日雇い派遣の特徴は以下のとおりです。
●期間が短い契約
労働契約が1日ごとに更新される形式で、継続的な雇用契約ではありません。例えば、イベントスタッフとして1日のみ働き、その後は契約が終了する形です。
●派遣会社との雇用契約
労働者は派遣会社に雇用されているため、給与の支払いや社会保険の管理は派遣会社が行います。しかし、就業先での業務内容や指示は派遣先企業が行います。
●多様な業界での活用
イベント運営、倉庫内軽作業、キャンペーンスタッフ、製造業の補助作業など、短期間で人手が必要なさまざまな分野で活用されてきました。
日雇い派遣が普及した背景としては、企業側にとって「必要なときにだけ人員を確保できる」手段として重宝され、労働者にとっても短期間で収入を得られる柔軟な働き方として需要がありました。とくにフリーターや学生など、短期間の労働を希望する人々が利用するケースが多かったのです。
日雇い派遣の禁止理由

日雇い派遣は、一時的な労働力を柔軟に確保できる手段として普及していましたが、2012年に労働者派遣法の改正により原則禁止されました。その背景には、労働者の保護や雇用環境の改善が求められたことがあります。禁止に至った具体的な理由を解説します。
●雇用の不安定化
日雇い派遣は1日単位の契約が主流で、労働者は次の日に仕事があるかどうかが保証されません。この不安定な雇用形態は、労働者の生活の基盤を脅かし、経済的な安定を得にくい状況を生み出していました。安定した収入を確保できず、社会保険への加入も限定されることから、将来の生活設計にも悪影響を与えるとされました。
●低賃金と過酷な労働条件
日雇い派遣は単発的な仕事のため、長時間労働や過酷な労働環境に置かれることがありました。また、短期間の仕事に対して十分な賃金を得られないケースも多く、労働者が生活を支えるだけの収入を確保できない問題が指摘されていました。
●安全衛生管理の不備
短期間で異なる職場に派遣される日雇い労働者には、業務内容や作業環境についての十分な教育や訓練が行われにくい傾向に。その結果、労働災害や事故のリスクが高まることが懸念されました。労働者が適切な指導を受けないまま現場に投入される事例も少なくありませんでした。
●企業による不適切な利用
企業側は、日雇い派遣を人件費削減の手段として利用することがありました。正社員を雇用せず、必要なときだけ労働力を確保することで人件費を抑える目的で乱用されるケースが増え、これが労働市場全体の不安定化を招きました。
●社会的な格差の拡大
安定した正規雇用が減少し、非正規雇用や派遣労働の比率が増加することで、社会的な格差が拡大するとの懸念も禁止の背景にありました。日雇い派遣は、とくに若年層や低所得者層に多く利用されていたため、彼らの生活基盤を守るために法規制が強化されました。
●国際基準への対応
ILO(国際労働機関)が求める労働者の保護基準に基づき、日本の労働法制も見直されました。安定した労働条件と雇用機会の提供を促進するため、日雇い派遣の規制が強化されることとなりました。
これらの理由から日雇い派遣は禁止されましたが、一部の業界では例外措置が認められています。規制によって労働環境の改善が進んだ一方、短期間の労働を希望する労働者にとっては選択肢が減少し、別の問題が生じるケースもあります。そのため、雇用の柔軟性と安定性のバランスを取ることが今後の課題とされています。
「単発バイト」と「日雇い派遣」の違い

「単発バイト」と「日雇い派遣」は、どちらも短期間の働き方ですが、契約形態や法律上の位置づけが異なります。労働者や企業にとって、これらの違いを理解することは非常に重要です。以下でその違いを詳しく解説します。
●雇用契約の違い
・「単発バイト」
単発バイトでは、労働者は雇用主(企業)と直接契約を結びます。例えば、イベント会社が直接アルバイトを雇い、1日や数日間だけ働いてもらう形です。この場合、労働者は企業の従業員として扱われ、賃金や労働条件は企業が直接管理します。
・「日雇い派遣」
日雇い派遣では、労働者は派遣会社と雇用契約を結びますが、実際の働き場所や指揮命令は派遣先企業が行います。派遣会社が労働者に賃金を支払い、労働条件を管理する一方で、派遣先企業が仕事内容を指示します。
●法律上の規制の違い
・「単発バイト」
単発バイトは「労働基準法」に基づく直接雇用であり、派遣法の規制を受けません。企業は労働基準法や最低賃金法などの基準を守る必要がありますが、契約期間や仕事内容の制限は比較的少ないです。
・「日雇い派遣」
日雇い派遣は「労働者派遣法」によって厳しく規制されています。とくに2012年の法改正以降、30日以内の派遣契約は原則禁止されており、一部の例外を除いて日雇い派遣を行うことはできません。
●労働条件と社会保険の違い
・「単発バイト」
単発バイトでは、契約期間が短期間の場合でも、労働基準法に基づいて残業代や休日手当などが支払われます。ただし、労働時間が短い場合には社会保険の加入義務は発生しないことがあります。
・「日雇い派遣」
日雇い派遣では、派遣会社が労働者を雇用しているため、賃金は派遣会社から支払われます。短期間でも社会保険の対象となることがありますが、派遣先での労働環境や条件の把握が困難なため、労働者の保護が十分でない場合がありました。
日雇い派遣を雇用する条件

原則禁止されている日雇い派遣ですが、特定の条件を満たす場合に限り、例外的に雇用することが認められています。日雇い派遣を利用できる条件は以下の通りです。
-
-
1.高収入の専門職(年収500万円以上など)
2.60歳以上の労働者
3.学生(昼間学生に限る)
4.副業として働く人(本業の年収500万円以上)
-
その詳しい内容・具体例を解説します。
1.高収入の専門職
年収500万円以上の労働者が対象です。特定の高度なスキルや専門知識を持つ労働者が、短期間の派遣で高い収入を得るケースがこれに該当します。
(具体例/ITエンジニア、コンサルタント、専門的な知識が必要な財務アドバイザー、通訳など)
2.60歳以上の労働者
60歳以上の労働者については、日雇い派遣が例外的に認められています。シニア層の就業機会を確保するための措置です。
(具体例/軽作業の補助、交通整理、小売店の販売サポートなど)
3.昼間学生
昼間部に在籍している学生は例外です。夜間学生は対象外となります。
(具体例/放課後や夏休み期間中の短期派遣スタッフ、学園祭などのイベント運営補助など)
4.副業として働く者(年収500万円以上)
副業を希望する労働者で、本業の年収が500万円以上の場合も日雇い派遣が可能です。労働時間の制約がある中で柔軟な働き方を求める人に適用されます。
(具体例/会社員が週末や休日に派遣先で行う短期間業務、専門資格を活かした短期コンサルティング業務など)
日雇い派遣の例外業務

社会的に必要性が高い特定の業務についても例外として許可されています。ここでは、日雇い派遣の例外として認められている業務とその理由を詳しく解説します。
-
-
1.ソフトウェア開発・機械設計
2.クリエイティブ業務
3.通訳・翻訳業務
4.秘書業務
5.ファイリング
6.その他の例外業務
-
その詳しい内容・具体例を解説します。
1.ソフトウェア開発・機械設計
高度な専門知識やスキルを必要とする業務で、短期間でも特定のプロジェクトにおいて専門家の協力が求められるケースがあります。
(具体例/新製品のソフトウェアプログラムを開発するための短期契約、生産ラインの新設や機械の設計・改善に関するコンサルティングなど)
2.クリエイティブ業務
芸術性や専門知識が必要な業務が該当します。これらの仕事はプロジェクトベースで行われることが多いため、日雇い派遣の形態が適しています。
(具体例/広告デザインやウェブサイトの制作、映像編集やコンテンツの制作補助など)
3.通訳・翻訳業務
通訳や翻訳は専門性が高く、短期間で特定の案件に対応することが多いため、例外的に日雇い派遣が認められています。
(具体例/国際会議での通訳、外国語資料の翻訳プロジェクトなど)
4.秘書業務
経営者や特定のプロジェクトチームのサポートを行う秘書業務も例外です。短期間であっても業務内容が限定的で、専門的な対応が必要です。
(具体例/役員の短期的なスケジュール管理や文書作成補助など)
5.ファイリング
文書やデータの整理・管理を行うファイリング業務も例外とされています。大量の資料を一時的に整理するための労働力を確保する目的で利用されます。
(具体例/年度末の文書整理業務、大型プロジェクト終了後の資料保管作業など)
6.その他の例外業務
その他の例外として認められる業務には、イベントの運営や設営、災害復旧、および一時的・季節的な業務が含まれます。
(具体例/コンサートや展示会の設営・撤収作業、台風や地震後の災害復旧作業、年末年始や収穫期の繁忙期における補助作業など)
日雇い派遣のメリット・デメリット

日雇い派遣は、短期間で労働力を確保したい企業や、柔軟に働きたい労働者にとって便利な仕組みです。しかし、法的規制が設けられる理由にもあるように、メリットだけでなく多くのデメリットも存在します。以下では、日雇い派遣のメリット・デメリットを詳しく解説します。
●労働者にとってのメリット
・短期間で収入を得られる
短期集中型の働き方ができるため、すぐに収入を得たい人にとって便利です。とくに、学生や副業希望者には柔軟な働き方が提供されます。
・柔軟な勤務時間の選択
勤務日や時間帯を選びやすいため、ライフスタイルに合わせて仕事を探すことが可能です。
・多様な業務経験を積める
イベントスタッフや軽作業など、さまざまな分野の仕事を短期間で経験できるため、スキルを広げたり、適性を見極めたりする機会になります。
●企業にとってのメリット
・即戦力として労働力を確保できる
急な欠員や繁忙期に素早く人手を補うことが可能です。とくにイベント運営やキャンペーンなどの期間限定業務では欠かせません。
・雇用リスクの軽減
労働契約が短期間のため、長期的な雇用リスクを回避できます。必要なときだけ人材を雇えるため、人件費の最適化にもつながります。
●労働者にとってのデメリット
・雇用の不安定さ
仕事が1日ごとに終わるため、次の仕事が見つかるかどうかの保証がありません。継続的な収入を得ることが難しく、生活基盤が不安定になります。
・社会保険への加入が困難
一定の条件を満たさない限り、日雇い派遣では社会保険に加入できません。そのため、将来の年金や医療保険の保障が十分でないリスクがあります。
・労働条件の悪さ
短期間の労働のため、十分な研修や労働環境の整備が行われない場合があります。安全管理の不備や過酷な作業条件に直面することもあります。
●企業にとってのメリット
・即戦力として労働力を確保できる
急な欠員や繁忙期に素早く人手を補うことが可能です。とくにイベント運営やキャンペーンなどの期間限定業務では欠かせません。
・雇用リスクの軽減
労働契約が短期間のため、長期的な雇用リスクを回避できます。必要なときだけ人材を雇えるため、人件費の最適化にもつながります。
●労働者にとってのデメリット
・雇用の不安定さ
仕事が1日ごとに終わるため、次の仕事が見つかるかどうかの保証がありません。継続的な収入を得ることが難しく、生活基盤が不安定になります。
・社会保険への加入が困難
一定の条件を満たさない限り、日雇い派遣では社会保険に加入できません。そのため、将来の年金や医療保険の保障が十分でないリスクがあります。
・労働条件の悪さ
短期間の労働のため、十分な研修や労働環境の整備が行われない場合があります。安全管理の不備や過酷な作業条件に直面することもあります。
●企業にとってのデメリット
・労働者の質やスキルが一定でない
派遣労働者は短期間のため、企業独自の研修や教育が行き届かず、業務の効率や品質にばらつきが出るリスクがあります。
・コンプライアンスのリスク
労働者派遣法に違反すると行政指導や罰則を受ける可能性があります。例外条件をしっかり確認し、適切な契約を結ぶ必要があります。
日雇い派遣の導入で企業が注意するポイント

日雇い派遣の利用は便利ですが、法的規制や雇用リスクを適切に管理しないと、違法行為とみなされ罰則を受ける可能性があります。ここでは、企業が日雇い派遣を導入する際に注意すべきポイントを解説します。
●法令遵守の確認
労働者派遣法の遵守は必須です。30日以内の日雇い派遣は原則禁止されており、例外条件に該当する場合のみ利用可能です。企業は、労働者の属性(学生、高収入労働者、60歳以上など)や業務内容を確認し、証明書類を適切に保管する必要があります。
●派遣先管理台帳の作成
日雇い派遣を利用する際には、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者の氏名、勤務日、業務内容などを記録・更新しなければなりません。さらに、台帳は法定期間(3年間)保管する必要があります。これにより、労働条件の透明性が確保されます。
●労働条件の管理
派遣元と協力して、労働者の労働条件通知書を交付し、給与や勤務時間、休憩時間を明確にします。また、残業や深夜労働が発生する場合には、派遣法および労働基準法に基づき適切な対応を行います。労働時間の管理責任は派遣元企業と派遣先企業の双方が負います。
●安全衛生の確保
派遣労働者の安全管理は、派遣先企業の責任です。労働環境を整え、必要に応じて安全教育や設備の使用方法を説明する必要があります。安全教育の実施記録を残す、危険を伴う業務では派遣労働者を使用しないことなどがポイントとなります。
●派遣元との緊密な連携
派遣元(派遣会社)と密接に連携し、労働者の管理や苦情対応、問題解決にあたります。とくに労働条件の変更やトラブル対応には迅速な協力体制が求められます。
【まとめ】企業と労働者にメリットも多いが、法令順守が最優先

日雇い派遣は便利な働き方ですが、法規制により利用が制限されています。企業が導入を検討する場合、例外条件を確認しつつ、労働者の安全性や法令遵守を最優先にすることが求められます。一方で、単発バイトなど代替手段を活用することも選択肢の一つです。
企業や派遣会社は、日雇い派遣を正しく理解し、違法にならないよう適切に運用することが求められます。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験&フリーター歓迎の正社員求人を多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、正社員就職に向けたサポート体制も充実! まずは下記ボタンをチェックして、お気軽にエントリー&ご応募ください!
