クレーンの種類と生かせる仕事は?運転に必要な資格についても詳しく解説
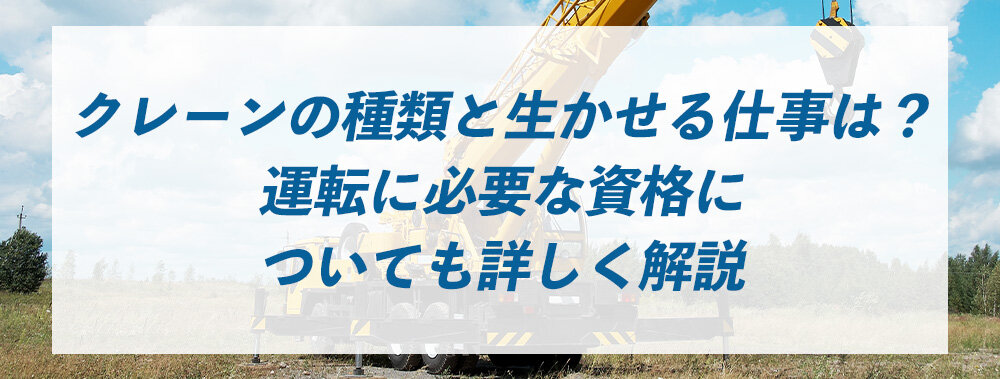
2024/6/13 更新
-
■目次
- 1.クレーンの定義とは?
- 2.クレーンの主な種類と特徴、使用用途について
-
・トラッククレーン
・ラフテレーンクレーン
・クローラークレーン
・ガントリークレーン
・ジブクレーン
・スタッカークレーン
・ケーブルクレーン
- 3.クレーンの運転・作業に必要な資格
-
・クレーン運転に必要な資格の種類
-クレーン運転特別教育
-床上操作式クレーン運転技能講習
-クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
-クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
-クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
・移動式クレーン運転に必要な資格の種類
-移動式クレーン運転特別教育
-小型移動式クレーン運転技能講習
-移動式クレーン運転士免許
・玉掛けに必要な資格の種類
-玉掛け業務特別教育
-玉掛け業務技能講習
・高所作業に必要な資格
-ロープ高所作業特別教育
-フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育(フルハーネス型安全帯)
- 4.クレーンの資格を取得する方法は?
-
・クレーン運転特別教育を取得するには
・床上操作式クレーン運転技能講習を取得するには
・クレーン・デリック運転士免許を取得するには
・移動式クレーン運転特別教育を取得するには
・小型移動式クレーン運転技能講習を取得するには
・移動式クレーン運転士免許を取得するには
・玉掛け業務特別教育を取得するには
・玉掛け業務技能講習を取得するには
・ロープ高所作業特別教育を取得するには
・フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を取得するには
- 5.各種のクレーン資格に取得する順番はある?
-
6.クレーン資格をとるための勉強や実技練習はどうすればいい?
- 7.クレーン資格は転職に生かせる?給与はアップする?
- 8.まとめ
クレーンの定義とは?
工場や建設現場などで、重量物を吊り上げたり、運んだりする際に活躍するクレーン。法的には、以下2つの条件を満たしたものを「クレーン」と定義しています。
●動力を用いて荷を吊り上げるもの(人力によるものと、吊り上げ荷重0.5トン未満のものは含まない)
●吊り上げた荷を水平に運搬することを目的とした機械装置(人力によるものも含む)
したがって、荷の吊り上げだけを行う機械や、吊り上げを人力で行う機械はクレーンとは呼びません。反対に、荷の吊り上げを動力で行えば、荷の水平移動を人力で行ってもクレーンに含まれるわけです。
また、吊上げ荷重0.5トン未満の機械は、法令の規制対象とならない(クレーンに含まれない)ため、運転・作業に携わるための資格は不要となります。
ちなみに、クレーンの一種として知られる「移動式クレーン」は、エンジンなどの原動機を搭載し、不特定の場所に移動可能なクレーンのことです。同じく「デリック」とは、本体とは別に設置されたウインチ(原動機付きの巻上機)から、ワイヤーロープを介して本体のアームの上げ下げ・旋回を行うものを指します。
クレーンの主な種類と特徴、使用用途について
クレーンは使用する場所や作業内容に応じてさまざまな種類があります。ここでは代表的な10種類のクレーンの特徴や使用用途について紹介します。
【トラッククレーン】
トラックの荷台と運転室の間に小型のクレーン装置を搭載した車両積載型の移動式クレーンで、3トン未満の荷物の吊り上げに使われます。また、トラックのシャーシを補強してクレーンを取り付けたレッカー型もあり、事故車や故障車、駐車違反車両の移動などに使われます。いずれも操作が比較的容易で、高速道路の走行が可能なのも特徴です。
【ラフテレーンクレーン】
ラフテレーンクレーンは、ひとつの運転室で走行と吊り上げの操作ができる移動式クレーンです。2軸4輪駆動式で小回りに優れており、市街地の狭い現場や未整備の変形土地、軟弱な地盤の土地などで使われます。
【オールテレーンクレーン】
高速道路を走行できるトラッククレーンと、整備されていない土地で活躍するラフテレーンクレーンのメリットを兼ね備えた移動式クレーンです。大型タイヤを装着し、国内最大級の550トン吊りまで対応できるものがあり、狭い場所で大きなパワーを必要とする現場で使われます。
【クローラークレーン】
ブルドーザーなどと同様の「クローラー(キャタピラ)」で地面と接して走行し、未舗装の地面や雪上での作業にも対応できる移動式クレーンです。他の移動式クレーンと比べて、さまざまな場所で作業できるというメリットがありますが、タイヤを装着していないため、公道を走ることや速く走ることはできません。
【ガントリークレーン】
レールの上を「トロリ(荷物を運搬する台車)」が走行する構造のクレーンで、「橋型クレーン」「ブリッジクレーン」と呼ばれることもあります。主に大型コンテナを運ぶ港湾作業などに使用されます。
【ジブクレーン】
「ジブ」と呼ばれる長いアームを備え、その先端から垂れ下がったワイヤとフックで荷物を吊り上げるクレーンです。このタイプは高さがあるため、屋外の建設現場や高所作業で使われます。
【スタッカークレーン】
建物の床や壁、部品を保管するラックなどに設けられたレール上を、前後・上下に走行するクレーンです。レール上であれば自由に行き来することができるため、多くの資材や部品を運ぶ工場や、荷物を保管する自動倉庫などで活用されています。また、スタッカークレーンには「天井クレーン」や「懸垂型」などのタイプもあります。
【ケーブルクレーン】
ケーブルカーのような構造を持ち、離れた2つの柱をつなぐメインロープに沿って「トロリ(荷物を運搬する台車)」が行き来するクレーンです。主にダム工事や河川改修、橋梁架設などの土木工事に使用されます。また、工場や倉庫などでも、ケーブルクレーンと同じ仕組みの「テルハ」と呼ばれるクレーンが利用されています。
クレーンの運転・作業に必要な資格
クレーンの運転・作業に必要な資格は、「クレーン資格」「移動式クレーン資格」「玉掛け資格」の3種類があります。
クレーン資格と移動式クレーン資格は、安全衛生法に基づいたクレーンやデリック、移動式クレーンの運転に必要な資格で、免許や技能講習、特別教育があります。玉掛け資格は、吊り荷の荷掛けや荷外しの作業に必要な資格で、技能講習と特別教育がありますが、玉掛け資格のみではクレーンの運転はできません。
では、それぞれの資格について詳しく見ていきましょう。
【クレーン運転に必要な資格の種類】
●クレーン運転特別教育
吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務ができます。
●床上操作式クレーン運転技能講習
吊り上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務ができます。5トン未満のクレーンを運転することも可能です。
※床上操作式クレーンとは、運転者が荷とともに移動するタイプのクレーンです。
●クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
吊り上げ荷重5トン以上の床上運転式クレーンの運転業務ができます。5トン以上の床上操作式クレーンや、5トン未満のクレーンの運転も可能です。
※床上運転式クレーンとは、運転者がクレーンの走行とともに移動するタイプのクレーンです。
●クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
吊り上げ荷重5トン以上を含むすべてのクレーンの運転業務ができます。
●クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
吊り上げ荷重5トン以上を含むすべてのクレーン、およびデリックの運転業務ができます。
【移動式クレーン運転に必要な資格の種類】
●移動式クレーン運転特別教育
吊り上げ荷重0.5トン以上1トン未満の移動式クレーンの運転業務ができます。
●小型移動式クレーン運転技能講習
吊り上げ荷重5トン未満の移動式クレーンの運転業務ができます。
●移動式クレーン運転士免許
吊り上げ荷重5トン以上を含む移動式クレーンの運転業務ができます。
【玉掛けに必要な資格の種類】
●玉掛け業務特別教育
吊り上げ荷重1トン未満のクレーンや移動式クレーン、デリックの玉掛け業務に就くことができます。
●玉掛け業務技能講習
吊り上げ荷重1トン以上のクレーンや移動式クレーン、デリックの玉掛け業務に必要な資格です。
その他、クレーン業務などで高所作業を行う際に必要な資格(特別教育)も併せて紹介します。
【高所作業に必要な資格】
●ロープ高所作業特別教育
足場が使えない高さ2メートル以上の場所で、ロープにぶら下がりながら高所作業を行う際に必要な資格です。
●フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育(フルハーネス型安全帯)
足場が使えない高さ2メートル以上の場所で、墜落制止用器具のうちフルハーネス型の安全帯を用いて作業する際に必要な資格です。
クレーンの資格を取得する方法は?
上項で紹介したクレーンや玉掛けなどの資格は、18歳以上であれば誰でも取得できますが、免許の種類によって、講習・試験を実施している場所(申込先となる機関・団体・教習所など)や、取得にかかる料金、日数、試験日、会場、取り扱いなどが異なります。
以下、各資格の取得に関する基本情報を紹介します。詳細については、受講・受験を申し込む際に、実施先へ直接問い合わせて確認しておきましょう。
【クレーン運転特別教育を取得するには】
クレーン運転特別教育は、全国各地のクレーン教習所や一般社団法人日本クレーン協会の支部、都道府県労働基準協会連合会などで実施しています。講習時間は13時間(基本的に学科・実技を合わせて2日間)で、すべてを受講すれば修了試験なしで取得できます。
クレーン運転特別教育の受講費用は、1万円台~2万円程度が目安です。
【床上操作式クレーン運転技能講習を取得するには】
床上操作式クレーン運転技能講習は、全国各地のクレーン教習所や一般社団法人日本クレーン協会の支部、都道府県労働基準協会連合会などで実施しています。講習時間は20時間(基本的に学科・実技を合わせて3日間)で、受講後の修了試験に合格すると取得できます。また、保有する資格によっては講習時間が短縮されます。
床上操作式クレーン運転技能講習の費用は、3万円~4万円台が目安です。
【クレーン・デリック運転士免許を取得するには】
クレーン・デリック運転士免許(各種)を取得するためには、全国7ヵ所(北海道、宮城県、千葉県、愛知県、兵庫県、広島県、福岡県)に設置されている安全衛生技術センターで行われる「学科試験」と「実技試験」に合格する必要があります。
また、各都道府県労働局長登録教習機関(クレーン教習所など)で「クレーン・デリック運転実技教習」を受講し、修了試験に合格すると実技試験が免除になります。
労働衛生技術試験協会によるクレーン・デリック運転士免許の受験料は、学科試験が6800円・実技試験が1万1100円です。
【移動式クレーン運転特別教育を取得するには】
移動式クレーン運転特別教育は、全国各地のクレーン教習所や企業事業所などで実施しています。講習時間は13時間(基本的に学科・実技を合わせて2日間)で、すべてを受講すれば修了試験なしで取得できます。
移動式クレーン運転特別教育の講習費用は1万5000円程度が目安です。
【小型移動式クレーン運転技能講習を取得するには】
小型移動式クレーン運転技能講習は、全国各地のクレーン教習所や都道府県労働局長登録教習機関などで実施しています。講習時間は20時間(基本的に学科・実技を合わせて3日間)で、受講後の修了試験に合格すると取得できます。また、保有する資格によっては講習時間が短縮されます。
小型移動式クレーン運転技能講習の費用は4万円程度が目安です。
【移動式クレーン運転士免許を取得するには】
移動式クレーン運転士免許を取得するためには、全国7ヵ所(北海道、宮城県、千葉県、愛知県、兵庫県、広島県、福岡県に設置されている安全衛生技術センターで行われる「学科試験」と「実技試験」に合格する必要があります。
また、各都道府県労働局長登録教習機関(クレーンの教習所)で「移動式クレーン運転実技教習」を受講し、修了試験に合格すると「実技試験」が免除になります。
労働衛生技術試験協会による移動式クレーン運転士免許の受験料は、学科試験が6800円・実技試験が1万1100円です。
【玉掛け業務特別教育を取得するには】
玉掛け業務特別教育は、全国各地のクレーン教習所などで実施しています。講習時間は9時間(基本的に学科・実技を合わせて2日間)で、すべてを受講すれば修了試験なしで取得できます。
玉掛け特別教育の講習費用は1万円台が目安です。
【玉掛け業務技能講習を取得するには】
玉掛け業務技能講習は、全国各地のクレーン教習所や都道府県労働基準協会連合会などで実施しています。講習時間は19時間(基本的に学科・実技を合わせて3日間)で、受講後の修了試験に合格すると取得できます。また、保有する資格や実務経験によっては講習時間が短縮されます。
玉掛け技能講習の講習費用は2万円台が目安です。
【ロープ高所作業特別教育を取得するには】
ロープ高所作業特別教育は、各都道府県の建設業労働災害防止協会(建災防)、労働技能講習協会、企業事業所などで実施しています。受講時間は7時間(学科・実技を合わせて1~2日間)で、すべてを受講すれば修了試験なしで取得できます。
ロープ高所作業特別教育の受講費用は1万円程度が目安です。
【フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を取得するには】
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育は、各都道府県の建設業労働災害防止協会(建災防)、労働技能講習協会などで実施しています。受講時間は6時間(学科・実技を合わせて1~2日間)で、すべてを受講すれば修了試験なしで取得できます。
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育の受講費用は、7000円~8000円程度が目安です。
各種のクレーン資格に取得する順番はある?
ここまで見てきたように、クレーンの資格にはさまざまな種類がありますが、クレーンを使う職場で働くのであれば、まず玉掛け資格を取得しておくといいでしょう。基本的にクレーン業務では、吊り荷の荷掛けや荷外しなどの作業が必ずありますので、玉掛け資格を持っていると重宝されます。
ただし、「玉掛け業務特別教育」の資格は、吊り上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けはできませんので、可能であれば荷重に制限のない「玉掛け業務技能講習」を取得するのがおすすめです。
また、クレーン運転の資格では、荷重に制限なくすべてのクレーン・デリックを運転できる「クレーン・デリック運転士免許(限定なし)」、荷重に制限なくすべての移動式クレーンを運転できる「移動式クレーン運転士免許」が最上位となりますが、はじめから上位の資格取得を目指すのはややハードルが高いかもしれません。
まずは、特別教育や技能講習などの限定資格を取得し、可能な範囲の実務でクレーンの知識や技術を養いながら、上位資格にチャレンジする人も多くいます。
クレーン資格をとるための勉強や実技練習はどうすればいい?
クレーン運転や玉掛けの特別教育・技能講習は、基本的に講習をしっかり受講すれば取得できますので、特別な受験対策は必要ないでしょう。
一方、クレーン・デリック運転士免許や移動式クレーン運転士免許を取得するには、筆記試験・実技試験の双方に合格する必要があるため、事前の受験勉強や実技練習が必須となります。クレーン業務に関する基礎知識が問われる筆記試験については、テキストや過去問題集が多数ありますので、独学で勉強することも可能です。ただし、実技試験ではクレーンの基本的な運転・操作の技術が問われるため、実際にクレーンを使って練習しなければいけません。
こうしたことから、クレーン・デリック運転士免許や移動式クレーン運転士免許を取得するためには、まずクレーンの教習所に通うのが一般的となっています。教習所では学科教習や実技教習があり、基本的に7日~10日間ほどで卒業できます。教習費用として10万円~17万円程度かかりますが、登録教習機関(認定教習所)で実技教習の修了試験に合格すれば、本試験の実技試験が免除になりますので、資格取得もぐっと近づくでしょう。
また、教習所によっては実技教習のみのコースも用意されていますので、教習費用を抑えつつ実技試験の免除を受けたい人は、学科のみ独学で勉強するという方法もあります。
クレーン資格は転職に生かせる?給与はアップする?
クレーンの運転資格や玉掛け資格は、いずれも有資格者のみが業務に携われる業務独占資格(国家資格)です。そのため、クレーン業務が欠かせない製造・物流・建設の現場などを中心に有資格者のニーズは高く、実務経験がなくても資格を持っていれば、転職・就職の際にも大きなアピールポイントとなります。
また、一般作業の従業員として工場などで働く際にも、クレーン運転や玉掛けの資格を持っていると対応できる業務や仕事の幅が広がり、それにともなって資格手当や昇給なども期待できるでしょう。
まとめ
今回は、さまざまなクレーンの種類や使用用途とともに、運転・作業に必要な資格について詳しく解説しました。
ご紹介したように、クレーンの運転資格は機種や吊り上げ荷重によって多くの種類があります。より幅広い業務に就くためには、上位となる運転士の資格が必要となりますが、荷重や機種によっては特別教育や技能講習でも運転業務に就くことができますし、クレーンを使う業務では玉掛け作業も欠かせません。
本記事を読んで興味を持った方は、まずは入門編として、クレーン運転や玉掛けの特別教育・技能講習を取得してみてはいかがでしょう。工場への転職・就職の際にも有利となりますし、仕事の幅や転職先の選択肢を広げる上でもきっと役立つはずです。
── 日総工産<工場求人ナビ>では、未経験者歓迎の工場ワークを多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職活動のサポート体制も充実。製造業やモノづくりの現場で働きたいニートの方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
