田舎で仕事! 地方へ移住するときのメリット・デメリットとは?
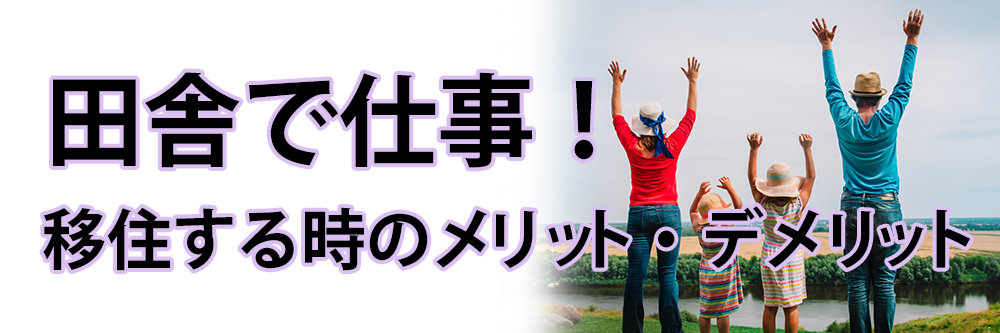
2023/9/13 更新
-
■目次
- ●あなたは、田舎のどんな場所で暮らしたいですか?
- ●2022年1月、東京都で“初”の「転出超過」に
- ●“幸せ”や“豊かさ”に対する考え方の変化で、地方移住に関心が高まる
- ●田舎暮らし、地方移住のメリット
-
1.【新たな仕事を始めたい人を政府、県、自治体がサポート】
2.【起業を支援する自治体も急増】
3.【広くて安い住居で、のびのび暮らせる】
4.【生活費(出費)が格段に減る】
5.【育て・教育・医療支援が充実している自治体も】 - ●田舎暮らし、地方移住のデメリット
-
1.【現地で新しい仕事に就くことは難しい場合も】
2.【子育て世帯にとっては不便さを感じることも】
3.【移動手段の公共交通機関が少ないのは当たり前】
あなたは、田舎のどんな場所で暮らしたいですか?
ひと口に「田舎」「地方」といっても場所によって気候、風景、特徴はさまざまです。総務省が公表した「国民意識調査」によると、下グラフのとおり、20〜39歳の63.7%が「地方の都市部」への移住を希望する結果に。この数字の背景には、「やっぱり、大型のショッピングモールや飲食店、店舗などが立ち並ぶ都市部が便利」という考えが窺えますね。
ところが、都市部希望者は世代が上がるごとに減少し、60歳以上の3割が「少し不便でもいいので、都市部から離れた農山漁村エリアでのんびり暮らしたい」と考えている結果になっています。

2022年1月、東京都で“初”の「転出超過」に
家賃の高い東京都心で通勤ラッシュや人混みにストレスを感じて暮らすよりは、豊かな自然環境下で広い家に住み、穏やかな気持ちで暮らしたいと考える人は以前から多かったものの、リモート(テレ)ワークが当たり前になったことがその思いに拍車をかけ、実際の行動に出る人が増加に転じたと言われています。そしてそれを裏付けるのが、東京都の転出者数が転入者数を1万4828人上まわり、初めて「転出超過」となった2022年1月の数字です。
その後、地方や東京近隣県から東京都へ転入する人が増えたことで、再び“東京一極集中”の兆しは強まっているものの、コロナ禍を機に多くの人が「人間らしい豊かな行き方ってどんな生き方だろう?」などと考えるようになり、地方に住むことで得られる豊かさや、都会では得られない魅力を見つめ直すようになったのです。
“幸せ”や“豊かさ”に対する考え方の変化で、地方移住に関心が高まる
都会暮らしのときに当たり前だと思っていたことも、田舎、地方では当たり前でないことがたくさんあります。
東京から信州に移住し、現地で新しい仕事に就いた30代の独身男性は、「近くにコンビニがないことに初めは少し不便さを感じたけど、買い出しを多めにしておけば問題ないし、夜中に意味なくフラッとコンビニに行っていた頃と比べて無駄遣いが減った」と話します。
あるいは、東京の企業に席を置きながら静岡へ移住を決めた30代夫婦も、「街を歩いているときの大音量の音楽や街にあふれる騒音に慣れてしまっていたけど、田舎暮らしを始めてからは鳥のさえずりや川のせせらぎが生活音になり、体と心が浄化されるような毎日を過ごしている」と話します。
このように大なり小なりの不便さはあるものの、人間本来のあるべき暮らしと心の豊さかを得られることに幸せや豊かさを感じている人も多いようです。とはいえ、自由度が高い単身者と、幼いこどもがいる家族では、地方移住を決断する際の希望条件は大きく異なってきます。いずれの場合もメリット、デメリットにしっかり目を向けて適切な判断をすることがとても重要です。

田舎暮らし、地方移住のメリット
1.【新たな仕事を始めたい人を政府、県、自治体がサポート】
最近は、地域の農業、林業、漁業、畜産業等の人材募集をサポートする自治体も増えているので、ある程度移住先を絞り込んだら、その自治体に就業サポートを行っているかどうか問い合わせてみましょう。自治体のHPをチェックしたり、オンラインの移住セミナーに参加することも有効な手段ですが、リアルタイムな情報を得るには「移住を考えているけれど、そちらに移住したときにどんないい点がありますか?」と電話で自治体の担当者に聞くことで、有効な情報を入手できることも。
また、政府、県、自治体が連携した「起業支援金・移住支援金」制度なども見逃せないポイントです。この制度は地方での転職希望者と、人材が欲しい地元企業をつなぐものですが、自治体によって支援内容はさまざまながら、対象企業で内定・就職をした単身者には60万円、世帯(2人以上の家族)には100万円が支給されるケースもあります。
2.【起業を支援する自治体も急増】
それまで培ったスキルをもとに地方で起業したい……、起業して地元に貢献したい……と考える人が増えていることを受け、起業者向けの支援制度を用意する自治体も増えています。
移住先で起業を考えている人は、政府が行う「起業支援金・移住支援金」の対象に該当する可能性が高くなりますので、「どんな内容の支援制度なのか」「支援を受けるためにどんな条件があるのか」を事前にしっかり確認しましょう。また、国の制度以外に、自治体独自の支援を用意しているところも多数ありますので、そちらのチェックも忘れずに!

3.【広くて安い住居で、のびのび暮らせる】
地方在住者の多くが、「東京の家賃相場は目玉が飛び出るほど高い」と口を揃えて言いますが、東京で暮らす単身者の多くが高い家賃のワンルームのマンションで暮らしています。そのため、東京の賃貸物件に住む人が地方に移住したときに最も変化するのが、住環境への出費といえるでしょう。
古民家などの空き家を安価で貸し出す自治体も数多くありますし、そのほかにも「1年以上住んでくれる人は家賃無料」「単身者=若者の家賃3万円以下の定住促進住宅」「移住した人に家をプレゼント(移住宅地譲渡)」「0円空き家バンク」など、安価&無料で住居に関する支援制度を用意し、移住を積極的に推奨する自治体も急増しています。
住環境に対する支援や特典は自治体によって異なりますので、住む地域がある程度定まった段階で、そのエリアではどのような住宅支援を行っているのかを、しっかり調べましょう。
4.【生活費(出費)が格段に減る】
生活費のなかで最も固定費の割合が高いのは家賃ですが、総務省が発表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると、木造ワンルーム(専有面積29平米以下)の相場が最も高い都道府県は東京で5万6481円。安いほうに目を向けると46位の大分県が3万2250円、沖縄県が3万511円で、全国平均は4万6098円になります。
例えば、“うどん県”で知られる香川県のさぬき市では、40歳未満の他県からの移住者には「家賃の2分の1または2万円のいずれか安価な額を最大2年助成」してくれるなど、移住者を対象にした「家賃支援補助金」や「助成制度」を用意する自治体も多くなっています。
5.【子育て・教育・医療支援が充実している自治体も】
幼児がいる世帯が地方移住を決断する大きな理由は、「自然の多い環境でのびのびと子どもに育ってほしい」という親御さんの思いといえるでしょう。実際に、地方に移住した幼児が2人いる4人家族は「まわりを気にせず思いきり遊べる」「山、海、川などの大自然を身近に感じた暮らしを通して、自然や美しいものに感動する心が養われた」「人、心、生命を尊重する心が育まれた」といった情操教育の面でメリットを感じているようです。
また最近は、子育て・教育支援の充実を目玉に、家族世帯の移住を推奨する自治体も増えています。「2歳から保育費無料」「赤ちゃん2人目まで50万円、3人目は100万円の出産支援」「22歳まで医療費全額助成」などを実施する自治体のほか、子育て・教育・医療以外に結婚、出産、就学時の祝い金など、趣向を凝らした支援制度を用意する自治体も増えていますので、家族で移住を考えている人は、どんなサポートを受けられるのか確認を忘れずに!
田舎暮らし、地方移住のデメリット
1.【現地で新しい仕事に就くことは難しい場合も】
過疎化が進み、主だった産業がない地域に移住した場合、その地で新しい仕事に就くことは難しいと言えますが、車やバイクで通える範囲(距離)に、大手メーカーが運営する工場などがないかを確認してみましょう。広大な敷地を要する大規模工場は人里離れたエリアにあることも多いですし、清流を使うアルコール飲料メーカーが不便な山あいに工場を展開していることも珍しくないので、現地で新たな仕事を探す人は近隣エリアの情報をしっかり下調べしましょう。
下調べをしたけれど、そうした工場がみつからないときは、人材募集を行っている地元の農業や漁業にも目を向けてみましょう。自治体によっては地場産業への転職支援を実施しているところもありますし、なかには本人が直接扉をたたいて、あっけないほど簡単に採用が決まったケースも! 地方の中小企業は慢性的な人手不足に悩んでいるところも多いので、住む地域がある程度定まったら、そのエリアではどのような就職・転職支援を行っているのか忘れずにチェックを!
2.【子育て世帯にとっては不便さを感じることも】
子育て・教育・医療に限らず、結婚、出産、就学など、自治体ごとにさまざまな支援を実施していますが、子育て・教育の面では都市部と同じ環境を整えるのは難しいかもしれません。
親御さんが車を運転して片道1時間以上かかる遠い場所の教室や習い事に通わせることができれば問題ありませんが、ピアノを習わせたい、水泳教室や学習塾に通わせたい、中学受験をめざしている……とう希望をもつ人は、居住地の近くにそうした教育施設や塾があるかどうかを調べたうえで、さらに、こどもさんが一人でそこに通うためときには、電車、バス、自転車などのどの交通手段を使ったらよいかなどを具体的にシュミレーションしておきましょう。

3.【移動手段の公共交通機関が少ないのは当たり前】
東京などの都市部と地方の日常生活での大きな違いは、なんといっても「足」にあります。網の目のように地下鉄が走る都心と異なり、田園風景が広がるエリアや山間部の集落などでは、「最寄りの駅まで遠い」「バスの運行本数が日に数本」「タクシーを使う際はその都度電話をかけて依頼する」といったことも珍しいことではありません。
そうしたエリアでは1人に1台車があると言っていいほど自家用車の利用率が高いので、移住する際にマイカーを準備することが必要最低限の条件になることも。「東京では車の必要がなかったから、わたしペーパードライバーなんです」と地元の人に言ったら、鼻で笑われてしまうかもしれませんので、くれぐれもご注意を(笑)。
