ブルーカラーとは?その職種や特徴、ホワイトカラーとの違いについて解説!
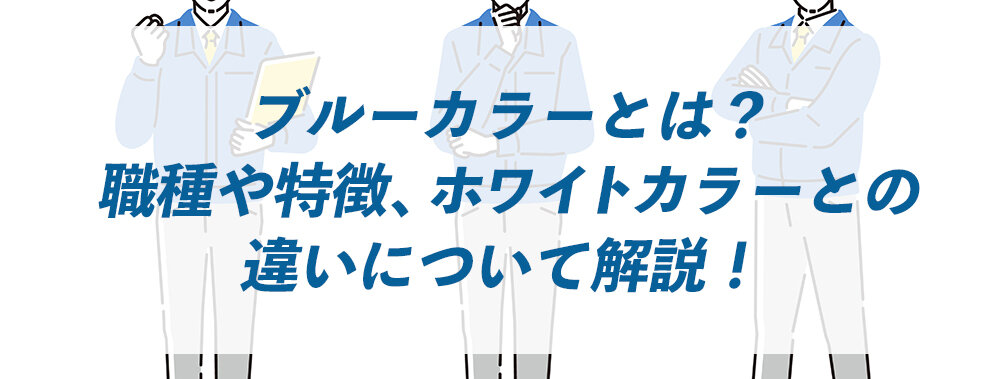
2024/2/6 更新
そもそもブルーカラーとは?
ブルーカラーの意味・言葉の由来
ブルーカラーとは、主に製造業・建設業などの生産現場で、生産工程や現場作業に直接従事する労働者のことを指す言葉です。現場の業務に直接携わる作業者や肉体労働者のほか、機械設備やインフラ系の特殊な作業を担う技術者もブルーカラーに含まれます。
ちなみに、ブルーカラーという言葉は、イギリスで産業革命が起こった1800年代、現場で働く労働者が着ていた作業着の「Blue Collar(青い襟)」が由来といわれています。
ブルーカラーの業種・職種
具体的には、主に以下の業種・職種がブルーカラーに属します。
-
-
【代表的なブルーカラーの業種・職種】
●製造業……工場で製造業務に従事する作業員、組立工、溶接工、旋盤工など
●建設業……土木・建設作業員、塗装工、溶接工、重機・クレーン操作者など
●運輸業……配送・トラック運転手、旅客機・旅客車運転者、クレーン操作者など
●農林水産業……農業・林業・畜産業・漁業など、第一次産業の仕事に携わる者
●鉱業……掘削作業者、重機・クレーン操作者など
●インフラ業……水道・ガス・電気・鉄道などの設備保守・点検に携わる者
●サービス業など……機械設備の整備・修理、清掃、警備などの業務に従事する者
-
ブルーカラーに対するホワイトカラーとは?
ホワイトカラーの特徴と主な職種

ブルーカラーが現場系・肉体労働系の仕事であるのに対し、ホワイトカラーはデスクワーク系・頭脳労働系の仕事に従事する労働者を指します。言葉の由来である「White Collar(白い襟)」とはワイシャツのことで、スーツを着てオフィスで働くビジネスパーソンなどがイメージしやすいでしょう。
具体的には、事務職・営業職・研究職・技術職・販売職・管理職など、生産現場の業務に直接携わらない職種を指します。とくに医療・金融・教育・IT系などは、ホワイトカラーが多い業種といえるでしょう。また、ブルーカラーが多い製造業などの企業で働いていても、営業職や管理職、経理担当者などはホワイトカラーに属します。
ブルー・ホワイト以外のカラーも
業種や職種が多様化する近年は、ブルーカラー・ホワイトカラー以外にも、新しい分類の「○○カラー」が登場しています。
-
-
【新しい分類の「○○カラー」の一例】
●グレーカラー……ブルーカラーとホワイトカラーの特徴を併せ持つ職業
●メタリックカラー……AI・IoTなどの最先端技術に携わる職業
●グリーンカラー……環境系の仕事に携わる職業
●ゴールドカラー……高いマネジメント能力を持つ起業家やコンサルタントなど
-
ブルーカラーとホワイトカラーの給与を比較
ブルーカラーとホワイトカラーの給与差は?

厚生労働省が発表した「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、産業別の平均賃金(月額)のトップ5は以下の通りとなっています。
-
-
【産業別の平均賃金トップ5(全年齢・男女計)】
《1》電気・ガス・熱供給・水道業……40万2000円
《2》学術研究、専門・技術サービス業……38万5500円
《3》情報通信業……37万8800円
《4》教育・学習支援業……37万7000円
《5》金融業・保険業……37万4000円
-
このように、平均賃金の高い業種は、1位を除いてホワイトカラーが多い業種となっています。ちなみに、同調査で建設業は33万3500円(8位)、製造業は30万1500円(9位)となっており、ブルーカラーが多い業種は、ホワイトカラーが多い業種と比べて、平均賃金が低い傾向にあることがわかります。
10代はブルーカラーの賃金が高い傾向に

一方、同調査で19歳以下の平均賃金を産業別に比較すると、上記の全年齢平均のランキングとは大きく変わり、ブルーカラーの業種の方が高くなる傾向にあります。
たとえば、ブルーカラーの代表業種である「建設業」が19万3800円(1位)、「製造業」が18万4100円(6位)であるのに対し、ホワイトカラーの代表業種である「情報通信業」は18万円(11位)、「金融業・保険業」は17万9000円(14位)、「教育・学習支援業」は17万3000円(15位)となっています。
この差は20代になると縮まり、25~29歳でほぼ逆転しますが、10代に関してはブルーカラーの方が平均賃金が高い傾向にあることから、ブルーカラーの業種に就職する新規高卒者には有利となるでしょう。
※参考資料/厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」
ブルーカラーのメリット
ここからは、ブルーカラーの仕事に就くメリットを、ホワイトカラーのデメリットと比較しながら見ていきましょう。
残業や休日出勤が少ない

現場業務が中心となるブルーカラーの職場は、稼働時間・作業時間が決まっていることが多いため、残業や休日出勤が少ない傾向にあります。とくに製造業の工場は、生産計画に基づいて稼働スケジュールや勤務時間が組まれているので、オン・オフを切り替えてメリハリのある働き方ができます。
一方で、パソコン作業が多いホワイトカラーは、時間や場所を選ばずに仕事ができるため、夜中までダラダラと仕事を続けたり、パソコンを持ち帰って自宅で作業する人も多いようです。とくにIT系のホワイトカラーの場合、納期に合わせて残業や休日出勤が発生することが多く、過重労働に陥りやすい傾向にあります。
専門スキルを身につけて転職しやすい

ホワイトカラーの職種は、企業ごとに仕事のやり方が異なる場合があり、身につけたスキルやノウハウが社内でしか通用しないことも多々あります。
一方、ブルーカラーは未経験からのスタートでも、その業種全般で生かせる現場スキルが身につく(手に職がつく)仕事が多く、経験を積めば即戦力として大手他社から求められることも。ブルーカラーは人手不足が深刻化している職種も多いため、資格取得などとあわせて自身のスキルを磨けば、より好条件で転職しやすいというメリットがあります。
ブルーカラーのデメリット
次に、ブルーカラーの仕事に就くデメリットについて、ホワイトカラーのメリットと比較しながら解説します。
3K(キツい・汚い・危険)の仕事が多い

現場で働くブルーカラーは、いわゆる「3K(キツい・汚い・危険)」の仕事が多い傾向にあります。職場や職種によっては夜勤や力仕事などもあり、それ相当の体力が求められるため、年齢とともに仕事を続けるのがキツくなるかもしれません。また、建設業・運輸業などの現場は、高所作業や重量物の取り扱いなど危険を伴う業務が多く、ちょっとしたミスや不注意が労災事故などにつながる可能性もあります。
一方で、ホワイトカラーはオフィスでのデスクワークが中心となるため、ブルーカラーと比べると比較的危険が少ない労働環境といえます。身体に負荷のかかる力仕事もほとんどないので、体力に自信がなくても就業でき、年齢を重ねても仕事が続けやすいでしょう。
給与が低く昇給しにくい

先述したように、ブルーカラーはホワイトカラーと比べて給与が低い傾向にあり、年齢とともに昇給しにくいのがデメリットといえます。とはいえ、ブルーカラーは現場業務に関する専門知識・技術の習得や資格取得により、さらなる給与アップが期待できますので、平均的な年収以上に稼ぐことも可能です。
まとめ
ご紹介したように、ブルーカラーは一貫して「現場の仕事」に携わる職種ですが、その業種は製造業や建設業、運輸業など多種多様です。したがって、ブルーカラーの仕事に就く際には、自分自身の適性に合った職業を見極めることが重要です。
たとえば、モノづくりが好きなら製造業、体力に自信があれば建設業、車の運転が好きなら運輸業など、自分の興味や得意分野に合わせて検討してみると、仕事の選択肢を絞りやすくなるでしょう。
製造業・工場のお仕事探しなら<工場求人ナビ>へ!
ブルーカラーを代表する製造業で働いてみたい方は、日総工産<工場求人ナビ>にご相談ください。日本全国のさまざまな工場の求人情報を多数掲載し、どの求人がいいのか迷っても、専門コーディネーターと相談しながら、あなたにぴったりなお仕事をスムーズに始められます。まずは、下記リンクからお気軽にエントリー&ご応募ください!
