年間休日105日はきつい?平均日数やメリット・デメリットを解説!
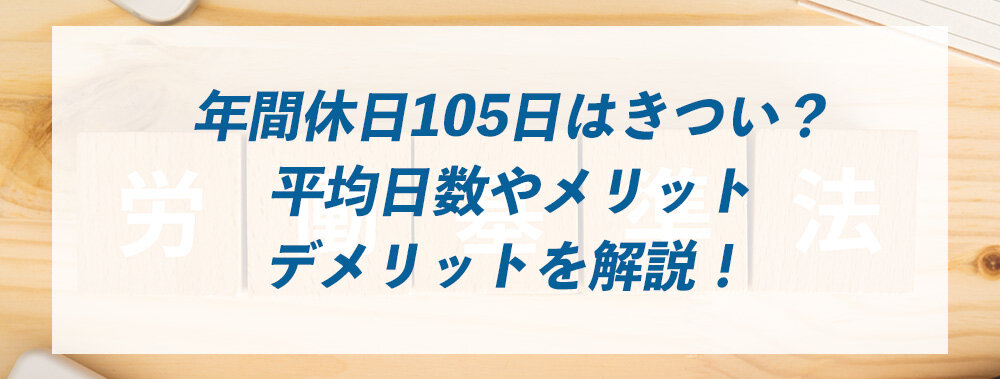
2024/11/29 更新
-
■目次
- 1.年間休日105日は労働基準法で最低限の日数?
-
・年間休日105日の内訳
・年間休日105日だと祝日や長期休暇は?
- 2.年間休日105日は少ない?平均はどれぐらい?
-
・年間休日の平均値
・年間休日105日はホワイト企業?
- 3.年間休日105日の企業で働くメリット
-
・収入が高い傾向にある
・残業が発生しにくい
・仕事のスキルを身につけやすい
- 4.年間休日105日の企業で働くデメリット
-
・ワークライフバランスがとりにくい
・長期休暇が取れない
・個人的な休暇が取りづらい
- 5.年間休日が多い業界・少ない企業は?
-
・年間休日が多い業界
・年間休日が少ない業界
- 6.休日・休暇に関して押さえておくべきポイント
-
・完全週休2日制と週休2日制は違う?
・休日と休暇の違いや有給休暇の扱いは?
- 7.休日・休暇に関して押さえておくべきポイント
年間休日105日は労働基準法で最低限の日数?
求人情報に記載されている年間休日とは、従業員全員に適用される1年間の休日数のことを指します。年間休日には、労働基準法で定められた法定休日(毎週1日または、4週で4日の休日)と、企業が規定で定めた所定休日(法定外休日)が含まれます。所定休日の内容は企業によって異なりますが、法定休日以外の休日(土曜、祝日など)や、ゴールデンウィーク・夏季・年末年始の長期休暇を所定休日として定めるケースが一般的です。
年間休日105日の内訳
コンビニバイトのメイン業務です。レジでの接客業務には、主に以下のようなものがあります。
【1週間に40時間働く場合の年間労働時間】
(365日÷7日)×40時間=2085時間
【1日に8時間働く場合の年間労働日数】
2085時間÷8時間=260日
【1年間(365日)から年間労働日数を引いた年間休日】
365日-260日=105日
上記のように1日8時間労働の場合、「年間休日105日」が法的に定められている最低限の日数となります。ただし、1日あたりの労働時間が短い場合や、労使間で36協定を結んでいる場合は、年間休日105日未満でも違法になりません。
年間休日105日だと祝日や長期休暇は?

1年はおよそ52週となるため、毎週土日が休みの場合の年間休日は「52週×2日=104日」となり、土日だけで最低ラインの105日にほぼ達してしまいます。また、1年間の祝日は16日あるため、土日・祝日休みの場合、年間休日は「104日+16日=120日」必要となります。
したがって、年間休日105日で毎週土日が休み(毎週2日休み)のケースでは、祝日の出勤が必要になるほか、長期休暇(ゴールデンウィーク・夏季・年末年始など)も取得できないことになります。もし祝日や長期休暇のタイミングで休みを取得したいのであれば、週休1日の週を作るなどの工夫が必要となります。
年間休日105日は少ない?平均はどれぐらい?
年間休日の平均値

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、国内全企業の平均年間休日は110.7日、労働者1人あたりの平均年間休日総数は115.6日となっています。したがって、法的に最低ラインとなる年間休日105日は、平均と比較して少ないといえるでしょう。
また、同調査で平均年間休日を企業規模別に見ると、従業員数が多い(企業規模が大きい)企業ほど年間休日が多いことがわかります(下記参照)。
-
-
●従業員数1000人以上の企業……平均年間休日116.3日
●従業員数300~999人の企業……平均年間休日115.7日
●従業員数100~299人の企業……平均年間休日111.6日
●従業員数30~99人の企業………平均年間休日109.8日
-
※参考資料/厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」
年間休日105日はホワイト企業?

一般的なホワイト企業の特徴としては、「年間休日が多い」「離職率が低い」「有給取得率が高い」といった点が挙げられるでしょう。とはいえ、年間休日が少なくても「必ず定時で帰れる」「給与水準が高い」「福利厚生が手厚い」といった点に魅力を感じる人もいます。
勤務先に求める条件は人によって異なりますし、年間休日105日の会社がホワイト企業であるかどうかの判断基準も人それぞれです。仕事を探す際には年間休日だけに注視せず、ほかの勤務条件も見ながら、自分に合った働き方ができるかどうかを考えることが大切です。
年間休日105日の企業で働くメリット
年間休日105日は「きつい」「少なすぎる」と感じる人もいると思いますが、休日が少ない働き方にはメリットとなる部分もあります。以下、年間休日105日の企業で働くメリットを見ていきましょう。
-
-
●収入が高い傾向にある
●残業が発生しにくい
●仕事のスキルを身につけやすい
-
収入が高い傾向にある

年間休日が少ない企業では労働時間が長くなるため、それに比例してもらえる給料も増える傾向にあります。とくに日給制・時給制を採用している企業の場合は、勤務した日数・時間で給料が変動するため、働いた分だけ給料がアップします。休日よりも収入を増やしたい人にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
残業が発生しにくい

年間休日が少ない企業は、祝日や長期休暇などで業務が滞らないため、年間を通して仕事量やスケジュールの見通しが立てやすく、イレギュラーのスケジュールで発生する残業も少ない傾向にあります。定時で帰れる仕事であれば、休日が少なくても終業後に自由な時間を確保できるので、日々のアフター5を大切にしたい人にはメリットとなるでしょう。
仕事のスキルを身につけやすい

労働時間が長くなれば、仕事に携わる時間が増えるため、短期間でも多くの実務経験を積んで、自身のスキルアップにつなげることができます。「仕事のスキルを早く身につけたい」「若いうちに自分の市場価値を高めたい」と考える人には、こうした点も大きなメリットとなるでしょう。
年間休日105日の企業で働くデメリット
一方で、年間休日105日には、やはり「休みが少ない」ことで生じるデメリットもあります。以下、年間休日105日の企業で働くデメリットを見ていきましょう。
-
-
●ワークライフバランスがとりにくい
●長期休暇(ゴールデンウィーク・夏季・年末年始など)が取れない
●有給などの個人的な休暇が取りづらい
-
ワークライフバランスがとりにくい

年間休日105日のデメリットとしては、まず「ワークライフバランスがとりにくい」という点が挙げられます。年間休日が少ないと、必然的に趣味や家事などのプライベートな時間が確保しにくくなります。祝日を含めてカレンダー通りに休みを取ることも難しいため、家族や友人と過ごす機会が減ってしまい、寂しい・つまらないと感じるかもしれません。
長期休暇が取れない

先述したように、年間休日105日では長期休暇(ゴールデンウィーク・夏季・年末年始など)がほとんど取れず、基本的に短い休みと仕事を繰り返すことになります。そのため、心身の疲労が溜まりやすく、ゆっくり羽を伸ばしてリフレッシュしたり、海外旅行に行ったりすることが難しくなるかもしれません。
個人的な休暇が取りづらい

年間休日が少ない企業は、業務スケジュールがタイトだったり、人手不足で業務量が多かったりする傾向があります。そうした状況で、有給休暇や育児休暇などを取得すると、周囲の従業員に負担をかけてしまうため、「自分だけ休むのは気まずい」「休んでいる間の仕事を頼みにくい」と感じて、個人的な休暇が取りづらくなるかもしれません。
年間休日が多い業界・少ない企業は?

ここからは、厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査の概況」をもとに、年間休日の多い業界・少ない業界をその特徴とともに紹介します。
年間休日が多い業界
労働者1人あたりの平均年間休日が多いのは、以下の業界です。
-
-
●電気・ガス・熱供給・水道業……労働者1人あたりの平均年間休日120.9日
●情報通信業……労働者1人あたりの平均年間休日119.8日
●複合サービス事業……労働者1人あたりの平均年間休日119.7日
●学術研究、専門・技術サービス業……労働者1人あたりの平均年間休日119.6日
●金融業・保険業……労働者1人あたりの平均年間休日119.1日
-
年間休日が多い業界は、完全週休2日制を採用する大手企業が多く、長期休暇も充実している傾向があります。とくに、情報通信業や複合サービス業はBtoB企業が多く、取引先に合わせて休みが取れるため、年間休日が多くなると考えられます。また、金融業の場合は、銀行法によって土日祝や年末年始に休むことが定められています。
年間休日が少ない業界
労働者1人あたりの平均年間休日が少ないのは、以下の業界です。
-
-
●宿泊業・飲食サービス業……労働者1人あたりの平均年間休日102.9日
●生活関連サービス業、娯楽業……労働者1人あたりの平均年間休日105.6日
●運輸業、郵便業……労働者1人あたりの平均年間休日106.6日
●鉱業、採石業、砂利採取業……労働者1人あたりの平均年間休日109.9日
●医療、福祉……労働者1人あたりの平均年間休日111.5日
-
宿泊業や娯楽業、飲食サービス業は、基本的に土日祝日が忙しく、お盆の時期やゴールデンウィーク、年末年始なども休みを取りにくいことが、年間休日の少ない理由と考えられます。また、運輸・医療・福祉などの業界は、エッセンシャルワークであるとともに、人手不足の企業も多いため、休みが少ない傾向にあるようです。
※参考資料/厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況」(業界別の最新データ)
休日・休暇に関して押さえておくべきポイント
求人欄に掲載されている情報には、休日・休暇についてさまざまな表記があります。ここでは、年間休日とあわせて確認したいポイントや、休日・休暇の違いについて解説します。
完全週休2日制と週休2日制は違う?


一見すると同じように思えますが、「完全週休2日制」と「週休2日制」はまったく異なります。完全週休2日制は、毎週必ず2日の休みがある(曜日は企業によって異なる)という制度のこと。一方で週休2日制は、週2日の休みが月に1回以上あるという制度です。「完全」が付いているかいないかで年間休日が大きく異なるため、求人欄を確認する際には見落とさないように注意しましょう。
休日と休暇の違いや有給休暇の扱いは?

「休日」とは、従業員に労働の義務がない日のことを指し、労働基準法が定める法定休日と、企業の規則によって定められた法定外休日が該当します。また「休暇」とは、労働の義務はあるものの、企業が労働の義務を免除した日のことを指し、企業が独自に定める法定外休暇と、労働基準法によって定められた法定休暇があります。
法定外休暇に該当する長期休暇(ゴールデンウィーク・年末年始、夏季など)は、従業員全員に対して一律に適用されるため、年間休日としてカウントされます。一方で、有給休暇は法的に「年5日以上取得させることが義務化」された法定休暇で、日数や取得するタイミングが個々の従業員によって異なるため、基本的に年間休日としてカウントされません。よって、求人を検討する際には、年間休日だけでなく、有給の取りやすさや日数などもしっかり確認しておきましょう。
まとめ 休日数以外の条件もしっかりチェックしよう!

法的に最低ラインとなる年間休日105日は、ワークライフバランスがとりにくい傾向があるのも事実ですが、休日の少なさは必ずしもマイナスになるわけではありません。「休日が少なくても残業がない方がいい」「休日よりも収入を増やしたい」「スキルアップを優先したい」など、勤務時間・収入・スキルという点でメリットが大きいと考える人もいるでしょう。
仕事選びで後悔しないためには、自分の目的や重視したい条件にマッチしているかどうか、総合的な観点から見極めることが重要です。年間休日を重視して求職活動を行う場合でも、まず自分が働く上で外せない条件を洗い出し、休日以外の希望条件に優先順位をつけておけば、仕事選びをよりスムーズに進められるでしょう。
――日総工産<工場求人ナビ>では、未経験歓迎の工場ワークや正社員募集の求人を多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職に向けたサポート体制も充実!社内ニートから転職したい方も、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!
